〜トクニソウギノマエにネムタイワダイモウイイんだよ〜
いつもと変わらない8時、昨日は無しにして、「大きめの声」での「おざっす」が大事。。。

【たった一度の送別にかける情熱】
遺族の想い、仲間の絆、届ける信念
私は小さな葬儀社で働いています。ここでの日々は、ただ業務をこなすだけではなく、人の人生の最終章に寄り添う、かけがえのない時間の連続です。私たちの仕事は、故人と遺族を結びつけ、その最後の時間を最高の形で演出すること。その中には、家族葬のようにごく近しい人々だけで静かに送り出すものもあれば、地域全体が関与し、盛大に行われる盆藏儀のような大規模な送別もあります。一つひとつの葬儀には、故人と遺族の特別な物語があり、その瞬間はこの世でたった一度きりの重要なものです。
だからこそ、私たちは遺族の心に深く刻まれるような葬儀を提供するために何ができるかを常に考えています。その答えは一つではありません。ときには、遺族の思い出をより鮮やかに引き出すために、故人が大切にしていた曲を葬儀で流す提案をしたり、故人が好きだった花を祭壇にあしらうなど、細やかな演出に力を入れることもあります。また、遠方から訪れる親族のためにスケジュールを調整し、すべての人が「送る瞬間」に立ち会えるような工夫を施すこともあります。こうした努力が報われ、遺族が感謝の言葉をかけてくださったときの喜びは、この仕事ならではのやりがいです。
しかし、現実の現場では美談だけでは済まない一面もあります。人々の悲しみや緊張感が最高潮に達している場面では、小さな行き違いや意見の不一致が大きなトラブルに発展することも珍しくありません。例えば、故人の葬儀の形式について家族間で意見が対立したり、親族同士の確執が表面化したりする場面に立ち会うこともあります。そのようなとき、私たちは感情の矢面に立たされ、時に板挟みになることもあります。また、事務的な手違いが発覚した場合や、スケジュールが予期せぬ形で狂った際には、迅速な対応が求められます。
私自身、そうした混乱の一因となってしまうこともあります。未熟な判断やコミュニケーション不足が原因で事態を悪化させてしまった経験もあります。しかし、そうした状況から逃げることなく向き合い、改善を目指すことが私の成長に繋がっていると感じます。スタッフ同士が意見を出し合い、解決策を模索しながら乗り越えるプロセスの中で、職場の絆が深まることもあります。何より、どんなに難しい状況でも、最終的に遺族が「良いお別れだった」と思えるような葬儀を提供できたとき、私たちは全力を尽くした甲斐を感じます。
送別の瞬間は二度と訪れることはありません。それは同時に、私たちが手掛ける葬儀が一回きりの挑戦であり、完璧を目指すべき瞬間であることを意味します。その挑戦に情熱を注ぎ続けることで、遺族にとってかけがえのない時間を提供できると信じています。
【悩ましい人間関係と葛藤】
仕事において、チームの中での人間関係や価値観の違いは避けられない課題です。私にとってその象徴ともいえるのが、上司であるジェームスとの関係です。彼は私より若いながらも管理職としての地位についており、非常に合理的で効率を重視するタイプです。その姿勢は、チームを動かし、プロジェクトをスムーズに進行させるためには必要不可欠であると認めざるを得ません。しかし、彼が冷淡な態度で指示を出すときや、こちらの努力を軽視するような発言をすると、内心苛立ちを覚えずにはいられません。特に、「これが早く終われば、それでいい」というような物言いには、どうしても私の「過程にこそ価値がある」という信念と相容れないものを感じてしまいます。
ジェームスにとっては、結果を出すことが何よりも優先されます。一方で私は、故人や遺族との信頼関係を築きながら、細部にまで心を配るプロセスこそが、この仕事の本質だと信じています。この価値観の対立は、些細なやりとりの中でも表面化します。例えば、故人の趣味や個性を反映した祭壇のデザインを提案した際、ジェームスが「その時間をもっと効率的な業務に回せ」と一蹴したことがありました。その瞬間、自分の努力が否定されたように感じ、悔しさがこみ上げました。しかし同時に、彼の視点には学ぶべき点があることも理解しています。結果を追求する姿勢を見習いつつ、自分の信念をどう守り抜くか――この葛藤が、私の中で常に続いています。
さらに、もう一人の悩みの種が副社長のジョーです。彼はこの業界での経験が長く、昔ながらのやり方に深い信頼を寄せています。そのため、私のように「もっと遺族に寄り添える新しいサービスを取り入れるべきだ」という提案には、ほとんど耳を貸しません。以前、私は葬儀に故人の生前の思い出を映像で振り返る演出を加えることを提案しましたが、彼の反応は「そんな余計なことにリソースを割くな」の一言で片づけられました。その時の失望感は今でも忘れられません。ジョーのような保守的な考え方は、安定感をもたらす一方で、新しい挑戦の障壁になることも多いのです。
それでも、私はこのような反応を受けるたびに、自分の信念が揺らぎそうになるのを必死に抑えています。この仕事を始めた理由、そして私が目指す「人に寄り添う葬儀」という理想を見失わないように、自分に言い聞かせています。ジェームスやジョーとのやりとりを通じて、自分の考えをただ押し通すのではなく、彼らの意見に耳を傾けながらも、どうやって信念を実現していけるのかを模索することの重要性を学んでいます。対立や葛藤は避けられないものですが、それを乗り越える中で、自分自身も成長しているのだと信じています。そして最終的には、チーム全員が納得のいく形で遺族に寄り添える葬儀を作り上げることを目指して、私はこれからも試行錯誤を続けていくつもりです。
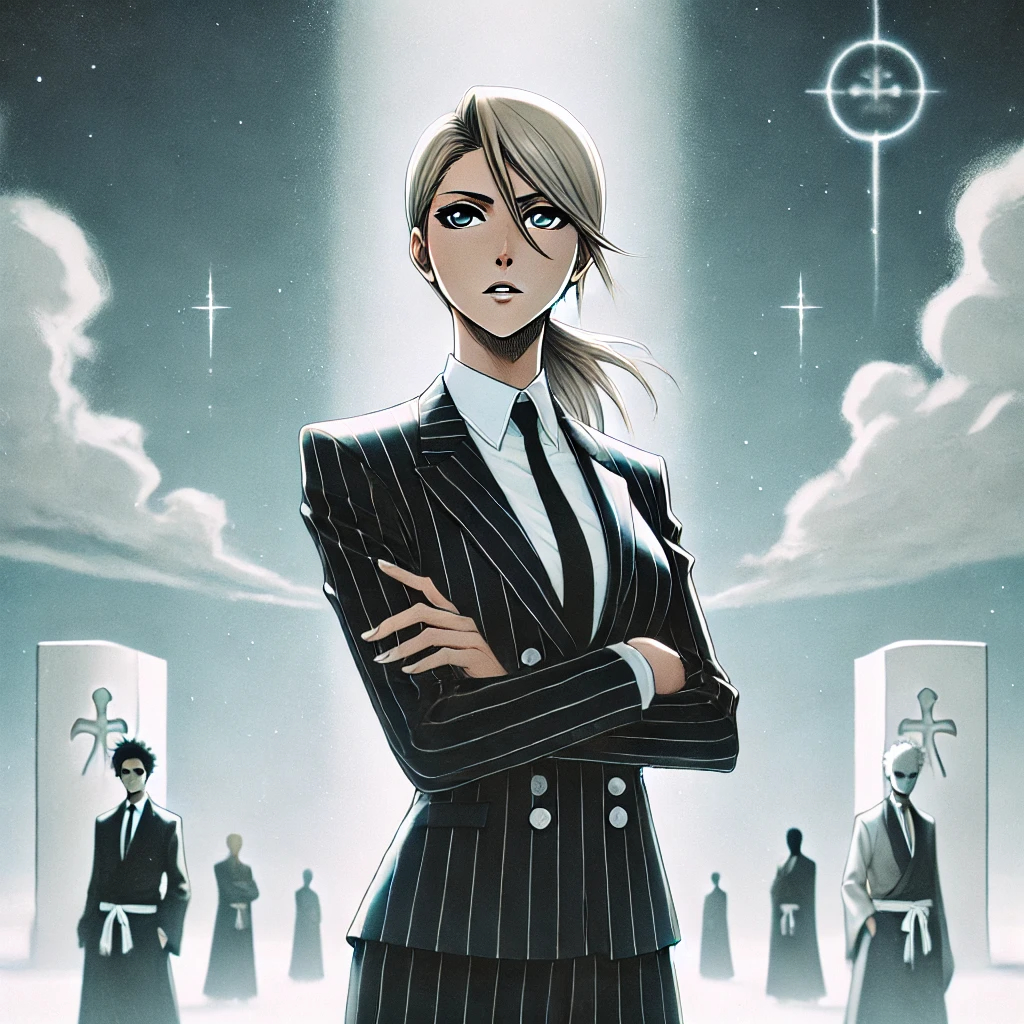
また、同僚のサリーとの関係も私にとって試練の一つです。彼女は非常に真面目で優秀なスタッフであり、仕事への責任感も強く、尊敬すべき存在です。しかし、その一方で、仕事の優先順位や取り組み方について意見がぶつかることが少なくありません。例えば、私は遺族の気持ちに寄り添い、少しでも多くの希望を反映することを優先すべきだと考えています。一方でサリーは、限られた時間とリソースを最大限に活用するために、効率を重視する傾向があります。どちらも正しいと信じているからこそ、意見が平行線をたどり、話し合いが噛み合わないこともしばしばです。
印象的だったのは、ある家族葬の準備を進めていたときのことです。遺族が故人の趣味を反映した特別な演出を希望されていたのですが、それには追加の時間と手間が必要でした。私はその希望を叶えるべきだと主張しましたが、サリーは「他の業務に支障が出る」と懸念を示しました。その議論は次第にヒートアップし、最終的にはお互いに納得しないまま、気まずい空気の中で作業を続けることになってしまいました。その日の帰り道、私は自分の主張がどこまで正しかったのか、彼女の意見をもっと尊重するべきだったのかと自問自答しました。
こうした状況は決して望ましいものではありませんが、それでも私たちは遺族にとって最善の形を目指して、妥協点を見つける努力を続けています。たとえば、後日改めて冷静な状態で話し合い、双方の意見をすり合わせる時間を設けるようにしています。また、サリーの効率を重視する姿勢がどれほど貴重かを理解し、彼女もまた私の遺族への配慮を重要視してくれていることを確認した瞬間、少しずつ信頼関係が深まっていると感じます。
サリーとのやりとりを通じて学んだのは、仕事の中での意見の違いは必ずしも悪いことではないということです。むしろ、その違いがあるからこそ、新しい視点や改善の余地が生まれるのだと思います。重要なのは、その違いを乗り越えるためにお互いを尊重し合い、目標を共有することです。遺族に寄り添い、最善の形で故人を送り出すという共通の目的がある限り、私たちは衝突を糧にしてより良いチームになれると信じています。

【私の哲学——めんどくさいヤツでいい】
そんな困難の中でも、私がこの仕事を続けられる理由。それは「遺族にとって最高の葬儀を提供する」という揺るぎない信念があるからです。この信念があるおかげで、どんな壁にぶつかっても立ち止まることはありません。この仕事には、時に重圧や葛藤、そして周囲との摩擦が伴いますが、それらを乗り越える原動力となっているのは、この信念以外にありません。
時には、「そこまでやらなくてもいい」「もっと割り切って考えればいい」と周囲から助言されることもあります。効率を重視し、結果だけを追求することが、ある意味でこの業界の常識とされる部分もあります。確かに、それは現実的な選択肢かもしれません。しかし、私にはそのように妥協することはできません。遺族にとって葬儀は人生の中でたった一度の特別な時間です。悲しみの中でも故人との最後のひとときを心に刻むこの時間を、適当に済ませるわけにはいかないのです。
正直なところ、自分でも「めんどくさいヤツだな」と思うことがあります。理想を追求するあまり、周囲と衝突してしまうこともあります。たとえば、ある葬儀で、遺族がどうしても実現したいと望んだ細やかな演出を提案した際、「それは予算やスケジュール的に無理がある」と一蹴されたことがありました。それでも私は何とかして遺族の希望を叶えようと、他のスタッフや上司に何度も掛け合い、最終的には協力を得ることができました。その過程で、「お前のやり方は面倒だ」と言われることもありましたが、遺族の方が満足そうに感謝の言葉を伝えてくれたとき、全ての苦労が報われたと感じました。
また、自分のこだわりが原因で周囲に迷惑をかけているのではないかと悩むことも少なくありません。「他のスタッフの負担を増やしてしまったのではないか」「もっとスムーズに進める方法があったのではないか」と自問自答する日もあります。それでも、遺族の方々から「あなたが担当してくれて本当に良かった」と涙ながらに感謝される瞬間があると、そのすべての悩みや葛藤が吹き飛びます。
私が理想を追い続けるのは、自己満足のためではありません。ただ一度の送別の時間を、遺族にとって忘れられないものにするためです。それが、たとえ「めんどくさいヤツ」と思われても、周囲と衝突しても、私が譲れない理由です。そして、そんな私の信念が少しでも誰かの心に届き、葬儀が単なる悲しみの場ではなく、温かい思い出として残る時間になるのであれば、私はこれからも「めんどくさいヤツ」であり続けようと思っています。

【最後に見えた光】
先日、特に心に残る家族葬を担当しました。そのご家族は非常に温かい方々で、悲しみの中にも故人への愛情と感謝が溢れていました。葬儀の準備が進む中で、遺族の方々は私たちスタッフ一人ひとりに何度も感謝の言葉をかけてくださいました。「こんなに親身になってくれるなんて思いませんでした」と微笑むその姿に、私自身も励まされる思いでした。
この葬儀をきっかけに、チーム全体にも変化が訪れました。ジェームスは、効率を重視する彼らしくも遺族への配慮を忘れない対応を見せてくれました。彼は迅速に物事を進めながらも、遺族の希望を最大限に叶えられるよう調整に奔走し、彼らからの信頼を得ていました。一方で、サリーもまた、自分の得意分野で全力を尽くし、細部にまでこだわった準備で葬儀の完成度を高めてくれました。彼女とのこれまでの衝突が嘘のように、私たちは共に理想を追い求める仲間として協力できているのを感じました。
そして、何よりも驚いたのは、副社長のジョーが「今回の仕事は良かったな」と声をかけてくれたことです。保守的な姿勢が強い彼が私たちの努力を認め、さらには「こういう形なら今後も取り入れていけるかもしれない」と言葉を続けた瞬間、胸が熱くなるのを感じました。これまで数多くの意見の対立や葛藤を乗り越えてきたからこそ、その言葉の重みは計り知れませんでした。
その瞬間、私は改めて気づきました。どんなに価値観が異なり、意見が対立しても、どれだけ衝突があっても、最終的には「故人と遺族のために」という共通の目標が私たちをつなげているのだと。そして、その目標に向かって全員が力を合わせたとき、私たちの仕事は本当に意味のあるものになるのだと実感しました。
もちろん、これからも葛藤や悩みが消えることはないでしょう。新しい挑戦には常に反発や困難がつきものです。しかし、それらの一つひとつが、遺族にとっての最高の送別を作り上げるための大切なピースなのだと思えるようになりました。どんなに小さな努力や妥協が、全体の完成度に影響を与えるのかを、この葬儀を通じて深く学びました。
だからこそ、私はこれからも「めんどくさいヤツ」であり続けようと思います。時に周囲を巻き込みながらも、遺族の心に寄り添い、仲間と共にたった一度の送別を形にする。そのために、この仕事に全力を注ぎ続けていきたいのです。そうして少しでも多くの人の心に残る時間を届けることで、この仕事が本当に必要とされているものだと証明していきたいと強く願っています。

【このブログを読んでくださった皆さまへ】
葬儀という仕事は、悲しみと希望が交差する特別な場です。その場に立ち会う私たちには、大きな責任と同時に、人々の人生の一部に触れるという特別な使命があります。日々の仕事の中で、私たちはさまざまな感情や出来事に向き合いながら、試行錯誤を繰り返しています。決して平坦な道ではありませんが、その分だけ得られる喜びややりがいがある仕事です。
このブログを通じて、私たちが葬儀という仕事に込める想いや、その裏側で奮闘している現実の一端を知っていただけたなら、とても嬉しく思います。葬儀はただの形式ではなく、遺族の悲しみを癒し、故人の思い出を未来へつなぐための大切な儀式です。その一瞬一瞬を最高の形で支えるために、私たちはこれからも努力を続けていきます。
また、この仕事には、さまざまな葛藤や難しさも伴います。それでも私たちは、遺族の想いを最優先に考え、どんな困難な状況でも寄り添う姿勢を忘れないようにしています。その想いが少しでも伝わり、葬儀というものが単なる悲しみの場ではなく、大切な人を送り出す温かい時間であることを感じていただけたなら幸いです。
最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。これからも、たった一度の送別を最高の形にするため、日々成長し続けたいと思います。どうか、これからも私たちの取り組みを温かい目で見守っていただければ幸いです。皆さまのご意見やお考えもぜひお聞かせください。それが私たちの力になります。



