葬儀社が対応する理由を現場目線で解説
突然、警察から
「ご遺体の引き取りについてお話があります」
そう連絡が来たら、多くの人は混乱します。
このとき言われるのが 「警察案件」 という言葉。
しかし、これは特別な事件だけを指す言葉ではありません。
この記事では、
- 警察案件とは何か
- なぜ葬儀社が遺体引き取りを行うのか
- 家族が知っておくべき現実と注意点
を、実際の現場に基づいて 解説します。

今回は警察署での遺体引き取りについて、私自身の体験談をもとに書いていきたいと思います警察案件とは?実はとても幅が広い
「警察案件」と聞くと、
事件・事故・犯罪を想像しがちですが、実際はもっと広い概念です。
警察案件になる主なケースは以下の通りです。
- 自宅で亡くなり、医師の死亡確認がすぐできない
- 孤独死で発見まで時間がかかった
- 死因がはっきりしないため検視が必要
- 事故死・自殺・他殺の可能性がある
- 身元確認が必要な状態
つまり、
「死因が明確でない状態で発見された死亡」
これが警察案件になる最大の理由です。
オススメ記事 中央線のオレンジは本当に飛び込みを誘発するのか?
なぜ警察が遺体を引き取らないのか?
ここで多くの人が疑問に思います。
「警察案件なら、警察が最後まで対応するのでは?」
結論から言うと、
警察は“捜査・確認”が役割で、葬送は担当外 です。
警察が行うのは主に👇
- 現場確認
- 検視・司法解剖の判断
- 死因・事件性の有無の確認
- 書類手続き
これらが終わると、
遺体は“引き取り待ち”の状態 になります。
そこで登場するのが葬儀社です。

警察案件で葬儀社が担う役割
警察案件における葬儀社の役割は、一般葬儀とは少し違います。
主な対応内容
- 警察署・監察医施設へのお迎え
- 遺体の搬送・安置
- 衛生処置(必要に応じて)
- 家族への説明と段取り整理
- その後の葬儀・火葬の相談
特に重要なのが
「すぐに引き取らないといけない」 という現実。
警察施設は長期安置を前提にしていないため、
家族が迷っている間も時間は進みます。
読んで欲しいブログ 💰 2026年、最初に備えるべき“お金”の話:葬儀のプロが教える年末の最低限チェックリスト
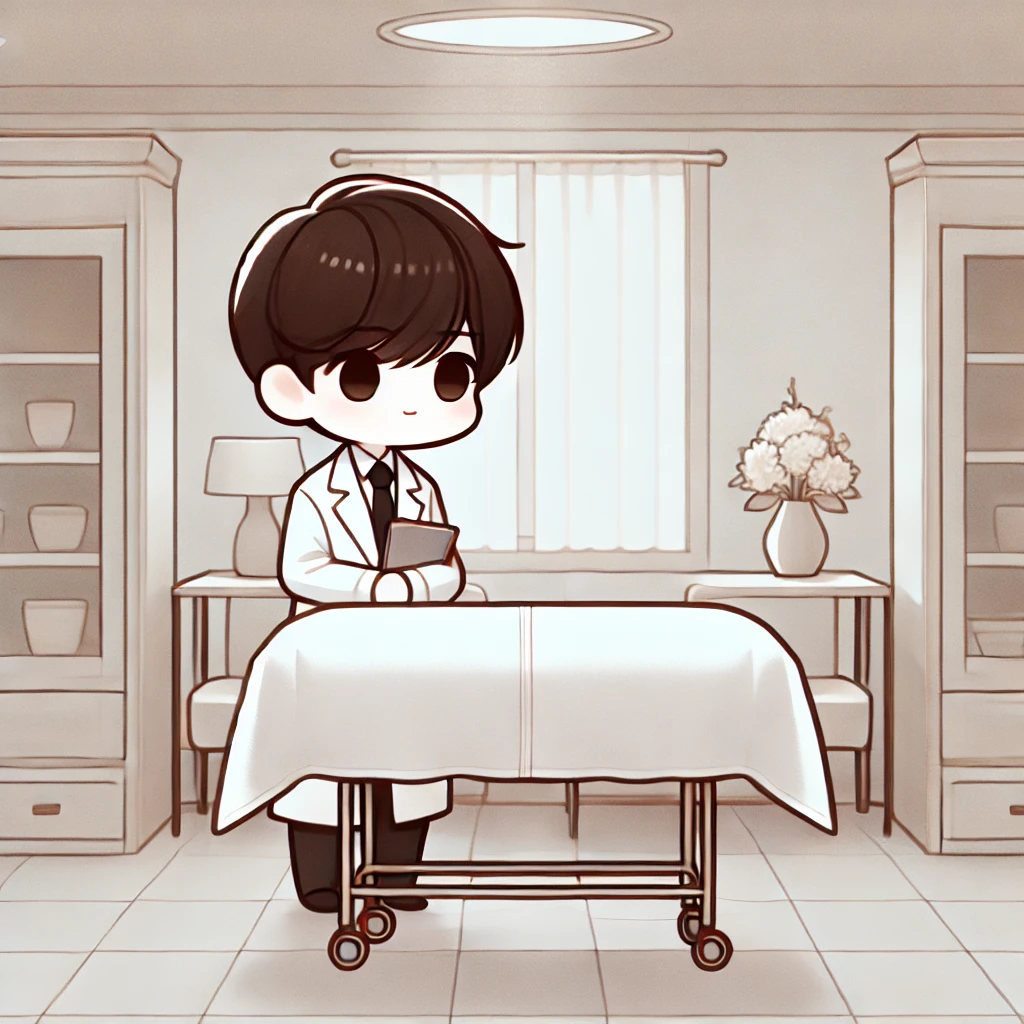
「警察案件=高額」ではない
もう一つ、よくある誤解があります。
警察案件だと費用が高くなる?
実際には、
- 搬送距離
- 安置日数
- 処置の有無
によって変わるだけで、
警察案件だから特別高額になるわけではありません。
ただし、
- 状態によっては処置が必要
- 通常より搬送距離が長い
といったケースでは、費用が増えることもあります。
重要なのは
「内容を説明されているか」 です。

まとめ|警察案件は「特別」ではない
警察案件は、
- 事件性が確定したもの
ではなく、 - 確認が必要な死亡
という位置づけです。
葬儀社が対応するのは、
警察の仕事を引き継ぐためではなく、
「家族の元へ戻す役割」 を担っているから。
もし警察案件に直面したときは、
慌てず、説明を受け、
選択肢があることを忘れないでください。



