お葬式に参列したあと、心身ともにどっと疲れることはありませんか?
大切な人との別れに加え、慣れない場での長時間の移動や緊張感…。
そんな中でも、帰宅後にきちんとした“清め”や“手続き”をすることで、心も身体も整いやすくなります。
本記事では、葬儀後に行う塩での清め方から、香典返しの整理・遺族へのお礼まで、7つのステップに分けて詳しく解説します。

1. 【玄関先で】塩を使った清め方とその作法
お葬式の後、自宅に入る前に「塩で清める」という風習をご存じですか?
これは、故人の“死”を穢れ(けがれ)とみなす古い風習に基づくもの。仏教では死を穢れとしない立場もありますが、地域や家庭のしきたり、年配者への配慮として行われることがあります。
塩で清める正式な手順
- 事前に塩を用意
小さな紙袋や器に盛っておきます。 - 玄関の外で立ち止まる
- 右肩→左肩→足元の順に振る
- 衣服についた塩を手ではたき、余分な塩は地面にまく
- 塩をまいた場所は踏まないように家に入る
- 家族全員が同じように清める
💡ワンポイント:
地域によってはこの風習がない場合も。親族や近隣の方に事前確認をしておくと安心です。

2. 【感染症対策にも】帰宅後は手洗い・うがいを忘れずに
塩で清めたあとは、手洗い・うがいでしっかり衛生管理を。
葬儀会場は多くの人が集まるため、風邪やウイルス感染のリスクも考えられます。とくに冬季や流行期には、早めの手洗い・うがいを心がけましょう。

3. 喪服や小物の手入れは早めに
長時間着用していた喪服は、しわ・ホコリ・汗などが気になるもの。次の法要や万一の際に備えて、丁寧にメンテナンスしておきましょう。
靴・カバン・ネクタイなども確認を
ホコリはブラシや手で払い落とす
クリーニングに出す場合は喪服用の扱いがある店を選ぶ

4. 香典返しやいただいた品物の整理
葬儀・通夜のあと、香典返しや供物を受け取って帰るケースも多いです。
これらは帰宅後すぐに整理しておくと、次の法要やお礼の準備がスムーズになります。
香典返しの例
- お茶・のり・お菓子などの詰め合わせ
- 賞味期限を確認し、早めに分配or保管
いただき物
- 花は水を替えて長持ちさせる
- 名簿や手帳に「誰から何をいただいたか」を記録しておくと便利
5いんき)に向けての準備をする際にも、誰から何をいただいたか記録しておくとスムーズです。
5. 必要なら「お供え」の準5. 四十九日や命日に向けた「お供え」の準備
葬儀後、親しかった故人への供養として、後日「お供え」をする習慣があります。
お供えのタイミング
- 四十九日法要(忌明け)
- お盆・命日
- 初七日・満中陰忌(地域による)
よく選ばれるお供え品
- お線香・お花
- 日持ちするお菓子や果物
- 地元の名産・故人の好きだった物
のし紙の表書き
- 「御供」「御供物」
- 水引は黒白または双銀の結び切り
💡宅配で送る場合は、簡単なメッセージカードを添えると丁寧です。
6. 遺族へのお礼や気遣いも忘れずに
葬儀の喪主や遺族は、多くの準備や精神的負担を抱えています。
参列者としてできることは、一言の気遣いやちょっとしたお手伝いです。
- 電話やメールで「落ち着きましたか?」と声をかける
- 落ち着いた頃に弔問に伺う(長居は避ける)
- 役所の手続きや法要準備で手が必要なときはサポートを申し出る

7. 自分自身の気持ちも整える
故人との別れは、自分自身にも大きな感情の波をもたらします。
葬儀後は、静かな時間を持ち、自分の心も労わってください。
- 好きな音楽を聴く
- ゆっくりお茶を飲む
- 誰かに話を聞いてもらう
💡無理に元気を出そうとせず、自分のペースで日常に戻ることが大切です。
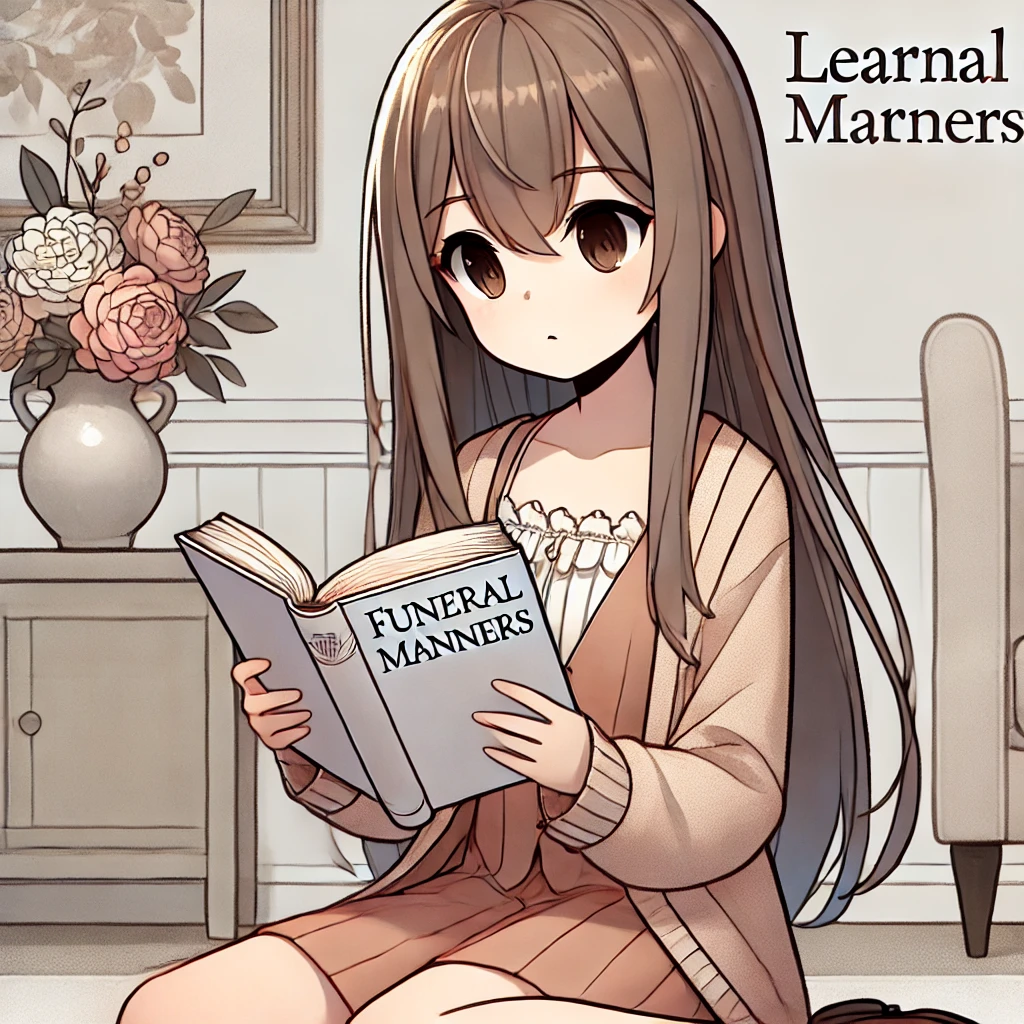
まとめ|葬儀後の流れを把握して心と環境を整える
お葬式の後にやるべきことをまとめると、以下のような流れになります。
- 【玄関先で】塩で体を清める(地域の風習による)
- 【帰宅後すぐ】手洗い・うがいで衛生ケア
- 【翌日までに】喪服・小物の整理・クリーニング
- 【落ち着いたら】香典返しや供物の整理・記録
- 【次の法要に備え】お供えの準備・マナー確認
- 【ご縁があれば】遺族へのお礼やサポートの連絡
- 【そして】自分の気持ちを労わる時間を持つ
葬儀は終わっても、故人を偲ぶ気持ちは続いていきます。
少しずつ日常を取り戻しながら、心穏やかに故人を思う時間を大切にしていきましょう。
オススメ記事
1、【驚愕】通常は知られないエグい葬儀トラブルとクレーム事例10選【誤らないための小ネタ】



