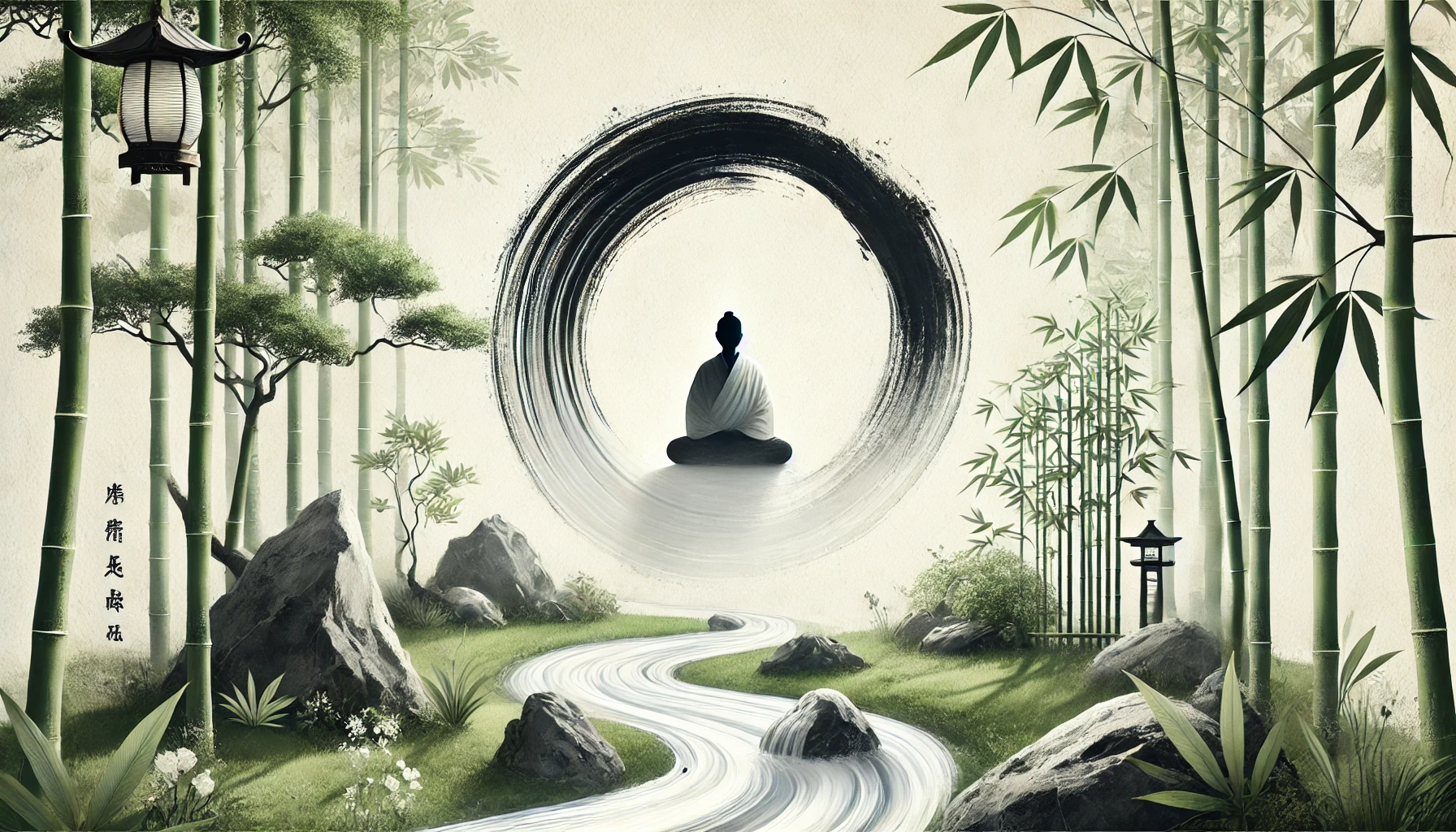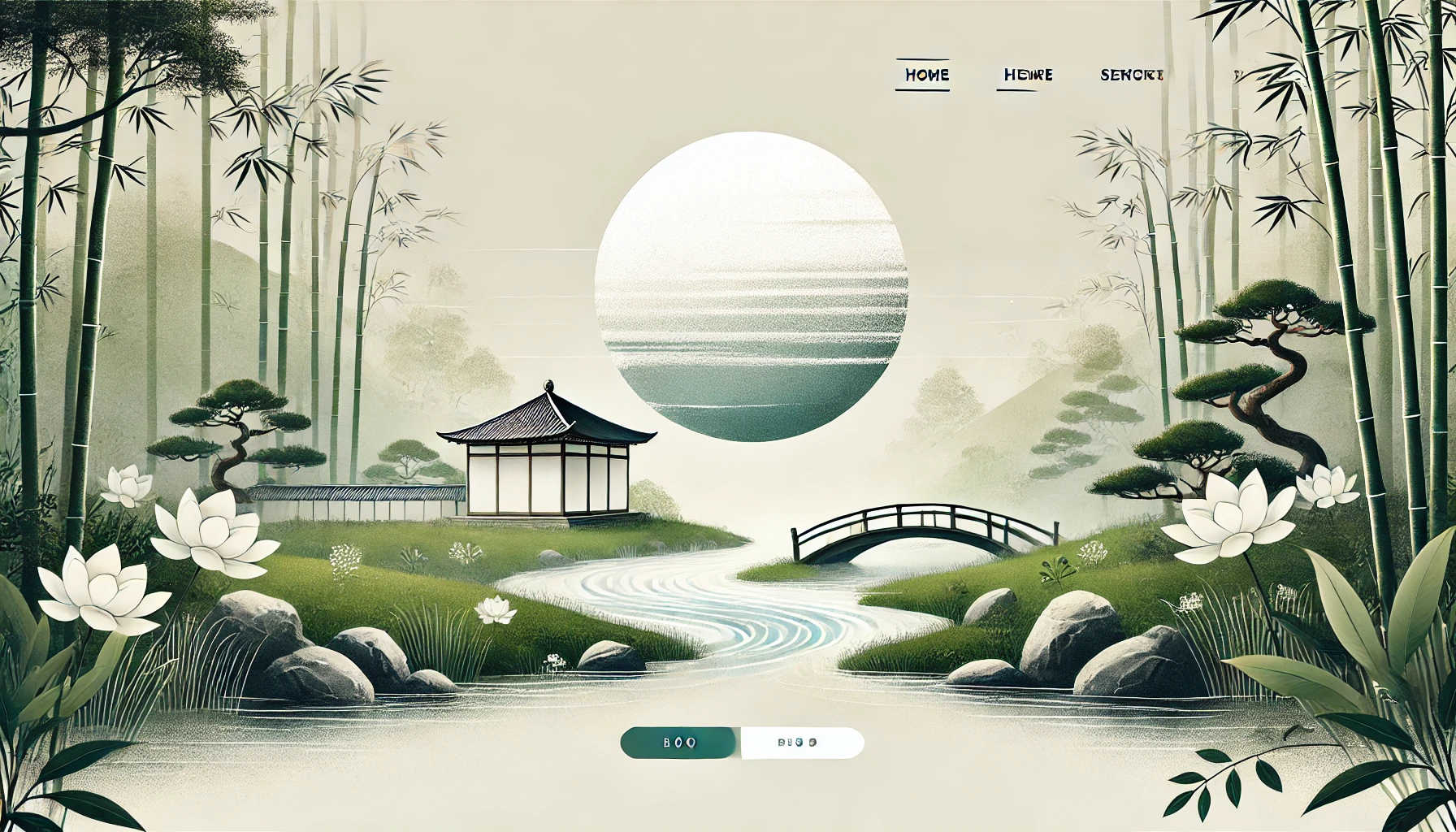
はじめに
現代はスマホや情報に囲まれ、常に心が落ち着かない時代です。
そんな中で、曹洞宗の「坐禅(ざぜん)」は、静けさを取り戻すための大切な教えとして注目されています。
この記事では、曹洞宗の教えをわかりやすく解説し、
日常生活での実践法、そして葬儀に出る際に心を整えるためのポイントを紹介します。

曹洞宗とは?
「只管打坐(しかんたざ)」— ただひたすら坐る
曹洞宗は、鎌倉時代に道元禅師によって伝えられた禅宗の一派です。
その根本教えは「只管打坐(しかんたざ)」、つまり「ただひたすら坐る」こと。
坐禅とは、雑念を消すための修行ではなく、姿勢・呼吸・心を整える時間。
何かを「得よう」とするのではなく、「今この瞬間を生きる」ことを大切にします。
創価学会・顕正会・統一教会…有名宗教団体のお布施・年間支出はいくら?
日常生活に活かす「坐禅の心」
曹洞宗の坐禅は、特別な修行ではなく、日常そのものが修行という考え方が根底にあります。
以下の3つのポイントを意識することで、生活の中に「禅の心」を取り入れることができます。
① 姿勢を整える
坐禅の第一歩は、正しい姿勢です。
背筋をまっすぐにし、顎を軽く引いて、体の中心を意識します。
椅子坐でも構いません。「身体を整える」ことで心も自然と落ち着きます。
② 呼吸を整える
曹洞宗では「調息(ちょうそく)」と呼ばれる呼吸法を大切にします。
一度深く息を吐き出し、ゆっくりと自然な呼吸に戻していきます。
呼吸が整うと、心の波も穏やかになります。
③ 所作を丁寧にする
掃除・挨拶・食事など、日常のすべてが「修行の場」。
例えば、靴をそろえる、箸を静かに置く、物を大切に扱う。
そのひとつひとつの所作に、坐禅の心が生きています。
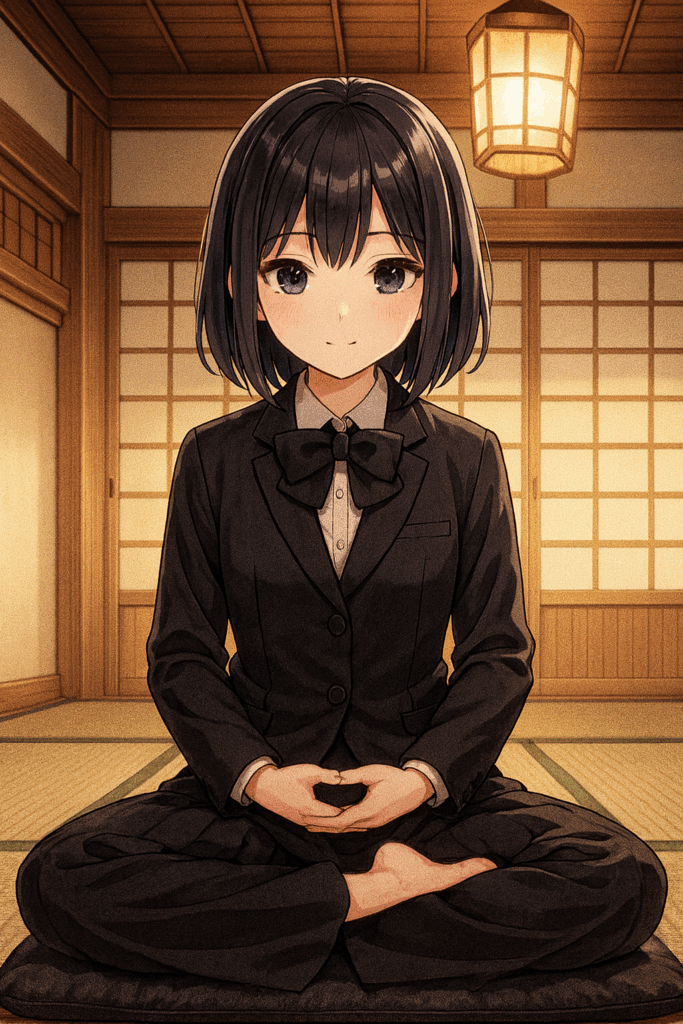
坐禅を続けることで得られる効果
坐禅を日々の中に取り入れることで、次のような変化が生まれます。
- 心が落ち着き、イライラや焦りが減る
- 集中力が高まり、仕事や家事に余裕が生まれる
- 「いま」を意識できるようになり、感謝の気持ちが増える
曹洞宗の教えは、現代人の「心のストレス」をやわらげるヒントでもあります。
🪯創価学会 vs 日蓮正宗──破門から始まった“水と油”の関係とは?
葬儀に出る際の心得
坐禅の「心を整える」という教えは、葬儀の場でも生かせます。
ここでは、曹洞宗の考え方を踏まえた葬式マナーと心構えを紹介します。
① 服装・身だしなみを整える
葬儀は「故人と向き合う時間」。
黒・紺・グレーなど落ち着いた色を選び、清潔感を大切にしましょう。
服装を整えることは、坐禅でいう「姿勢を正す」ことと同じです。
② 心の準備をする
式場に入る前に、深呼吸をして心を落ち着けましょう。
雑念を手放し、静かに故人への感謝を思い返すことで、
葬儀の時間がより意味のあるものになります。
③ 所作を丁寧にする
お焼香・合掌・一礼——。
一つひとつの動作をゆっくり、丁寧に行うことが何よりの供養です。
慌てず、静かな心で手を合わせましょう。
④ 言葉と態度に気を配る
式の場では、周囲の人や遺族への配慮が大切です。
余計な会話や軽率な言葉を避け、沈黙の中で故人を偲ぶ時間を共有しましょう。
⑤ 終わった後も「整える」
葬儀が終わった後は、すぐに日常へ戻らず、
静かに心を整える時間を取りましょう。
坐禅のように、自分の中の感情を一度受け止めてから動き出すことで、
「心の整理」が自然と進みます。
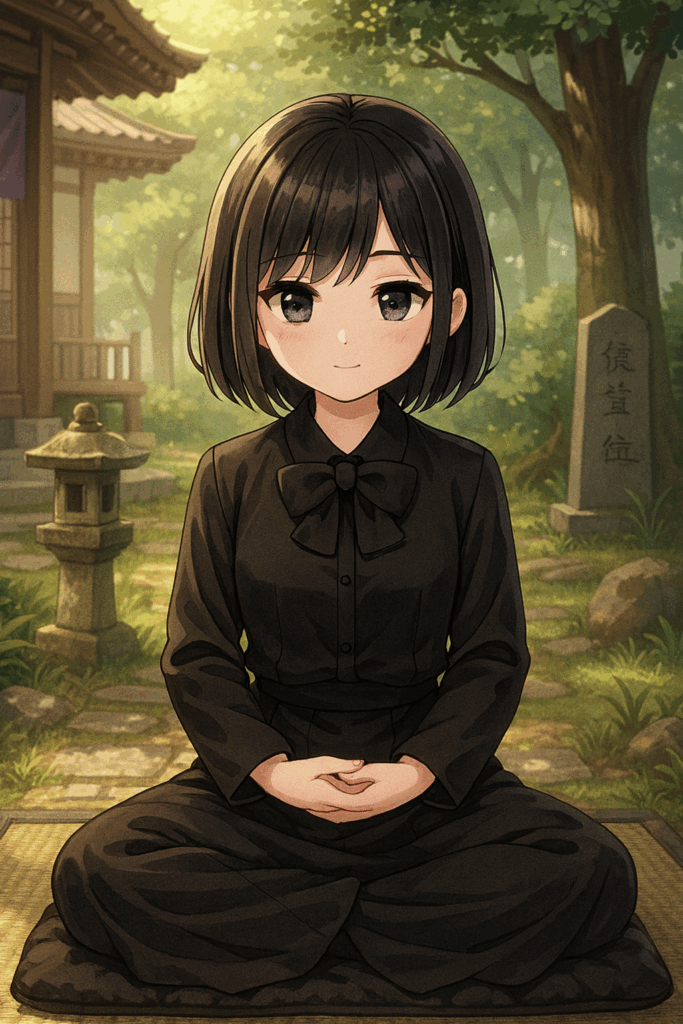
まとめ
曹洞宗の「坐禅」は、難しい修行ではなく、
心を整え、日常を丁寧に生きるための知恵です。
そして、その精神は葬儀の場にも通じます。
静かな姿勢、整った呼吸、丁寧な所作。
それらはすべて、「故人を敬う」ことの表れです。
慌ただしい現代だからこそ、
坐禅を通じて「いま」を見つめ、静かに心を調える時間を持ってみましょう。