葬儀や供養の際に必要になる「戒名(かいみょう)」。しかし、「戒名ってそもそも何?」「高いお金を払う必要があるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
今回は、戒名の意味や構成、費用相場、選び方、お布施を渡すタイミングについて詳しく解説します。
戒名の意味とは?

戒名とは、仏教の世界で与えられる「仏弟子としての名前」のことです。生前の俗名(戸籍名)とは異なり、亡くなった後、仏門に入ることを意味します。
戒名が必要とされる理由
- 仏の弟子として成仏するため
- 法要や供養で故人を呼ぶための名前
- 位牌や墓石に刻まれ、供養の対象となる
- 仏教の教えを尊重する家族が供養の一環として重視する
- 伝統的な葬儀の形式に沿うため
最近では、俗名での供養を希望する方も増えていますが、伝統的な仏教葬儀では戒名が一般的です。また、生前に戒名を授かる「生前戒名」を希望する人もおり、終活の一環として関心を持つ人が増えています。
戒名の構成とランク
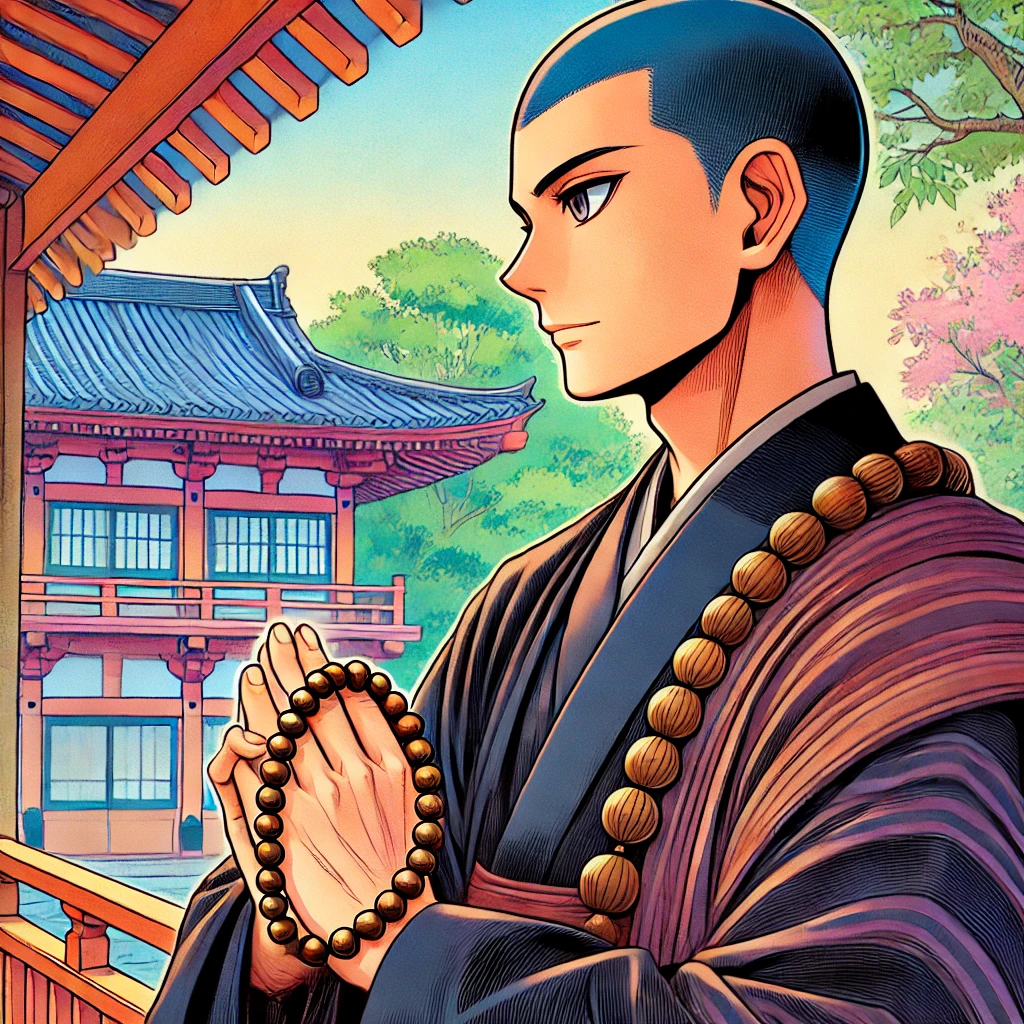
戒名は一般的に以下のような構成になっています。
| 構成要素 | 説明 |
|---|---|
| 院号(いんごう) | 特に格式の高い戒名につく。「○○院」など。 |
| 道号(どうごう) | 仏教的な意味を持つ称号。修行や徳を表すことが多い。 |
| 法号(ほうごう) | 最も中心となる部分。故人の人柄や生前の功績が反映されることが多い。 |
| 位号(いごう) | 故人の性別や年齢に応じた称号。「信士」「信女」など。 |
ランク別の戒名
| 戒名のランク | 意味・特徴 | 相場(円) |
| 信士・信女(しんし・しんにょ) | 一般的な戒名。多くの方が選ぶ。 | 10万~30万円 |
| 居士・大姉(こじ・だいし) | 格式が高め。信仰心の厚い方や高齢者向け。 | 30万~50万円 |
| 院号付き(院信士・院信女) | 「○○院」の称号がつく格式の高い戒名。 | 50万~100万円 |
| 院号+居士・大姉 | 最高位の戒名。社会的に功績があった方など。 | 100万~300万円 |
戒名のランクは、故人の社会的な立場や生前の活動に応じて決められることが多く、特に高位の戒名は寺院への多額の寄付を伴う場合があります。
戒名の費用相場と決まり方

戒名の費用は「お布施」の形でお寺に渡します。
費用が決まる要素
- 宗派やお寺の考え方
- お寺によって相場が異なる。都市部の方が高め。
- 戒名のランク
- 位が上がるほど高額になる傾向。
- 菩提寺の檀家かどうか
- 檀家なら費用が抑えられる場合も。
- 生前戒名の有無
- 生前に戒名を受けると、比較的安価になることが多い。
- 特別な意味を持つ戒名の依頼
- 故人の功績を称えるような特別な戒名は、追加の費用がかかることがある。
戒名をつける際の注意点

① 事前に確認することが大切
- 「いくら包めばいいか」をお寺に確認しましょう。
- 「お気持ちで」と言われる場合もありますが、相場を知っておくと安心です。
- 生前に相談しておくと、より納得のいく戒名を選びやすくなります。
② 高額な戒名を選ぶ必要はない
- 「格式の高い戒名=良い戒名」ではありません。
- 家族の意向や経済状況を考慮して決めましょう。
- 高額な戒名を授かることで後悔しないよう、慎重に検討することが大切です。
③ 俗名での供養も可能
- 最近では戒名をつけず、俗名で供養する人も増えています。
- 家族が無理に高額な戒名を選ばないようにしましょう。
- 寺院によっては俗名で供養するための対応をしている場合もあります。
お布施をお渡しするタイミング

お布施は、戒名を授かる際や葬儀・法要の際に僧侶へお渡しします。一般的には以下のタイミングで渡されることが多いです。
1. 戒名を授かるとき
- 生前戒名の場合:戒名を授かったときにお布施をお渡しします。
- 葬儀前に戒名を授かる場合:葬儀の準備段階で、お寺で戒名をつけてもらった際に渡すことが一般的です。
2. 葬儀の際
- 通夜や告別式で僧侶に読経を依頼したとき
- 読経が終わった後、もしくは葬儀が終わったタイミングでお渡しします。
- 僧侶によっては、最初に渡すことを希望する場合もあるので事前に確認しましょう。
3. 初七日や四十九日法要の際
- 法要ごとにお布施をお渡しするのが一般的
- 初七日、四十九日、百か日、一周忌、三回忌などの法要ごとに、僧侶の読経や供養をお願いした際にお渡しします。
4. お盆やお彼岸の供養の際
- 僧侶を招いてお盆やお彼岸の供養をする場合にもお布施を渡す
- 特にお盆の「棚経(たなぎょう)」の際は、読経後にお布施を渡します。
5. 年忌法要の際
- 三回忌、七回忌、十三回忌などの年忌法要の際にも渡す
- 法要の最後に、感謝の気持ちを込めて渡します。
まとめ:戒名は納得して選ぼう

戒名は、仏教の伝統に則った供養の一部ですが、必ずしも高額なものを選ぶ
必要はありません。費用相場を理解し、事前にお寺と相談しながら、納得のいく形で決めることが大切です。
また、家族の意向や故人の意思を尊重することも重要です。生前に戒名を決めておくことで、葬儀の際の負担を減らすことができるため、終活の一環として考えてみるのも良いでしょう。
**「本当に必要か?」「どのランクが適切か?」**を家族で話し合い、後悔しない選択をしましょう。
オススメ記事



