
はじめに法事は「やらなければいけない」と分かっていても、実際に何をどう進めればいいのか、一般の人にはとても分かりづらいものです。
葬儀の現場では、毎回「順番がわからない」「費用はどこにいくら払うの?」
という質問が本当に多くあります。
この記事では、初めて法事を主催する人でも迷わないように
・流れ
・準備
・費用
・よくある失敗
・節約のコツ
をまとめて“必要なところだけ”読みやすく解説します。
1. 法事の基本|「法要」と「法事」の違い
まず押さえておきたいのは、この2つの言葉の違いです。
- 法要…読経や焼香など、僧侶による供養の儀式
- 法事…法要+会食+お墓参りなど、一連の行事全体のこと
つまり、広く言えば**「法事の中に法要がある」**というイメージです。
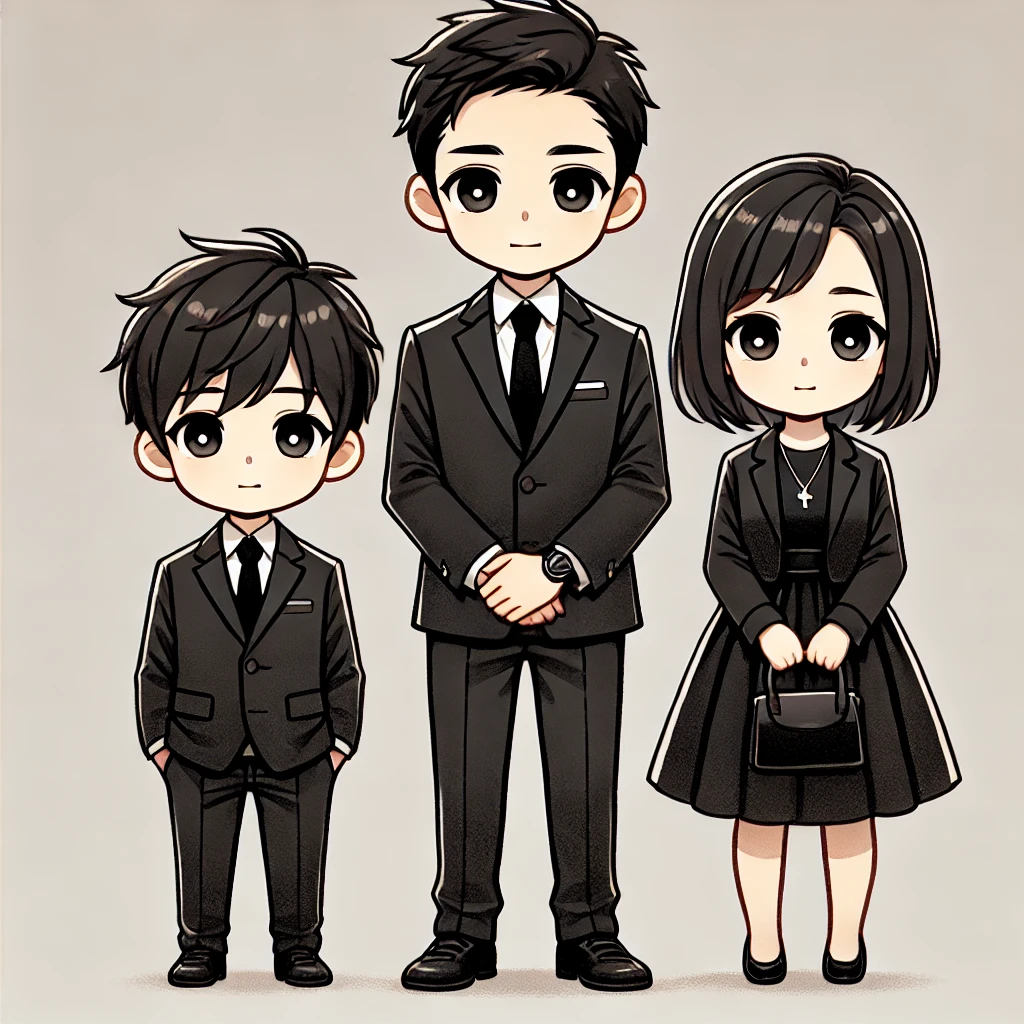
2. 法事の全体の流れ(一般的な一例)
ここだけ見れば、当日のイメージが完全に掴めます。
- 日程の調整(親族 × 住職)
- 会場の手配(寺院・自宅・会館)
- 料理の手配(仕出し・会食)
- 当日の受付・案内
- 読経・焼香(法要)
- 会食(精進落とし/お斎)
- 墓参り(納骨やお参り)
- 解散・お礼の連絡
実際は1〜2時間程度で完結します。
最近は会食なしのスタイルも増えています。

3. 法事の準備|いつから動けばいい?
● ベストは「1〜2か月前」
- 親族の予定調整
- お寺(住職)の予定確認
- 会場や料理の予約
をスムーズに行うには、このタイミングが理想です。
● 住職の予定は最優先
先に場所を決めてから住職に連絡すると「その日は空いていません」が多発します。
真っ先に住職の予定を押さえるのが最も重要です。
4. 法事にかかる費用の目安
一般的にかかる費用はこの3つ。
① お布施
→ 3万〜5万円前後
地域や宗派で変動がありますが、最も多い相場です。
② 会食(仕出し・精進料理)
→ 1人 4,000〜8,000円
③ 会場使用料
→ 自宅ならゼロ
→ 会館は 1万〜5万円ほど
合計:5万〜15万円前後が標準的です。
5. プロ目線:法事で多い「よくある失敗」
現場で本当に多いトラブルだけ絞って紹介します。
✔ 住職の予定が合わない
→ 一番多い失敗。必ず最優先で確認。
✔ 会食を人数より多く頼みすぎる
→ キャンセル不可の料理が多く、無駄な出費に。
✔ 会場が狭くて座れない
→ 観音開きの和室は特に注意。
✔ 案内状を出すのが遅れる
→ 遠方の人に迷惑がかかるので早めが理想
6. ここがポイント|法事費用を賢く節約する方法
節約と言っても“ケチる”のではなく、
無駄を減らして丁寧に供養するための方法です。
① 会食なしの法事も増えている
- 読経 → 墓参りだけで完結
- コロナ以降、一般的になった
② 自宅法要という選択肢
会場費ゼロ、移動もなし。
僧侶の出張は普通に対応してくれます。
③ 飾り(供花・供物)は必要最低限でOK
見栄えで追加を頼む必要はありません。
お寺側も気にしません。
④ 家族だけでやると総額が半分程度に
親族を呼ばなければ、料理・席・引き出物などが不要に。

7. 現場だから知っている「気持ちの準備」
法事が近づくと、
- 気持ちが沈む
- 思い出してつらくなる
- 準備の負担で疲れる
という方が本当に多いです。
でも、覚えておいてほしいのは
「完璧じゃなくていい」ということ。
供養は “形” ではなく、
故人を思う “気持ち” が何より大切です。
無理せず、気軽に相談しながら準備を進めてください。
8. まとめ|法事は「流れを知る」だけで不安が消える
今日お伝えした内容を押さえておけば、
初めての法事でも迷わず進められるはずです。
- 流れを知る
- 住職の予定を最優先
- 無理のない形式を選ぶ
- 節約は“簡略化”で十分
この4つを押さえるだけで、
あなたの負担はぐっと軽くなります。



