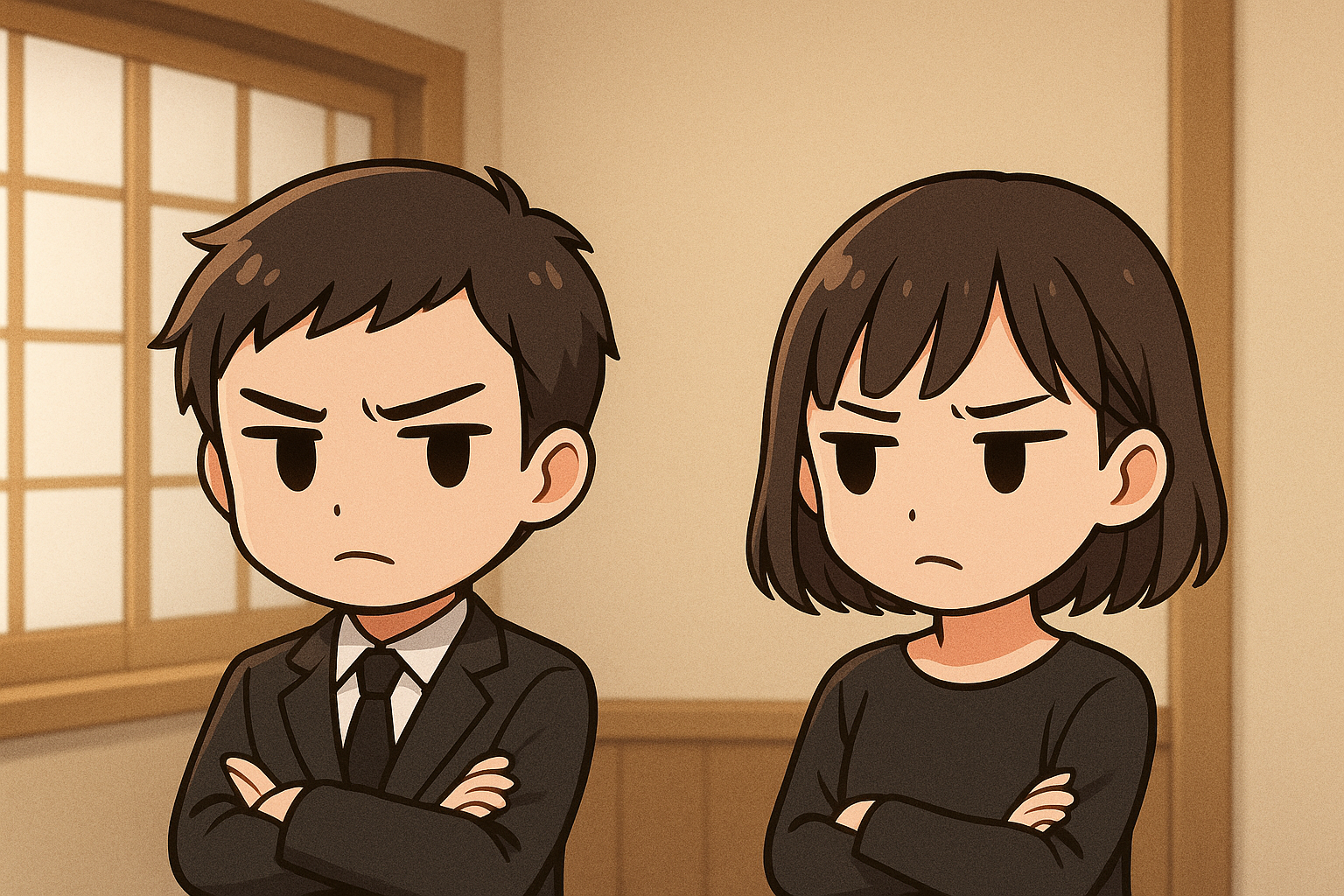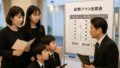神道の葬儀ってどうするの?初めて出席する人のための基礎知識と三大教団の信仰とは!?
葬儀の場で、親族同士がピリついている…そんな光景を見たことはありませんか? その裏には、遺産相続をめぐるトラブルが隠れていることもあります。
この記事では、よくある相続のもめ事と、トラブルを防ぐための備えを、葬儀現場の視点で解説します。
第1章:なぜ遺産相続は揉めるのか?
家族同士の間であっても、相続となると一気に関係が崩れることがあります。 特に、以下のようなパターンが原因になることが多いです:
- 遺言書が存在しない、または内容が不明確
- 不公平に見える分配(例:長男だけが多いなど)
- 介護してきた人 vs 何もしていなかった人の不満
- 再婚家庭でのトラブル(先妻の子と現妻の子)
- 相続人の一部が音信不通・行方不明
相続は金額だけでなく、過去の感情の積み重ねが爆発する引き金になることも。
第2章:葬儀の現場で起こる“相続トラブルの影”
葬儀という場は、相続の火種が表面化しやすいタイミングでもあります。
- 火葬中、遺族同士が会話せずにギスギス
- 喪主が財産や遺言について触れた途端、他の家族が不信感を抱く
- 葬儀費用を誰が負担するかで口論に
- 遺品や仏壇の処理をめぐって揉める
本来、故人を偲ぶべき葬儀が、遺産の取り合いの場になってしまうのは悲しいことです。

第3章:相続で揉めないためにできる3つの準備
1. 生前の「見える化」:エンディングノート・遺言書の作成
相続でもっとも揉めやすいのは、「何も決まっていない状態」。そのため、生前から財産や意向を明確にしておくことが非常に大切です。
エンディングノートは法的効力こそありませんが、自分の希望や想い、家族へのメッセージを伝えることができるツールです。手書きで構いません。「自宅は長男に、預金は平等に」など、具体的な意思が残っていれば、遺された家族が迷わずに済みます。
一方、正式な遺言書(公正証書遺言や自筆証書遺言)であれば法的効力があるため、さらに安心です。書き方や保管方法も確認し、無効にならないよう注意しましょう。
2. 専門家への相談:税理士・司法書士・行政書士
相続には法律・税金・登記など、複雑な問題が絡みます。素人判断では思わぬ落とし穴があるため、専門家のサポートは非常に有効です。
たとえば、税理士に相談すれば、相続税の控除や節税方法を事前に検討できます。不動産がある場合は司法書士が名義変更を行い、行政書士は遺言書作成のアドバイスをしてくれます。
どの専門家にどこまで依頼するかも含めて、事前に相続に強いプロを見つけておくことが「争族」を防ぐ第一歩になります。
【天理教の今と昔】国内外の現状・歴史・広がり・信仰の特徴まで徹底解説!!
3. 家族での話し合いの機会を持つ
もっとも効果的で、もっとも難しいのが「話し合い」です。日本では特に、“相続の話=縁起でもない”という風潮がありますが、それが逆にトラブルの原因になります。
まずは軽い雑談でも構いません。「うちはどうしようか」「誰が仏壇を守るか」などから始め、徐々に財産の話題に踏み込んでいくとよいでしょう。
重要なのは、家族それぞれの思いを尊重しながら、早い段階で方向性を共有することです。「あのとき言っておけばよかった」と後悔しないために、今、声をかける勇気が必要です。
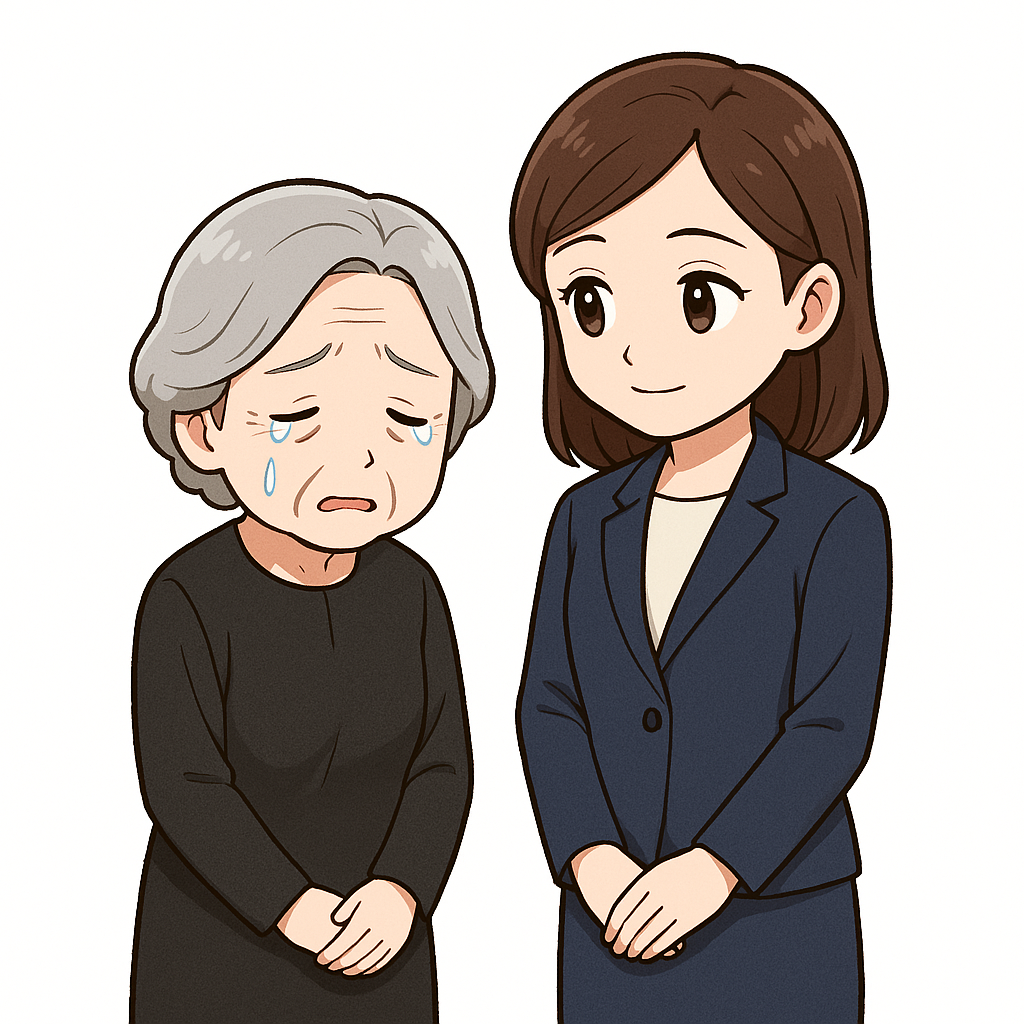
第4章:もしも揉めてしまったら?冷静な対処法
相続で揉めてしまった場合、感情に流されず、冷静に対応することが重要です。トラブルが表面化したときこそ、次のような対応が有効です。
- 第三者を挟む(弁護士や信頼できる親族) → 当事者同士では話し合いが感情的になりがちです。信頼できる親族や、相続に詳しい弁護士を介すことで、冷静かつ客観的に問題を整理することができます。
- 家庭裁判所での「遺産分割調停」も選択肢 → 協議での解決が難しい場合は、家庭裁判所の調停という手段があります。第三者である調停委員が中立の立場から助言してくれるため、話し合いが前進しやすくなります。
- 無断で遺産を引き出す、暴言を吐くなどはNG → 一時的な感情に任せた行動は、後々法的トラブルにも発展しかねません。たとえば、銀行預金を勝手に引き出す行為は「遺産の使い込み」と見なされ、他の相続人の信頼を完全に失う原因となります。
また、感情的な言動は、関係修復の機会を完全に断ってしまいます。特に親族同士の場合、相続が終わったあとも法事や介護などで再会する機会はあるもの。できる限り関係を壊さないためにも、早い段階で専門家の力を借りて、冷静な解決を目指すべきです。
感情的になると、かえって遺産分割協議が長引き、結果的に全員が損をします。後悔しないためにも、「冷静さ」と「段取り」が最大の武器になります。
宗教勧誘が気になる人へ|関東で“宗教活動が盛んな地域”とは?引っ越し前に知っておきたい4エリア
おわりに|“争族”にならないために、今こそ準備を
相続は「お金の問題」ではなく、「家族関係の問題」です。 元気なうちに整理しておけば、残された人たちが穏やかに故人を見送れます。 「まだ早い」と思わずに、今できる一歩から始めてみませんか?