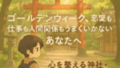「うちは財産そんなにないし、相続税なんて関係ないよ」と思っていませんか?

相続税とは?どんな税金?
相続税とは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続・遺贈により取得した人にかかる税金です。
所得税のように毎年かかるものではなく、「一度限りの税金」。
財産を「受け取った人」に課される**“取得課税方式”**なのが特徴です。
また、「相続人」以外にも遺言で財産をもらった人(受遺者)や、生前贈与を受けた人にも、特例条件のもとで課税されることがあります。
相続税の対象となる財産とは?
相続税がかかる財産は、大きく分けて以下の通りです。
■ 課税対象となる財産(プラスの財産)
- 現金・預貯金
- 土地・建物
- 株式・投資信託などの有価証券
- 生命保険金(受取人が相続人の場合)
- 自動車・貴金属・骨董品・ゴルフ会員権など
これらは時価や路線価などで評価され、相続財産の総額に含まれます。
■ 非課税となる財産(代表例)
- 墓地・仏壇・仏具・祭具
- 生命保険金のうち、500万円 × 法定相続人の数まで
- 死亡退職金のうち、500万円 × 法定相続人の数まで
- 公共団体や国への寄付財産(条件あり)
たとえば相続人が3人いれば、生命保険金や退職金はそれぞれ1,500万円まで非課税となります。
相続税のかかる・かからないの分かれ目は「基礎控除」
「うちは相続税なんて関係ない」と思っていても、基礎控除額を超えると課税対象になります。
■ 基礎控除の計算式
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例えば、相続人が配偶者+子2人の合計3人であれば、
3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
つまり、遺産総額が4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。
しかし、東京都内の一戸建て(土地付き)などの場合、それだけで5,000万円を超える評価となることも珍しくありません。
具体例:課税されるかどうか?
次のようなケースを考えてみましょう。
- 自宅(土地・建物):評価額 4,500万円
- 預金:1,000万円
- 生命保険金:1,500万円(受取人は相続人)
- 相続人:配偶者と子1人
【合計】4,500万円 + 1,000万円 + 1,500万円 = 7,000万円
ここから非課税分を引きます。
- 生命保険の非課税枠:500万円 × 2人 = 1,000万円
【課税対象額】7,000万円 − 1,000万円 = 6,000万円
基礎控除額は、3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円
➡ 差し引き1,800万円が課税遺産総額となります。
このように、「自宅と少しの現金しかない」という方でも、土地評価が高いと課税対象になってしまうことがあるのです。

「相続税はお金持ちだけ」ではない理由
かつては、相続税は“富裕層だけに関係ある税金”と言われていました。
しかし、2015年の税制改正により基礎控除額が引き下げられたため、現在では相続税が発生する家庭は全国で約8〜9%前後と言われています。
また都心部ではその割合が15%を超える自治体もあり、「一般家庭でも相続税に直面する」時代になったと言えるでしょう。
注意点:相続税が発生するのに「現金が足りない」ケースも…
課税遺産の中に不動産の割合が大きい場合、いざ相続税が発生しても、現金が足りず納税できないという事態が起こります。
こうしたときのために「延納」や「物納」という制度もありますが、条件が厳しいため、事前の準備や対策が必要不可欠です。
第2部では「相続税の計算・申告・納税の流れ」を徹底解説!
- 相続税の具体的な計算方法
- 法定相続分と税率の関係
- 申告から納税までの流れ
- 知らないと損する「特例や控除」
などを、具体例つきで紹介します。
ちなみに、チェックリスト。。
✅ 持ち家がある(都心または住宅地にある)
✅ 親が定期預金・株などを保有している
✅ 生命保険金を受け取る予定がある
✅ 退職金の支給がある
✅ 親名義の土地があり、相続人は複数いる
✅ 相続財産の評価をしたことがない
✅ 「相続税は関係ない」と思っていた
💬 1つでも当てはまったら、第2部も必見です!