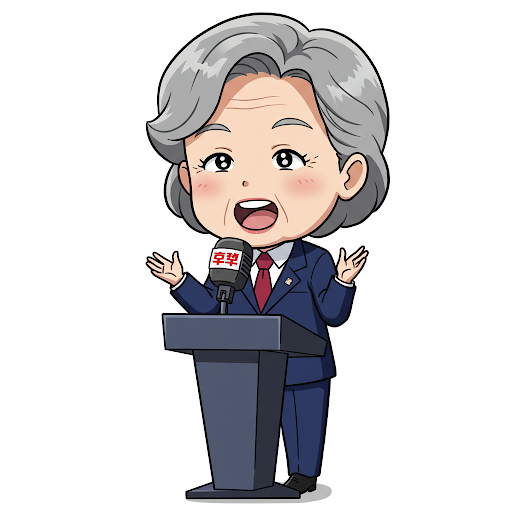日本国内の新興宗教の中でも、顕正会と創価学会の関係は際立った存在感を放っています。両者とも日蓮の教えを基盤としながら、互いを激しく批判し合う姿勢を長年にわたって続けているためです。そこで本稿では、この両団体の対立がいかにして芽生え、何が決定的な引き金となったのかを時系列で解説していきます。

■ 創価学会の急成長と内部での違和感
1930年に創立された創価学会は、戦後の混乱期を乗り越えながら急速に勢力を伸ばし、やがて日本を代表する新興宗教団体として大きな地位を築きました。特に、池田大作氏が表舞台に登場してからは、組織運営や政治活動にも積極的に関わり、社会的影響力を飛躍的に高めていきます。
しかし、その拡大路線に対しては、学会内外から「肥大化しすぎているのではないか」「日蓮の教えの本質に忠実なのか」といった声も少しずつ上がるようになりました。こうした疑問をいち早く提起したのが、のちに顕正会を率いることになる浅井昭衛氏だったのです。浅井氏は当初から学会内部で活動していたため、組織の変貌を間近で見てきた立場でもあり、こうした疑念は徐々に大きく膨らんでいきました。
特に、池田大作氏が推し進める政治活動や社会的進出のあり方について、学会の信仰路線が世俗的な方向へと走り過ぎていると感じる会員も少なくなかったのです。目覚ましい発展の裏には、スピード重視の組織拡大や政治への積極介入が見受けられ、これらが「日蓮大聖人の真髄とは距離があるのでは」という指摘が生まれ始めていました。

■ 浅井昭衛と「妙信講」の設立
当初、浅井昭衛氏は創価学会の熱心な信徒でしたが、池田大作氏の政治色の強い活動や組織拡張のあり方を「本来の日蓮仏法から逸脱している」と見なし、独自の活動を開始します。1960年代後半に入り、彼は「妙信講(みょうしんこう)」という講を立ち上げ、創価学会への批判的立場を鮮明にするようになりました。
妙信講は表向きは日蓮正宗の一信徒集団という位置づけでしたが、実質的には創価学会の運営を非難する独自路線を進んでおり、その存在は学会側にとって大きな懸念材料となっていきます。なぜなら、同じ日蓮正宗系統の中で反旗を翻す形が取られれば、それは学会の正当性に対する直接的な挑戦と捉えられるからです。
加えて、妙信講側も「創価学会が正しい信仰から外れてしまった」と感じていたため、さらに強硬な批判を繰り広げるようになりました。浅井昭衛氏自身の主張は一貫して「日蓮大聖人の教えに根ざした信仰を取り戻す」というものであり、その矛先は徐々に学会の指導者層へと向かっていったのです。

■ 破門による決裂──顕正会の誕生
1974年、日蓮正宗は浅井昭衛氏と妙信講を「反乱的行為」と見なして破門に踏み切りました。これを機に妙信講は宗派から独立し、新たに「顕正会」と名乗るようになります。「自分たちこそ真の正法を継承する」という強い主張を掲げ、これまで以上に創価学会への対立姿勢を示していくのです。
この破門措置を境に、浅井氏の言動はますます激化し、創価学会だけでなく、日蓮正宗の上層部にも矛先を向けるようになります。その背景には、妙信講を破門へと追い込んだのは創価学会と日蓮正宗が結託した結果だという不信感がありました。結果として、顕正会側は「自分たちこそが日蓮大聖人の教えを護持する唯一の団体」であるとの強い確信を深めていくことになります。
一方、創価学会は引き続き日蓮正宗との関係を保持していましたが、1991年になると逆に創価学会も日蓮正宗から破門される事態に陥ります。こうして顕正会と創価学会は、同じく“日蓮正宗から破門された”という皮肉な共通点を有することとなりました。とはいえ、両者が共感し合うわけではなく、むしろお互いに「正統性を逸脱した」と非難し合うことで対立は一層先鋭化していきます。

■ 対立の根底にある要因
顕正会は、今もなお創価学会を「曲解された仏法を広める団体」として糾弾し、一方の創価学会は顕正会を「過激な宗教団体」として警戒しています。両者とも街頭やSNSを通じて活発な布教と相互批判を行っており、そのやり取りはしばしば感情的なものに発展します。
こうした衝突の背後には、どちらの団体も強い排他性を帯びている点が挙げられます。少しでも異なる教義解釈や活動方針を「正しくない」と否定する態度が、双方の歩み寄りを困難にしているのです。さらに「自分たちこそが日蓮大聖人の本義を守っている」という強固な確信が衝突を先鋭化させる要因でもあります。
特に顕正会は、国立戒壇の建立を強く訴えるなど、“本来の日蓮仏法”に立脚した国家的変革を目指す姿勢を持っています。これに対し、創価学会は世界平和や個人の幸福を中心とした布教活動を進めてきており、それぞれの最終目的や手法の違いも相まって互いの正当性を認めることが難しい構図となっています。道筋が重なる部分が少ないからこそ、相手の主張を真っ向から否定することがしばしば起きるのです。

■ トラブル回避のための心得
実際、顕正会と創価学会の信者同士が街頭で口論に及んだり、互いの会合を邪魔しようとしたりといったトラブルが報告されています。警察が出動するケースもあり、物理的対立に発展するリスクも否定できません。
こうした状況を踏まえると、両者の活動現場では安易に批判をぶつけ合わない姿勢が大切です。宗教や信仰の問題は、単なる価値観の相違を超え、当人たちにとっては重大な意味を持つもの。安易な接触や議論は対立を深める結果を招きかねません。興味を持つことは大事ですが、関わり方には十分な注意が必要です。
また、双方ともに組織的な勧誘や広報活動を行っているため、第三者が巻き込まれるケースも考えられます。大学構内や駅前など、人の集まる場所での折伏(勧誘)活動は比較的活発で、そこで互いを否定するようなビラや説法を展開することもあるからです。万一トラブルに巻き込まれそうになったら、冷静に状況を離れるのが望ましいでしょう。

■ まとめ
顕正会と創価学会は、ともに日蓮系の教えを基盤としながら、互いを全く相容れない存在と見なすところに特徴があります。分裂の引き金となった浅井昭衛氏の批判と破門処分は、両者が完全に別の道を歩む大きなきっかけでした。
その後、創価学会も日蓮正宗から破門されて独自路線を進み、顕正会との対立はますます深まっていきます。「自分こそが正統」という強い信念や排他性が根底にあるため、近い将来に両者が和解する兆しは見えません。
こうした現状を踏まえ、両者の内情を見極めるときは、互いの歴史的背景や教義解釈の相違点を整理しながら、無用なトラブルを避けるよう心がけることが大切だと言えるでしょう。
◎オススメ記事
2、顕正会とは?道端での勧誘に注意。教義や被害例から考える“宗教との距離感”