こんな葬式依頼者は嫌だ!葬儀社が困る5つのタイプ

こんにちは!”初めての喪主への道しるべ” です。
葬儀は故人をお見送りする最期のセレモニーであり、遺族にとっては悲しみや慌ただしさが入り混じった特別な時間です。とはいえ、普段から葬儀の段取りに慣れている人は決して多くはありません。そのため、どうしても「何をどう準備すればいいのかわからない」「予算の決め方がわからない」という状況に陥りがちです。
一方で、葬儀社の立場から見ると、「こういう依頼をされると準備が進まず困ってしまう」というケースも少なくありません。せっかくの故人とのお別れの場を、なるべくスムーズに、かつ遺族や参列者の方々が納得のいく形で執り行うためにも、葬儀社とのコミュニケーションはとても重要です。
今回は、実際に葬儀の現場で耳にすることの多い「こんな葬式依頼者は困る……」という5つのタイプについて、詳しくお話ししてみたいと思います。もし葬儀を考えている方がいらっしゃれば、「自分は当てはまらないだろうか?」と客観的にチェックしてみてくださいね。

1. こちらの提案を聞いていない
~提案するけど聞いていなく、話を聞いていると『結局何をしたいかわからない』~
葬儀には宗教や地域の慣習、会場の広さ、参列者の数など、多くの要素が絡み合います。葬儀社はそれらを総合的に判断し、依頼者の希望や予算に合ったプランを提案しようとします。しかし、提案をしても最初は「はい、わかりました」と受け止めてもらえるものの、後になって「やっぱりそれはちょっと……」「結局どうしたいのかわからないんだけど?」と意見が二転三転してしまうケースがあるのです。
このような場合、葬儀社としては準備を進めようにも「最終的にどうしたいのか」が定まらず、スケジュールが立てられなくなります。さらに、大枠を決めてから細部を詰めようとした際に再度「いや、やっぱり違う気がする」という声が上がると、式の段取り全体に影響が出てしまいます。
なぜ困るのか?
- プランを決めるまでに何度も打ち合わせが必要になるため、時間がかかる。
- 当日間近になってからの変更が増えると、式場やスタッフの手配に支障をきたす可能性がある。
対策・アドバイス
- まずは「どういう葬儀にしたいのか」を家族や親族で話し合って、最低限の希望や方向性を共有しておきましょう。
- わからないことがあれば、その都度葬儀社に相談するのが大事ですが、相談する内容をメモに取っておくとブレにくくなります。
- 心情的に迷うこともあるかもしれませんが、大きな方針が固まっているだけで、葬儀社はスムーズに準備を進められます。

2. 金額に難色を示すけど、グレードダウンには納得しない
~プランを安くしてほしいと言う割に、内容の変更には渋る~
葬儀にかかる費用は、数十万円から数百万円に及ぶ場合もあり、大きな出費となります。「もっと安く抑えたい」「予算が厳しい」という意見は当然あり得ますし、その気持ちはよくわかります。しかし、いざグレードを下げる提案をすると「そこまでは削りたくない」「やはりあれもこれも付けたいんだけど……」と要望が膨らんでしまうことも少なくありません。
この場合、葬儀社としては「コストを削るには、このオプションを外す必要があります」と明確に伝えたとしても、依頼者の側が納得してくれないと進めにくいものがあります。結果として、何度も見積もりを取り直す羽目になり、時間と労力がかさんでしまうのです。
なぜ困るのか?
- 予算と希望がかけ離れすぎていると、折り合いをつけるのが難しくなる。
- 下げられる部分を削っても、依頼者が納得しない場合、ギクシャクしたまま式に臨むことになる。
対策・アドバイス
- 「絶対に削れない要素」と「少し調整できる要素」を最初に分けておくと、プランの再構成がしやすくなります。
- 大切なのは、葬儀の本質を見失わないことです。華美な飾りや不要なオプションを追加しても、故人を偲ぶ気持ちに代わりはありません。優先順位をしっかり決めましょう。
- 予算をなるべく抑えるためには、複数の葬儀社の見積もりをとるのも一つの方法ですが、価格だけでなく内容や対応も比較し、納得できる業者を選ぶのが大切です。

3. 値切ってくる
~あの手この手で値引きを要求~
「他の葬儀社の方が安いって聞いたんですけど、もっと安くなりませんか?」「オプションをサービスしてくれませんか?」などと、値引きを強く求めてくるケースも実際にあります。もちろん、価格交渉そのものが悪いわけではありません。大きな買い物(サービスの利用)をする際に、少しでも条件を良くしたいというのは人情として理解できます。
しかし、葬儀は会場費や人件費、装飾品の手配など、多種多様なコストが絡むサービスでもあります。極端な値引き交渉をされると、葬儀社としては最低限の利益が確保できず、対応が難しくなるのです。無理に価格を下げることで、結果的にサービスの質が下がる可能性も否めません。
なぜ困るのか?
- 適正価格が保てないと、スタッフの人員や式の品質に影響が出る。
- 度重なる値引き要求で、信頼関係が損なわれる可能性がある。
対策・アドバイス
- 葬儀社が提示する見積もりの内訳を確認し、どの部分にどのくらいのコストがかかっているのかを理解しておきましょう。
- 値引き交渉をしたい場合は、「ここだけはもう少し抑えてほしい」という部分を具体的に伝え、相手の話をしっかり聞くことが大切です。
- 過度な値下げ交渉は、結果として自分たちの求めるサービスの質が低下し、後悔を招く可能性があります。
4. 料金を払わない
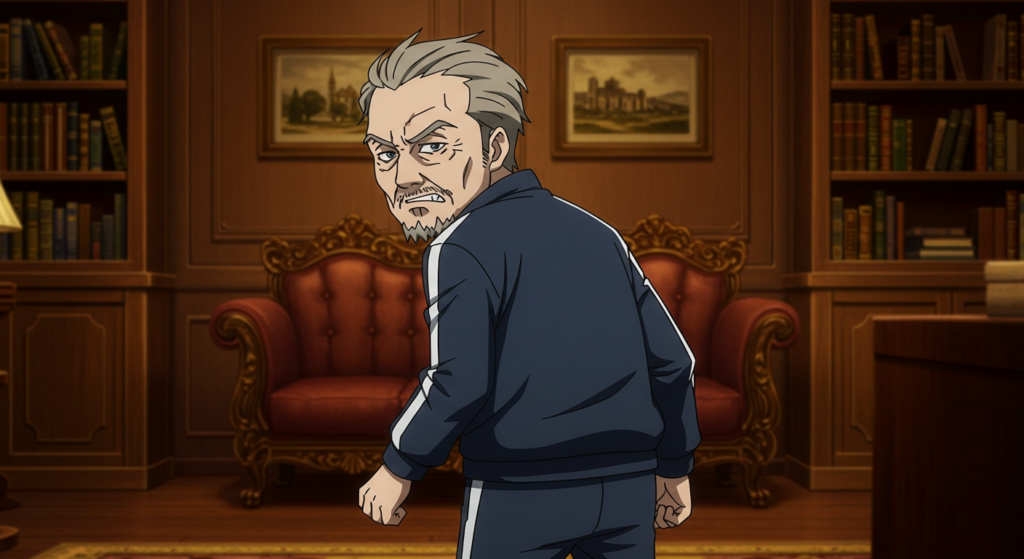
~葬儀が終わってから支払いを先延ばしにする~
葬儀が終わった後、正式に請求書を出すと「今すぐには用意できないので、少し待ってください」というパターンがたまに見受けられます。確かに急な出費ですし、保険金や香典の整理などで時間がかかることもあります。しかし、数週間、数カ月と先延ばしにされてしまうと、葬儀社としては立て替えた費用を回収できず経営を圧迫する要因となってしまうのです。
ほとんどの葬儀社は、遺族の方の気持ちに配慮し、強く催促することは避けています。しかし、だからこそ「少し待ってほしい」と言われ続けると、運営に支障が出てしまうケースも出てきます。これは葬儀社と依頼者双方にとって不幸な状況と言えるでしょう。
なぜ困るのか?
- 葬儀社は式場代や人件費、花などの手配に先行コストをかけているため、未払いが続くと経営難に陥る。
- 他の利用者へのサービスにも影響し、最終的には信用問題に発展する可能性がある。
対策・アドバイス
- 資金繰りが難しい場合、事前に相談するのがベストです。支払いを分割にしてもらうなど、柔軟に対応してくれる葬儀社もあります。
- 葬儀保険や互助会などを活用している場合は、その仕組みを理解し、支払い時期を明確にしておきましょう。
- 香典が入ると思っていても、実際には期待していたほど集まらない場合もあります。葬儀費用を考える際は、余裕を持った資金計画を立てましょう。

5. 友人葬(ゆうじんそう)
~うるさかったり、周りが見えておらず、他の参列者や近所に迷惑をかける~
「友人葬」とは、故人の友人・知人たちが主導で葬儀を取り仕切る形態の葬儀を指すことがあります。普通の葬儀と違い、宗教色が薄かったり、よりカジュアルなスタイルで執り行われるため、故人の趣味や人柄をよく知る友人たちが集まって和気あいあいと故人を偲ぶことができる、といったメリットがあります。
しかし、中には参列者同士が盛り上がりすぎて、周囲への配慮が欠けてしまうケースも。お酒を飲んで大声でしゃべったり、近所や式場の設備に大きな音が漏れたりして、クレームにつながることもあります。とくにマンションの一室でお通夜を行う場合などは、時間帯や騒音に注意が必要です。
なぜ困るのか?
- 葬儀は故人を偲ぶ厳粛な場。周囲の気持ちを考えずに騒げば、遺族や近所から苦情が出る。
- 式場や地域のルールに反する行為があると、トラブルの火種になりかねない。
対策・アドバイス
- 友人葬を行う場合でも、周囲への配慮は最優先です。特に夜間に及ぶ場合は、音量や話し声などのマナーに気を付けましょう。
- お酒を出す場合は、飲みすぎを防止する工夫が必要です。悲しみの中で飲むお酒は感情を高ぶらせることもありますので、誰かが率先して注意を呼びかける役割を担うと安心です。
- 本来の友人葬は「故人のために、故人を慕う仲間が協力して執り行う」スタイルです。故人の意志を尊重しつつ、遺族の想いにも寄り添う姿勢が大切になります。

まとめ
いかがでしたでしょうか?
葬儀は、人生の中で数少ない大切なイベントの一つです。それだけに遺族は大きな悲しみや不安を抱え、準備期間も短い中で多くの判断を迫られます。しかし、だからこそ 「葬儀社と依頼者の協力」 がとても重要になります。
- 最初の打ち合わせで基本方針をしっかり決めておく
- 予算と希望の折り合いをつけるために、優先順位を明確にする
- 適正価格やサービス内容を理解し、過度な値下げ交渉は避ける
- 支払い時期や方法は事前に相談し、無理なく対応できるようにする
- 周囲への配慮を忘れず、故人を丁寧に送り出す姿勢を心がける
こうしたポイントを押さえておけば、葬儀社とのやり取りもスムーズになり、結果として満足のいくお見送りができるはずです。もしこれから葬儀を考えている方がいらっしゃれば、ぜひ今回ご紹介した「こんな依頼者にはなりたくない!」という反面教師の例を参考に、素敵な葬儀になるよう準備を進めてみてください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。皆さんの大切な方とのお別れが、心のこもったかたちで実現しますよう、心からお祈り申し上げます。もし疑問点や心配事があれば、遠慮なく葬儀社や専門家に相談してみてくださいね。
オススメブログ
1、海洋散骨の総費用を徹底解説!家族同行や葬儀の有無で変わる具体的な金額とは?



