
葬儀の席で行われるお焼香(しょうこう)は、日本人にとって非常に馴染み深い儀式でありながら、いざ自分が参列者として焼香を捧げる場面になると「何回つまむの?」「どんな順番で進めばいいの?」「宗派によって作法が違うって聞いたけれど……」と戸惑うことも多いものです。さらに、実際の葬儀では出棺までの時間制約や参列者の人数、葬儀社・導師(僧侶)・司式者の判断によって焼香のやり方が変わることもあります。
本記事では、まずはお焼香の意味や基本的な流れ、宗派による回数や違いを解説します。続いて、司会進行役の説明がいかに重要か、そして当日の状況次第でどのように対応すればよいのかという点を詳しく紹介していきます。参列者として葬儀のマナーを押さえておきたい方、あるいは家族葬や小規模葬を検討中の方など、幅広い方に読んでいただける内容です。ぜひ最後までお付き合いください。
1.お焼香とは? その意味と目的
1-1.お焼香の基本的な意味
お焼香は、香(抹香・線香など)を焚いて故人や仏、先祖を敬い、供養する行為です。仏教では古くから、香を焚くことで場を清め、仏や故人への敬意を表すとされてきました。お焼香の煙は上方へと昇り、「故人やご本尊へ想いを届ける」「場の邪気を祓う」とも言われています。
また、日本では仏式葬儀や法要の際にお焼香を捧げる光景が一般的ですが、場合によっては神道やキリスト教では別の儀式に置き換えられるため、そもそもお焼香自体がない葬儀も存在します。仏教以外の宗教の場合、神道であれば玉串奉奠(たまぐしほうてん)、キリスト教であれば献花や聖水・聖香を使ったしきたりなどが行われるため、宗教や宗派ごとの違いを把握しておくと安心です。
1-2.お焼香が行われる場面
- 通夜・告別式(仏式葬儀)
- 法要(初七日、四十九日、一周忌など)
- 自宅の仏壇でのお参り(抹香焼香や線香を立てる場合)
葬儀や法要の本番で行うお焼香は多くの場合、祭壇の前に焼香台が用意され、参列者が順番に香を捧げる形をとります。
2.お焼香の基本的な流れ
2-1.一般的な流れ
- 焼香台の前へ進む
司会進行役や葬儀社のスタッフから案内があったら、指定されたタイミングで焼香台へ向かいます。歩くときは、厳粛な雰囲気を乱さないよう、静かに移動するのが基本です。 - 祭壇・遺影に向かって一礼
焼香台の正面に立ち、祭壇や遺影へ軽く一礼をします。これは故人や仏への敬意を示すための最初の動作です。 - 香をつまんでくべる
- 右手の親指・人差し指・中指の三本で香をつまみます。
- 香炉へ入れる回数は宗派や導師の指示によって異なりますが、1~3回が多いです。
- 浄土真宗の場合などは「香を額に押し頂かない」作法があるなど、細かい違いが出ることもあります。
- 合掌・礼拝
香をくべ終わったら、合掌をして心を込めて故人を偲びます。その後、軽く一礼しましょう。 - 退いて席に戻る
焼香が済んだら、会場の混雑状況を見つつ、ゆっくりと席に戻ります。周囲への配慮を忘れずに静かに移動しましょう。
2-2.立礼焼香と座礼焼香
- 立礼焼香(りつれいしょうこう):立ったまま焼香を行う形式。葬儀会場が広い場合や、椅子席が用意されている場合に多く見られます。
- 座礼焼香(ざれいしょうこう):畳の部屋や仏間で、正座・跪坐(きざ)の姿勢から焼香台に手を伸ばして行う形式。慣れていないと身体に負担がかかることもあり、近年は会場の事情や高齢者の参列を考慮して、椅子席・立礼焼香にするケースが増えています。

3.宗派によるお焼香の違い
「お焼香の回数や作法には諸説あり」というのは、仏教の宗派が多岐にわたることが大きな原因です。以下は主な宗派の一般的な焼香回数や特徴です。ただし、地域や寺院によっても作法が微妙に異なる場合があります。
- 浄土宗
- 回数:1回
- 阿弥陀如来への念仏を重視する浄土宗は、シンプルに1回だけ香をくべるケースが多いです。
- 浄土真宗(本願寺派・大谷派など)
- 回数:1回(場合によって2回)
- 香を額に押し頂かないのが特徴。自力ではなく他力(阿弥陀如来の本願)で救われるという教えが根底にあり、「押し頂く行為は不要」とされることも。
- 曹洞宗
- 回数:2回(または3回の場合も)
- 禅宗の一派。姿勢や所作を重視しつつ、静かに香をくべることが大切とされます。
- 臨済宗
- 回数:1回または2回
- 同じく禅宗の一派だが、地域や寺院によって異なる場合があり、あまり厳密に定義されていないことも。
- 日蓮宗
- 回数:1回または3回
- 「南無妙法蓮華経」の唱題(しょうだい)を重視し、導師やお寺の方針で回数が決まることが多いです。

4.導師や司式者、葬儀社の進行による違い
実際の葬儀や法要では、導師(僧侶)や司式者、または葬儀社の司会進行役が全体のスケジュールを管理しています。宗派の作法を踏まえつつも、式場の使用時間や火葬場の予約時間、参列者の人数などを考慮して進行を組み立てるため、当日に**「本来の作法」とは微妙に異なる指示や簡略化が行われる**ことがあります。
4-1.導師(僧侶)による違い
- 同じ宗派でも、お寺ごとの考え方や地域の習慣により回数が微妙に異なる
- 「今回は2回でお願いしましょう」と具体的に指示されたり、「押し頂きは不要です」と説明されたりする場合も。
- 法要や葬儀の開始前に「焼香は何回ですか?」と確認すれば、スムーズに対応できます。
4-2.司式者(神官・牧師など)による違い
- 神道の葬儀では、お焼香の代わりに**玉串奉奠(たまぐしほうてん)**を行うため、そもそもお焼香はありません。
- **キリスト教(カトリック・プロテスタント)**の葬儀でも、献花や聖水を振りかける灌水などが行われ、お焼香は行わない場合がほとんどです。
- 仏式以外の葬儀に参列するときは、「お焼香」という行為がない可能性もあると認識しておきましょう。
4-3.葬儀社の進行管理による違い
- 出棺の時間が迫っている、火葬場の予約時間があるなど、時間がタイトなときは焼香回数を1回に統一するなどして簡略化される場合があります。
- **参列者が非常に多い場合(社葬・合同葬・著名人の葬儀など)**では、全員に焼香させると膨大な時間がかかるため、代表者のみ焼香し、他の参列者は合掌だけにするケースも珍しくありません。
- 家族葬や小規模葬であれば、ゆっくりと正式な作法で焼香できる場合も多く、柔軟に対応が行われています。
5.出棺までのタイムリミットや参列者数による変化
5-1.時間制限がある場合
葬儀の進行は、火葬場の予約時間や式場のスケジュールに大きく左右されます。**「○時までに出棺しなければならない」**というタイムリミットがあると、焼香に時間をかける余裕がなくなることも。
時間短縮の工夫
- 焼香回数を1回に統一
- 人数を分散して一斉に焼香(複数の焼香台を用意する場合も)
- 喪主や近親者のみ焼香して、一般参列者は省略または合掌だけ
参列者としては、「本来は2回や3回するものなのに1回で大丈夫なのか?」と気になるかもしれませんが、葬儀社や導師の指示に従うことが最善策です。何よりも、円滑に儀式を進行するための措置と考えれば、無理にこだわる必要はありません。
5-2.参列者の数による影響
- 参列者が多い場合(数百~数千人レベルの大規模葬):全員が2~3回ずつ焼香すると膨大な時間がかかるため、1回に簡略化したり、代表焼香や献花形式に変更したりすることがあります。
- 参列者が少ない場合(家族葬・小規模葬):時間的な制約が少ないため、宗派の伝統的な作法をしっかりと踏まえて焼香が行われることが多いです。故人との最期の時間をゆっくり過ごせるため、遺族の意向や導師のアドバイスを細かく反映しやすいのも特徴です。
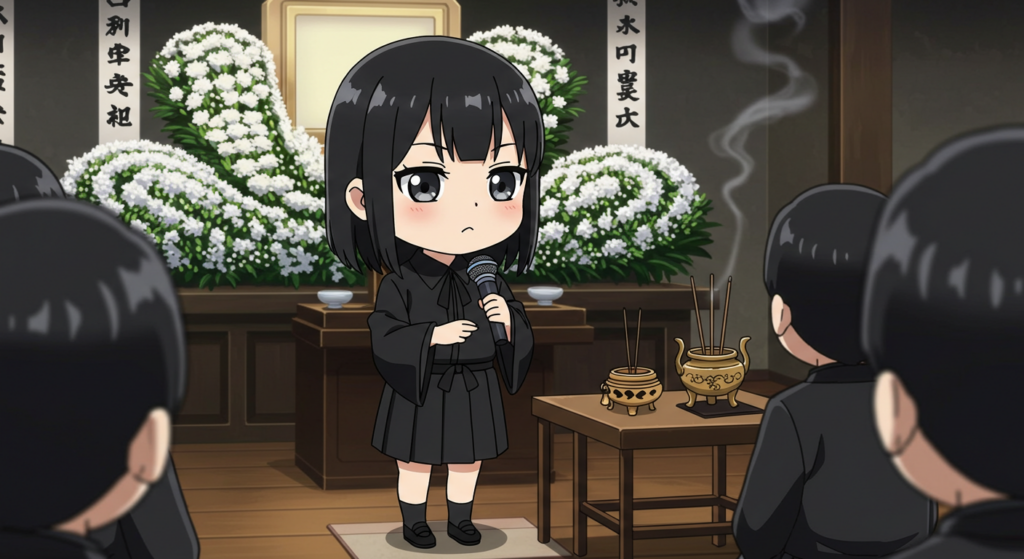
6.もし作法がわからないときの対応
いざ参列した際に、**「何回香をくべればいいか分からない」「指示がなかったけどどうしよう?」**と焦ることもあるかもしれません。そういったときは、以下の方法で対処しましょう。
- まずは周囲の様子を見る
喪主や先に焼香した人の動きや回数を見て、合わせるのが無難です。同じ葬儀会場なら、一人だけ大きく異なる回数で焼香するよりは、揃えておいた方が落ち着きます。 - 係員や導師に直接尋ねる
大きな葬儀では葬儀社のスタッフが案内をしてくれることが多いですし、法要など小規模な場では、導師に「焼香は何回でしょうか?」と聞くことができます。遠慮しすぎて後で失敗するより、事前確認で安心できる方がずっと良いです。 - 基本的には1回でも問題ない
宗派による違いはありますが、**「香をくべる回数が1回」**というのは比較的多くの宗派で通用します。もし分からないときは、1回にしておくと大きなマナー違反にはならないでしょう。
7.宗教や宗派の作法を知った上で、司会進行役の説明を優先する大切さ
ここまで見てきたように、仏式の宗派によるお焼香の違いや、司会進行役・導師・葬儀社が当日の進行都合で指示を変えるケースが多々あります。大切なのは、宗派の一般的な作法や意味を理解しつつも、「当日の説明を優先して従う」姿勢を持つことです。
- 当日の説明が最優先:進行役が「今日は時間の都合で1回にしましょう」と言えば、その指示が正解です。
- 宗派の作法を知っているとスムーズ:知識を持っていると、状況に応じて「なるほど、今日はこうするんだな」とすぐに納得でき、余計な戸惑いや不安が減ります。
- 形式にとらわれず、心を込める:最も大切なのは、故人や仏、神に対する敬意と祈りの気持ちです。形だけに囚われてしまうより、心を落ち着けて合掌することが供養になります。

8.まとめ:柔軟な対応と真摯な気持ちが大切
お焼香の作法や回数は、宗派による違いや**葬儀・法要の状況(時間・人数・会場)によって大きく変わります。そのため、「この宗派だから絶対に2回でなければならない」「押し頂きしないとマナー違反」**といった決めつけは、かえって当日の進行を乱してしまうこともあるのです。
- 知識を仕入れつつ、当日の案内を尊重しよう
基本的なマナーや作法は事前に勉強しておくと安心ですが、いちばん大切なのは司会進行役や導師、葬儀社スタッフの説明です。 - 出棺までの時間や参列者数にも注意
時間が限られている場合や、参列者が非常に多い場合、焼香は簡略化されるケースが多くあります。逆に家族葬など少人数の場合は、伝統的な作法をゆっくり楽しみながら行えるでしょう。 - 形よりも心を込めること
焼香はあくまで「故人を偲ぶ」ための供養の一環です。回数や所作も大事ですが、それ以上に故人への感謝や祈りの気持ちが大切です。焦って形にとらわれるより、「手を合わせて想いを届ける」という心の姿勢が何より重んじられます。
もし葬儀の場に直面したときは、本記事の内容を思い出し、柔軟に対応してみてください。「宗派別の作法をうまく実践すること」と「当日の指示に従い、心を込めて供養すること」を両立すれば、きっと後悔のないお別れができるはずです。
■ お焼香に関するポイントのおさらい
- お焼香の意味:香を焚くことで故人や仏に敬意を表し、場や心を清める。
- 宗派による回数の違い:1~3回が多い。浄土真宗では押し頂きを行わないなどの特徴も。
- 導師や司式者、葬儀社の指示:当日の進行状況(時間・人数)に応じて簡略化や変更があり得る。
- 出棺までのタイムリミット:火葬場の予約時間などで時間が限られると、焼香を省略・短縮するケースも。
- 参列者の多さ:大規模葬では、焼香を1回に統一したり、代表者のみの焼香や献花に切り替えたりする。
- わからないときは確認・周りに合わせる:周囲の人の回数を見たり、スタッフに質問したりして臨機応変に対応。
- 最も重要なのは心:形式的な回数や所作より、故人を想う真摯な気持ちが何よりの供養となる。

終わりに
「お焼香」という言葉は聞き慣れていても、いざ自分がやってみると意外と緊張し、思わぬところで迷ってしまうものです。しかし、宗派ごとの違いや当日の司会進行役からの説明の重要性を理解しておけば、たとえ初めての葬儀参列でも落ち着いて行動できます。
悲しみに包まれる場面であっても、最後の別れをきちんと行うことは、故人への礼儀であり、私たち自身が気持ちの整理をするうえでも大切な儀式です。どうしても作法がわからないときには、「葬儀社や導師に質問する」「周囲の動きを見て合わせる」ことを意識してみてください。そして何より、**「形式よりも心」**の姿勢を持って故人を送り出せれば、きっと後悔の少ない見送りができることでしょう。
もし、より詳しい手順や宗派別の深いマナーを知りたい場合は、事前に書籍や専門サイトで情報を調べたり、直接お寺や葬儀社に相談しておくのもおすすめです。突然訪れるかもしれない「そのとき」に備えて、ぜひ本記事を参考にしていただければ幸いです。合掌。
オススメブログ!
1、葬儀社が本音で語る! こんな「困った依頼者」にならないための5つのポイント



