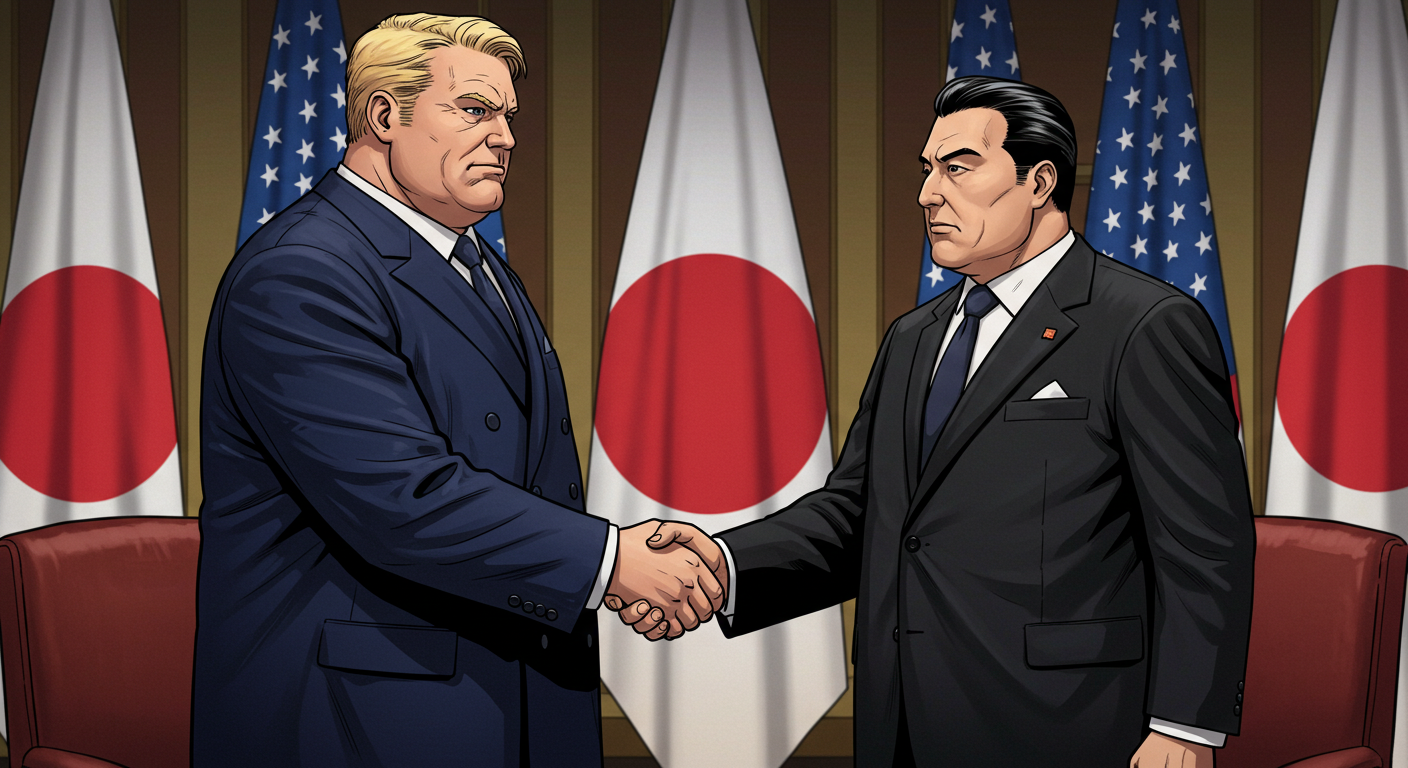はじめに
日本では一般的に、お葬式には数十万円から100万円以上かかることも珍しくありません。葬儀社によっては祭壇や式場代、飲食費、返礼品など様々なオプションが加わり、最終的な費用が当初の見積もりよりも大幅に高くなるケースも報告されています。
しかし、近年は高齢化や核家族化の進行、そして価値観の多様化により、**「できるだけ費用を抑えたい」「豪華にしなくても、最低限のお別れができればいい」**というニーズが増えています。そこで注目されているのが、公営火葬場や公営葬儀を活用するという選択肢です。
- 「公営火葬場・公営葬儀って何?」
- 「民間の葬儀社とどう違うの?」
- 「本当に安く済むの?その分、質が下がるのでは?」
本記事では、こうした疑問に答えつつ、公営の火葬場・公営葬儀を使うメリットや注意点、さらに費用を抑えながらも一定の満足度を得るためのコツをご紹介します。大切な故人を送る時間を、できるだけ心に残るものにしたい方は、ぜひ最後までお読みください。

1. 公営火葬場・公営葬儀とは?
1-1. 公営火葬場の概要
公営火葬場とは、自治体(市区町村や都道府県)が運営する火葬施設のことを指します。民間経営の火葬場と異なり、税金が投入されているため、住民が利用する場合には非常に安価で火葬を行うことが可能です。
- 住民料金が安い理由
公営火葬場では、住民が火葬を利用する際に補助が適用される仕組みが多く、例えば東京都内では2,000~10,000円程度、大阪市であれば10,000円前後など、比較的低額で火葬ができます。 - 他地域住民の割増料金
一方で、利用する火葬場が所在する自治体の住民でない場合、大幅に火葬料金が上がることがあります。たとえば、東京都瑞江葬儀所では区民料金7,000円に対し、区外の方は数万円以上というケースも。
1-2. 公営葬儀の概要
公営葬儀とは、自治体が直接・または指定管理者としての葬儀社を通じて、低価格の葬儀プランを提供している仕組みを指します。具体的には「〇〇市公営葬儀」「市営葬儀プラン」などの名称で運営している自治体が多いです。
- セットプランが多い
一般的に、火葬だけではなく祭壇や遺体搬送、ドライアイスなどの基本的な項目がセットになっており、総額で10万~20万円程度のケースが多いです。 - 利用条件
多くの場合、その自治体の住民であることが条件となります。また、収入や家族構成によってはさらに補助を受けられる場合があります。
1-3. 民間式場との比較
| 項目 | 公営火葬場・公営葬儀 | 民間式場・民間火葬場 |
|---|---|---|
| 運営主体 | 自治体(税金が投入) | 葬儀社や関連企業 |
| 料金 | 住民は割安(数千円~) | 一般的に高め(火葬料数万円~) |
| サービス内容 | 最低限の設備・シンプル | 多彩なオプション・豪華設備もあり |
| 利用制限 | 住民以外は割増、または不可 | 基本的に誰でも利用可能 |
| 混雑状況 | 時期によっては予約待ちあり | 施設数が多いため比較的選びやすい |

2. 公営火葬場・公営葬儀を利用するメリット
メリット1:費用が安い
最大のメリットは、何といっても費用を抑えられること。
火葬費用が住民割で数千円~1万円台になる自治体もあり、葬儀自体も公営プランを使えば総額が10万~20万円前後に収まるケースが多いです。民間の一般葬が50万~100万円以上かかることを考えると、かなりのコストダウンが期待できます。
メリット2:一定のサービス品質が担保されている
「安い=質が悪い」とイメージしがちですが、公営施設は自治体の基準を満たすための設備や衛生管理が整備されています。最低限の清潔感や設備はきちんと整っているため、安心して利用できるという声も少なくありません。
メリット3:住民割引や自治体独自の支援がある
自治体によっては、独自の支援策として**“住民割引”だけでなく、“低所得者向けの補助”や、“生活保護受給者向けの葬祭扶助”**などが整備されているところがあります。そのため、経済的負担が大きい世帯ほど、公営の活用メリットが大きいと言えるでしょう。
3. 公営火葬場・公営葬儀を利用する際の注意点
注意点1:予約が取りにくい時期がある
公営火葬場は安価で利用しやすい反面、混雑しやすいです。特に冬場は死亡者数が増える傾向にあり、火葬場の予約が埋まるスピードが早いです。
- 予約待ちが発生
数日~1週間以上待ちになることも珍しくありません。 - プラン内容が制限される場合も
混雑期は短時間での利用に限られることがあり、ゆっくりお別れする時間が取りにくいケースもあります。
注意点2:自治体ごとの利用条件
公営火葬場・公営葬儀は、その自治体に住民票がある方が優遇される仕組みです。住民でない場合、火葬料が数万円~数十万円と大幅に上がることもあるので注意が必要です。また、公営葬儀の利用にも一定の条件が課される場合があります。
- 例:市内在住○年以上、直近で転入してきた人は対象外、など
- 例:同一市区町村での葬儀のみ補助対象、近隣他市からの利用は割引無し
注意点3:自由度が限定される場合がある
公営施設では、民間式場ほどの装飾・演出の自由度が低いことが多いです。例えば、「大きな祭壇を飾りたい」「映像演出を使いたい」といった要望は、自治体の規定で制限される場合があります。そのため、シンプルな葬儀を望む方に適した選択肢と言えるでしょう。
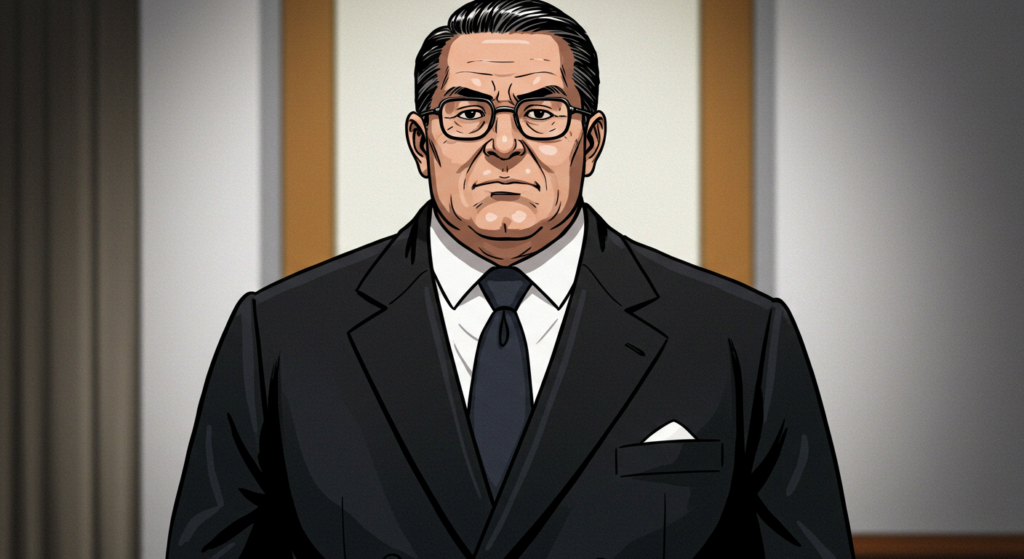
4. 費用を抑えつつ、ある程度の満足度を得るコツ
コツ1:最低限必要な項目を見極める
葬儀には大きく以下の費用項目が含まれます。
- 火葬料(火葬施設使用料)
- 式場使用料
- 祭壇・棺・ドライアイスなどの備品費
- 遺体搬送費
- 人件費(スタッフ)
- お料理・お返し物(必要な場合)
まずは、絶対に外せない項目(火葬料や棺など)を把握し、それ以外のサービスが本当に必要かどうかを精査してみましょう。これだけでも数万円以上の節約につながります。
コツ2:式場の規模より“お別れの時間”を大切に
「大きなホールで派手に行う」=「立派な葬儀」というイメージは、もはや時代遅れかもしれません。むしろ、少人数でもゆっくりと故人をしのぶ時間を設けるほうが満足度が高いという声が増えています。
- 家族葬や少人数葬
公営火葬場の付帯施設や、小規模の公営斎場であれば、必要最低限のスペースだけ借りて家族葬を行うことも可能。 - 直葬(火葬式)+お別れの会
火葬後に別の場所で「お別れの会」を開く方法も検討してみましょう。金銭的負担を抑えつつ、思い出を共有できる場を設けられます。
コツ3:オプションは必要なものを厳選
葬儀社に依頼する際、様々なオプション(祭壇ランクアップ、装花、供物、遺影加工など)が提示されることがあります。心理的に「こんな時こそ手を抜くわけには…」と思いがちですが、オプション費用は合計するとかなりの額になるケースもあります。
- 本当に故人や遺族が望むものかを再確認
- 価格の比較:見積もりを取って、「必須オプション」「あった方がいいオプション」「不要なオプション」に仕分ける
コツ4:オンラインやデジタルツールを活用
コロナ禍以降、リモート参列やオンライン追悼の仕組みが普及してきました。遠方の親戚・友人が集まれない場合でも、オンラインで参列できるようにすれば、あまり大勢を呼ばなくても心のこもったお別れができます。
- ライブ配信:スマホやタブレットからZoomなどのツールを使って中継
- 動画メッセージ:参列できない方からのメッセージ動画を撮影・編集して流す
- SNSや専用追悼サイト:故人の写真や思い出を共有しやすい

5. 公営葬儀の手続き・流れ
Step1:市区町村のHPや相談窓口をチェック
まずは、ご自身がお住まいの自治体のホームページを確認しましょう。「〇〇市 公営葬儀」「〇〇市 公営斎場」「〇〇市 火葬場料金」などのキーワードで検索すると、利用条件やプラン内容が掲載されている場合があります。見当たらない場合は、市役所や保健所などに問い合わせてみると良いでしょう。
Step2:公営葬儀プランの有無を確認
自治体によっては、公営火葬場のみ運営していて公営葬儀プランは用意していない、という場合があります。その場合、公営火葬場を使いつつ、葬儀自体は民間業者で行う形が一般的です。また、自治体によっては葬儀会社の指定管理者が公営プランを提供していることもあるので、そちらも確認してみましょう。
Step3:葬儀社に依頼する or 自治体指定の業者と打ち合わせ
- 公営火葬場の予約
多くの場合、葬儀社が代行して予約してくれます。自分で予約を行う場合は、自治体の電話窓口などから予約システムを利用します。 - 費用見積もりの取得
公営プランかつ最低限の家族葬や直葬で行いたい旨を伝え、明確な見積もりを出してもらいましょう。オプション費用も忘れずに確認。
Step4:式当日の流れ・火葬の予約
- 通夜や告別式を行う場合
公営葬儀プランのスケジュールに沿って進行します。式場の使用時間に制限がある場合が多いため、事前に「何時に集合するか」「どれくらいお別れの時間が取れるか」をよく確認しましょう。 - 直葬や家族葬の場合
最低限の準備のみなので、火葬の時間さえ確保できれば短時間で終わります。お別れの時間は短いですが、人数を絞る分、気持ちを集中しやすいというメリットもあります。
6. 公営火葬場・公営葬儀の料金イメージ(事例)
ここでは、いくつかの自治体の事例をご紹介します。具体的な金額は変更される場合があるため、必ず最新情報を公式サイト等でご確認ください。
6-1. 東京23区の例
東京23区には都営・区営の火葬場がありますが、実際には民間の指定管理者(東京博善など)が運営しているケースもあります。
- 区民の火葬料:7,000円~10,000円程度
- 区外利用:5万~10万円以上になることも
- 公営葬儀プラン:各区ごとに存在する場合があり、10万~25万円程度が多い
6-2. 大阪市の例
- 大阪市立北斎場:大阪市民なら火葬料が1万円前後
- 公営葬儀プラン:大阪市が提携する指定業者のセットプランがあり、10万~15万円台で利用できるケースがある
6-3. 横浜市の例
- 横浜市営斎場:横浜市民は火葬料12,000円~
- 市営葬儀プラン:内容によるが、15万~20万円程度が一般的

7. Q&A:よくある質問
Q1:他の市区町村でも公営火葬場を利用できる?
A:利用自体は可能なケースが多いですが、住民割引が効かず、料金が割高になります。 たとえば、東京都区外の人が23区の火葬場を利用すると数万円~10万円以上かかることがあります。また、自治体によっては「原則として住民のみ」の方針を取っている場合もあるので、事前確認が必須です。
Q2:生活保護を受給している場合はどうなる?
A:生活保護受給者には「葬祭扶助」が適用される場合があり、一定の条件を満たすと原則無料~20万円程度の補助で直葬(火葬式)を行うことができます。住民票のある自治体の福祉課に事前相談しましょう。
Q3:公営だと“安かろう悪かろう”にならない?
A:必要最低限の設備や衛生管理はしっかりしています。 ただし、民間の豪華な会場やきめ細かいサービスを求めると物足りない可能性はあります。とはいえ、最低限の儀式やお別れの場を設けるには十分な品質を保っている自治体が多いです。
8. まとめ:公営施設の上手な活用で、無理のない葬儀を
葬儀費用を大幅に抑えたいと考える方、あるいは**「質素でも、心のこもった葬式がしたい」と思う方にとって、公営火葬場・公営葬儀の利用は大変有力な手段です。住民であれば火葬料が格安になり、公営葬儀プランを選べばトータル費用が10万~20万円**に収まることも珍しくありません。
一方で、予約の取りづらさや自由度の制限、居住地条件などのデメリットもあるため、利用を検討する際には早めの情報収集が重要となります。複数の自治体や火葬場・葬儀社のプランを比較し、自分や家族に合ったスタイルを選ぶことがポイントです。
【今からできるアクション】
- 住んでいる自治体のHPをチェック
「公営葬儀」「火葬場料金」「斎場利用」などのキーワードで検索し、どのような制度やサービスがあるか調べてみましょう。 - 複数の葬儀社に見積もりを取る
公営火葬場を利用する場合でも、葬儀社を通さないとスケジュール調整が難しいケースが多いです。ぜひ価格やプランを比較してください。 - 家族や親戚と事前に相談
「直葬(火葬のみ)で十分なのか」「最低限の通夜やお別れの場を設けたいのか」など、事前に意向をすり合わせておくとスムーズに進みます。 - オンライン追悼やリモート参列も検討
遠方の親戚や多忙な友人などが参加しやすいように、デジタルツールを活用するのも一案です。
【まとめのメッセージ】
公営火葬場や公営葬儀は、費用を抑えながらも最低限の品質を維持し、故人を送るための選択肢として、多くの方に支持されています。特に、予算面に不安を抱えるご家庭や、シンプルで落ち着いた葬儀を望む方にとっては、非常に大きなメリットがあります。
- 大切なのは、単にコストを削ることが目的ではなく、「どう送り出すか、どこに気持ちを込めるか」を考えること。
- 施設自体はシンプルでも、家族や親しい友人が心を込めてお別れの言葉を交わす時間さえ確保できれば、後悔のない式を執り行うことができます。
もし「葬儀費用が高すぎる」「業者選びに不安がある」という方は、ぜひ一度、公営火葬場・公営葬儀の情報をチェックしてみてください。きっと、ご自身に合った“ある程度の満足感を得られるお葬式”を見つけられるはずです。

関連記事・参考リンク
- 厚生労働省「死亡数の推移」
https://www.mhlw.go.jp/
→ 日本の死亡者数推移や今後の高齢化データが掲載されています。 - 各自治体公式サイト
- 公営斎場ナビ系サイト(各市区町村の公営斎場が掲載されている民間の情報サイト)
→ 「公営 斎場」「公営 火葬場 検索」などで検索すると見つかります。
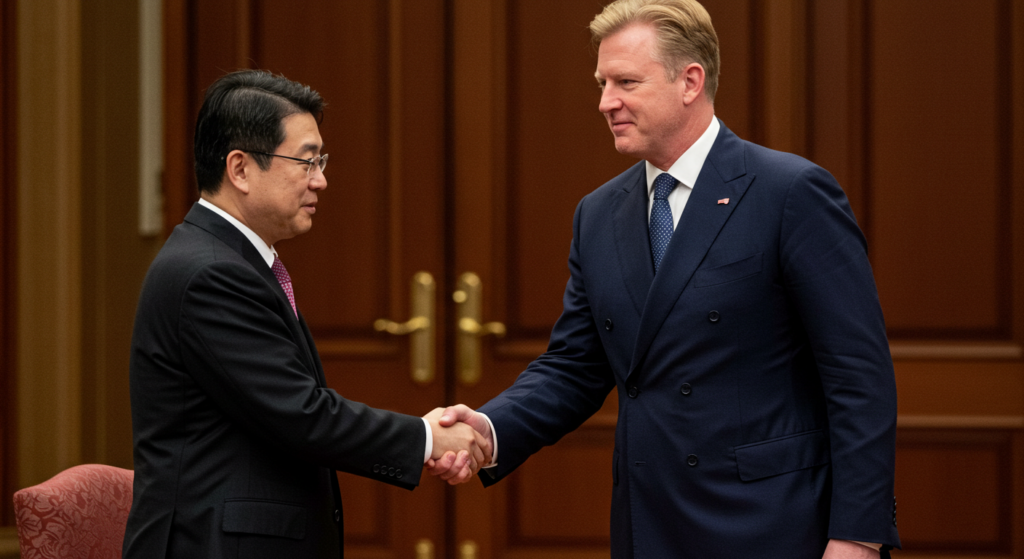
最後に:時代に合った葬儀のかたちを
葬儀のスタイルはここ数年で大きく変化しています。以前は「大勢を呼んで、何日もかけて盛大に行う」ことが一般的でしたが、今や家族葬・直葬・リモート参列など、多様な選択肢が当たり前の時代になりました。
その一方で、「どうしても費用面で心配がある」「お金がなくて葬儀をあきらめたくない」という方も増えています。そんな方々にとって、公営火葬場・公営葬儀はまさに“救世主”的な存在になるでしょう。
- 最低限の儀式を確保しつつ、懐にも優しい
- 必要以上に豪華な装飾をせずとも、しっかり故人を偲ぶことは可能
- 自治体によっては追加補助や低所得世帯支援がある
「公営」というだけで敷居を高く感じる方もいるかもしれませんが、実際には多くの利用者が満足し、コストを抑えて納得のいくお別れを行っています。ぜひあなたやご家族に合った方法を検討し、後悔のないお見送りを実現してください。
そんなあなたにこのブログ
1、 最近の葬儀トレンド〜現代の葬儀のあり方