~回数・作法・線香、それぞれのポイントを深掘り~

はじめに
葬儀や法要で「お焼香は何回?」「香は額にいただくの?」「線香は立てる?寝かせる?」と迷った経験はありませんか?
実はこれらの違いは、仏教の宗派による作法の違いが理由です。
しかも同じ宗派でも、地域や寺院によって少しずつ異なることもあります。
本記事では、主要な宗派ごとの「お焼香の回数」「作法」「線香の扱い方」をわかりやすく整理し、参列時に迷わないための実践ポイントを解説します。
これを読めば、どの場面でも落ち着いてお焼香ができるようになります。
お焼香の意味と基本作法
お焼香とは、香を焚いて心身を清め、故人や仏に対して敬意と感謝を表す行為です。
本来は「供養」だけでなく、「自らの心を整える」ための意味もあります。
お焼香の基本手順
- 祭壇前に進み、一礼して合掌
- 右手で香をつまみ、左手を添えて香炉へ
- 宗派に応じて「額にいただく/いただかない」を判断
- 終わったら合掌し、一礼して席へ戻る

宗派別お焼香マナー一覧(早見表)
| 宗派名 | 回数 | 額にいただく | 線香の本数/形 | ワンポイント |
|---|---|---|---|---|
| 浄土宗 | 3回 | いただく | 1本立てる | 故人と仏の縁を3度で表す |
| 浄土真宗本願寺派(西) | 1回 | いただかない | 1本折って寝かせる | 阿弥陀仏の慈悲を象徴 |
| 真宗大谷派(東) | 2回 | いただかない | 1本寝かせる | 本願を尊び、香を額に当てない |
| 曹洞宗 | 2回 | いただく | 1本立てる | 「静寂の心」を大切に |
| 臨済宗 | 1~3回 | いただく | 1本立てる | 格式より心を重視 |
| 日蓮宗 | 1~3回 | いただく | 1本立てる | 「南無妙法蓮華経」と唱えることも |
| 天台宗 | 3回 | いただく | 1本立てる | 三宝(仏・法・僧)への敬意 |
| 真言宗 | 3回 | いただく | 3本立てる | 密教の三密を意味する |

各宗派の特徴と実践ポイント
浄土宗のお焼香
- 回数: 3回
- 作法: 香をつまみ額にいただき、香炉に静かに入れる
- 線香: 1本を立てて焚く
- 実践ポイント:
→ 故人・仏・自分の三つの縁を表す「三香」が基本。
迷ったら、司会者や僧侶の案内に従えば安心です。
浄土真宗(西本願寺派/東本願寺派)
- 回数: 西=1回、東=2回
- 作法: 香を額にいただかず、そのまま香炉に入れる
- 線香: 折って寝かせるのが特徴
- 実践ポイント:
→ 「香をいただかない」のは、阿弥陀仏の慈悲をすでに受けているという教義から。
周囲の人が額に当てていなくても間違いではありません。
曹洞宗のお焼香
- 回数: 2回(最初の1回は供養、2回目は自らの修行)
- 作法: 香を額にいただいて香炉へ
- 線香: 1本を立てて焚く
- 実践ポイント:
→ 静かに、ゆっくりと動作することが大切。「慌てず落ち着いて」が曹洞宗の心です。
臨済宗のお焼香
- 回数: 1〜3回(地域差あり)
- 作法: 香を額にいただき、静かに供える
- 実践ポイント:
→ 格式にこだわらず、「心を込めて」が基本。僧侶の動作を参考にするのが無難です。
日蓮宗のお焼香
- 回数: 1~3回(地域・寺院による)
- 作法: 香を額にいただく
- 線香: 1本立てる
- 実践ポイント:
→ 焼香時に心の中で「南無妙法蓮華経」と唱えるのが特徴。
天台宗のお焼香
- 回数: 3回
- 作法: 香を額にいただく
- 線香: 1本を立てる
- 実践ポイント:
→ 三宝(仏・法・僧)への敬意を表す3回焼香。穏やかに香を供える姿勢が大切です。
真言宗のお焼香
実践ポイント:
→ 三密(身・口・意)を意味する3本。動作に迷ったら、僧侶の仕草を参考に。
回数: 3回
作法: 香を額にいただく
線香: 3本立てる(中央・右・左の順)
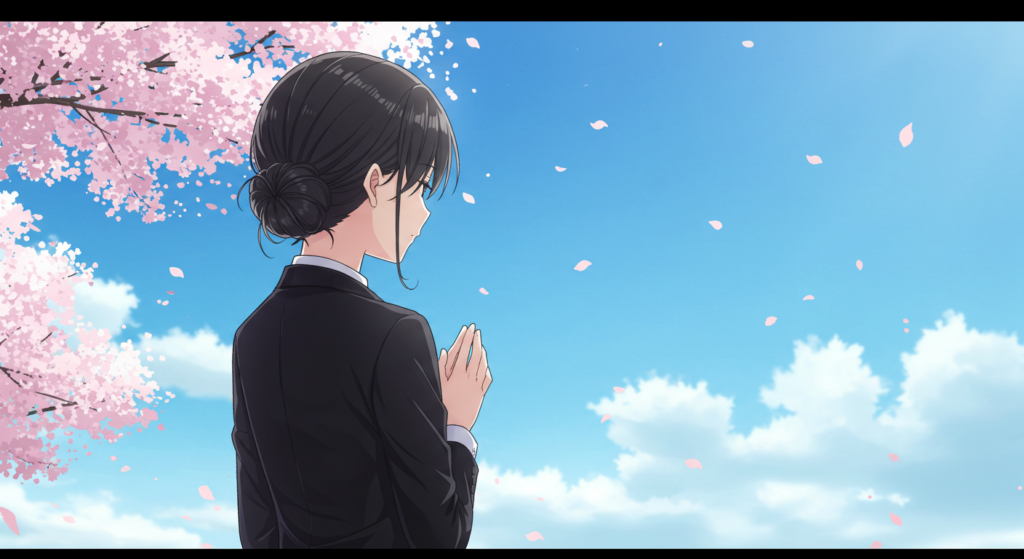
実際の葬儀でのポイント
- 会葬者が多い場合は1回で統一されることが多い
宗派ごとに2回・3回の焼香が定められていても、大勢の参列者がいる式では進行を優先して1回にまとめるのが一般的。周囲や司会者の指示に合わせて行動しましょう。 - わからなければ周囲を観察・スタッフに質問
自分とは違う宗派の葬儀に参列する際や、慣れない場合は、他の参列者の様子を見て合わせるか、司会者や葬儀社のスタッフに尋ねるのが確実です。無理に独自の作法を貫こうとするより、式の流れに従う方が安心。 - 最終的に大切なのは“故人を思う気持ち”
どの宗派であれ、根底にあるのは故人や仏への敬意と感謝。もし作法を多少間違えても、真摯な気持ちが伝われば大きな失礼にはなりません。気にしすぎて弔意が疎かにならないよう、まずは静かに手を合わせましょう。
よくある質問(Q&A)
Q1:香を額にいただくとは?
→ 右手でつまんだ香を額のあたりまで上げる動作です。仏や故人に敬意を示す意味があります。
Q2:数珠はいつ使う?
→ お焼香前後の合掌時に手にかけます。宗派ごとの形が違いますが、一般的なものでも問題ありません。
Q3:線香が寝かせてあったら?
→ 浄土真宗の形式です。立てずにそのまま横に置きましょう。
まとめ|一番大切なのは「心を込めること」
宗派によって作法や回数は異なりますが、共通して大切なのは**「故人を想う気持ち」**です。
迷ったときは、周囲や司会者の動きを見て静かに従えば十分。
そして何より、「間違えないこと」より「心を込めること」が最も尊ばれます。




