
「未就学児を葬式に連れて行くのはどうなんだろう…?」
大切な家族や親しい方を見送る葬儀の場で、お子さんを同席させることに悩む親御さんは、実はとても多いのではないでしょうか。
たとえば、こんな不安をお持ちではありませんか?
- 式の最中にお子さんが騒いでしまわないか
- しめやかな雰囲気を乱してしまわないか
- そもそも“死”というものをどう伝えればいいのか
私自身、4歳の息子を連れて祖母の葬儀に参列したとき、まったく同じ疑問や不安を感じました。
しかし、結果としては、親子ともにとても意味のある体験となったのです。
本記事では、未就学児がお葬式に参加する意義や影響、親ができる準備やフォロー、そして最近の葬儀事情(家族葬・小規模葬儀など)を踏まえて、スタッフ側のサポート体制などをわかりやすくまとめています。
「お子さんと一緒に大切な人を見送りたい」「葬儀という場を通して、命の大切さを感じてほしい」と願うすべての親御さんに向けて、ぜひ参考にしていただければ幸いです。

1. お子さんを葬儀に連れて行くことへの不安は、なぜ生まれる?
● “静粛な場”というイメージ
葬儀や告別式というと、多くの方は“厳かな場で大人しくしなければならない”というイメージを抱きがちです。
小さなお子さんはじっとしていられなかったり、泣き出したりしてしまうこともあるため、「迷惑をかけるのでは?」と不安に思うのは当然といえます。
● 「死」の概念を伝える難しさ
未就学児に「死」をどう説明すればいいのか、戸惑う親御さんも多いでしょう。
「まだ早いのではないか」「怖がってしまわないか」など、年齢に合った伝え方がわからず、悩む方は少なくありません。

2. それでも“お子さんを”葬儀に連れて行く意義とは?
● 家族の一員として、お別れの場を共有する
お子さんが葬儀に参列する一番の意義は、“家族みんなで大切な人のお別れを体験する”ということです。
普段から慕っていた祖父母や親族であれば、たとえ小さくとも「もう会えない」という事実を感じ取ることは、お子さんにとって大切な気づきとなります。
● 命や死を自然に受け止める機会
「死」を完全に避けるのではなく、家族とともに見送りの場に立ち会うことで、“命はいつか終わるもの”という理解を、やさしく伝えられるチャンスになります。
特に家族葬や小規模葬儀では、周囲が気を使うことなく、より身近な雰囲気で送り出せるため、お子さんにとっても安心感を持ちやすい環境です。
3. 実際に体験した事例:4歳児が祖母の葬儀に参列したとき
私自身の体験談として、4歳の息子を祖母の葬儀に連れて行ったときのことをお話しします。
最初は「式の雰囲気を壊すのではないか」「息子が怖がるのではないか」と迷いましたが、祖母のことが大好きだった息子本人が「行きたい」と言ってくれたため、思い切って連れていくことにしたのです。
葬儀の最中、息子は最初こそ不思議そうにキョロキョロしていましたが、私の隣りで静かに椅子に座り、お焼香のときには手を合わせていました。
終盤になって「おばあちゃん、なんで動かないの?」と聞かれたとき、「おばあちゃんはね、もう体が動かなくなっちゃったんだ。でもずっと心の中にいるよ」と伝えると、しばらく黙ったあとに「ぼくの心にもいるかな?」とたずねてきました。
「もちろんだよ」と答えた瞬間、息子は少しほっとした表情を浮かべていました。
こうして、式のあとも「おばあちゃん、ぼくが描いた絵見てくれたかな?」と話すなど、彼なりに祖母とのお別れを受け止めている様子が感じられました。
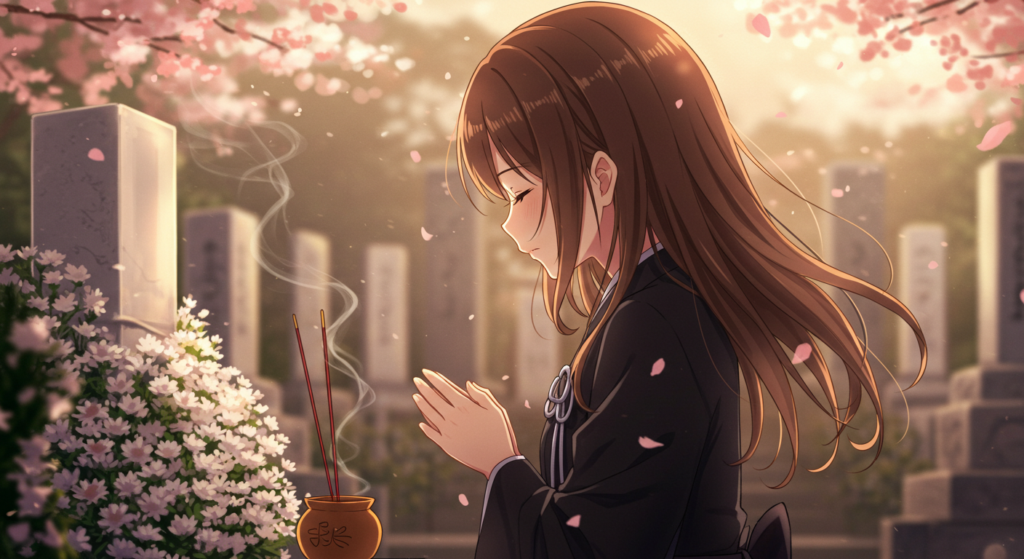
4. お子さんに「死」を説明するときのポイント
● ポイント1:年齢に合わせて、正直に伝える
「お空に行った」「天国に行った」という表現も悪くはありませんが、あまりに曖昧な言葉ばかりだと、お子さんが余計に混乱することもあります。
「もう会えなくなった」「体が動かなくなってしまった」という形で、できるだけ正直に伝えるよう心がけると良いでしょう。
● ポイント2:質問されたら都度答える
お子さんはふと思い出したように、後日になってから「なんで死んじゃったの?」「死ぬとどうなるの?」と疑問を口にすることがあります。
そのとき、忙しさなどを理由に「今はやめて」とシャットアウトしてしまうと、お子さんは不安を抱え込んでしまうかもしれません。
できる限り、素直に答えてあげるか、一緒に考える時間を作ってあげるのがおすすめです。
5. 葬儀当日にできる実践的な工夫
● 小さな役割を与える
式が始まる前に「おじいちゃん(おばあちゃん)にお花を渡してあげようね」「お手紙を描いて入れてあげようか」などと伝え、小さな役割を持たせると、お子さんは自分も“式に参加している”と感じられます。
退屈を防ぐだけでなく、お別れをより身近に考えるきっかけにもなります。
● 長時間が難しければ、無理をさせない
家族葬や小規模葬儀の場合は時間が短めですが、大規模な葬儀では式が長引くことも珍しくありません。
お子さんが退屈したり疲れてしまったら、ロビーや別室に出て休憩を取るなど、無理をさせない工夫が大切です。
● スタッフの存在を頼る
葬儀社のスタッフや会場スタッフには、お子さんの対応に慣れている方が非常に多いものです。
万が一、お子さんが泣き出してしまったり、じっとしていられなくなった場合も、「少し外の空気を吸わせてあげましょうか?」と自然にサポートしてくれるはずです。
6. スタッフやレディも子どもの参列を想定している

● 最近の家族葬・小規模葬儀の主流化
近年、「家族葬」が全国的に広がり、よりアットホームな雰囲気で葬儀を行うケースが増えています。
そのため、小さなお子さんが式に参列する場面は決して珍しくありません。葬儀社も、当たり前のように子ども対応を想定しています。
● スタッフはどう思っている?
実際、スタッフの多くは「お子さんがいるからダメ」という意識はまったく持っていません。
むしろ「大切な家族みんなで見送れるのは素敵なこと」と考えており、必要に応じてフォローや声かけを行ってくれます。
大人の側が必要以上に萎縮する必要はなく、ぜひわからないことや不安な点は遠慮なく相談してみてください。
7. 結論:気にしすぎず、ポジティブにお子さんと“家族の時間”を大切に
葬儀は悲しみの場でもありますが、同時に故人との思い出を振り返り、家族の絆を再確認する時間でもあります。
そしてお子さんにとっては、「命は永遠でない」ということを知るきっかけでもあり、何より「家族の一員として大切な人とお別れをする」という体験を通して、多くの学びを得る可能性があります。
たとえ小さい子が参列して、多少声を出したり動き回ったりしても、会場スタッフや親族は案外温かく見守ってくれるものです。
「お子さんがいると何かと心配…」と気を張りすぎると、その緊張がお子さんにも伝わってしまいます。
むしろ自然体で、**「どうか、気にしすぎないでください!」**というメッセージを改めてお伝えしたいところです。
8. 葬儀後のフォロー:お子さんの心を受け止める時間

式が終わってからしばらく経ったある日、お子さんが突然「どうして死んじゃったの?」と聞いてくることがあります。
その際は、できれば忙しくても手を止め、「どう思う?」と尋ねるなど、子ども目線の気持ちに寄り添う時間を持ってあげてください。
- 「悲しい? 寂しい? 不思議な気持ち?」
- 「分からないことがあったら、一緒に考えてみようね」
こうした声かけが、お子さんの安心感につながり、命への理解を深める一助となります。
9. まとめ:お子さんを葬式に連れて行っても大丈夫!
- 家族の一員としてのお別れは、子どもにとっても大切な経験
- 近年の葬儀スタイル(家族葬など)では、子どもの参列は珍しくない
- スタッフやレディも子ども対応に慣れているため、必要以上に萎縮しなくてOK
- 「死」の説明は年齢に合わせてシンプルに。質問には誠実に向き合う
- 無理のない範囲で役割を与えると、子どもも参加しやすい
長時間の参列が厳しい場合は、適宜外に出て休むなど、臨機応変に対応すれば問題ありません。
何より、大切な人を“家族みんなで見送る”という時間こそが、後々かけがえのない思い出となるのです。
最後に:あなたの体験も、ぜひシェアしてください
この記事を読んで、「実際にお子さんを葬式に連れて行った経験がある」「こういう工夫をしてうまくいった」など、エピソードをお持ちの方は、ぜひコメント欄でシェアしていただけるとうれしいです。
その声が、これから同じ悩みを抱える多くの親御さんの支えになるはず。
大切な人とのお別れは、悲しいだけでなく、“家族の絆”をあらためて感じる時間でもあります。
どうか気にしすぎず、ポジティブにお子さんと一緒に“家族の時間”を大切にしてくださいね。
@オススメブログ



