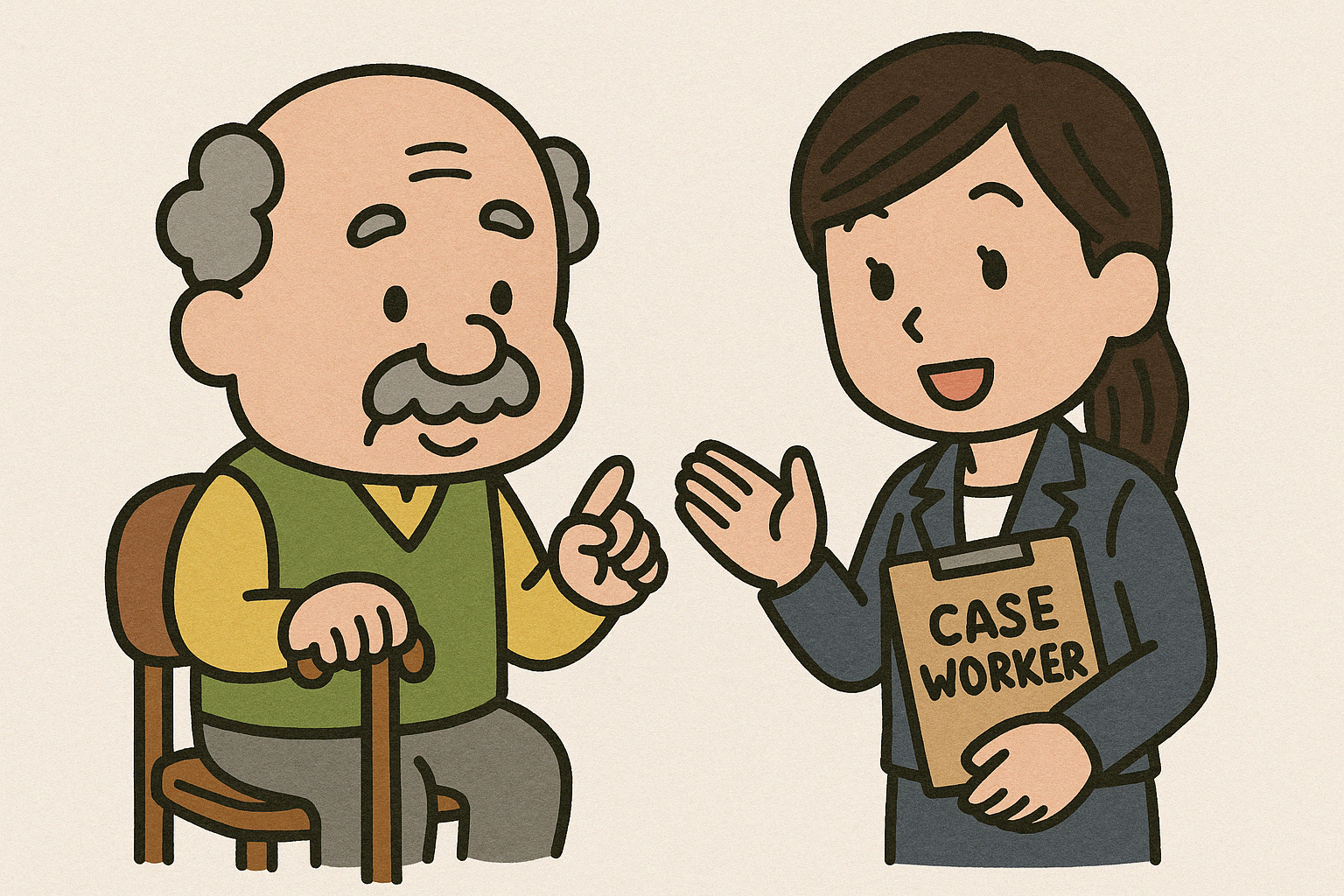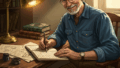~生前にやっておくべきこと・ご家族がやるべきこと~
🔰 はじめに
生活保護を受けている方にとって、「お葬式をどうすればよいのか?」は身近な悩みの一つ。
いざというときに困らないためにも、本人・家族それぞれが準備できることを整理しておきましょう。
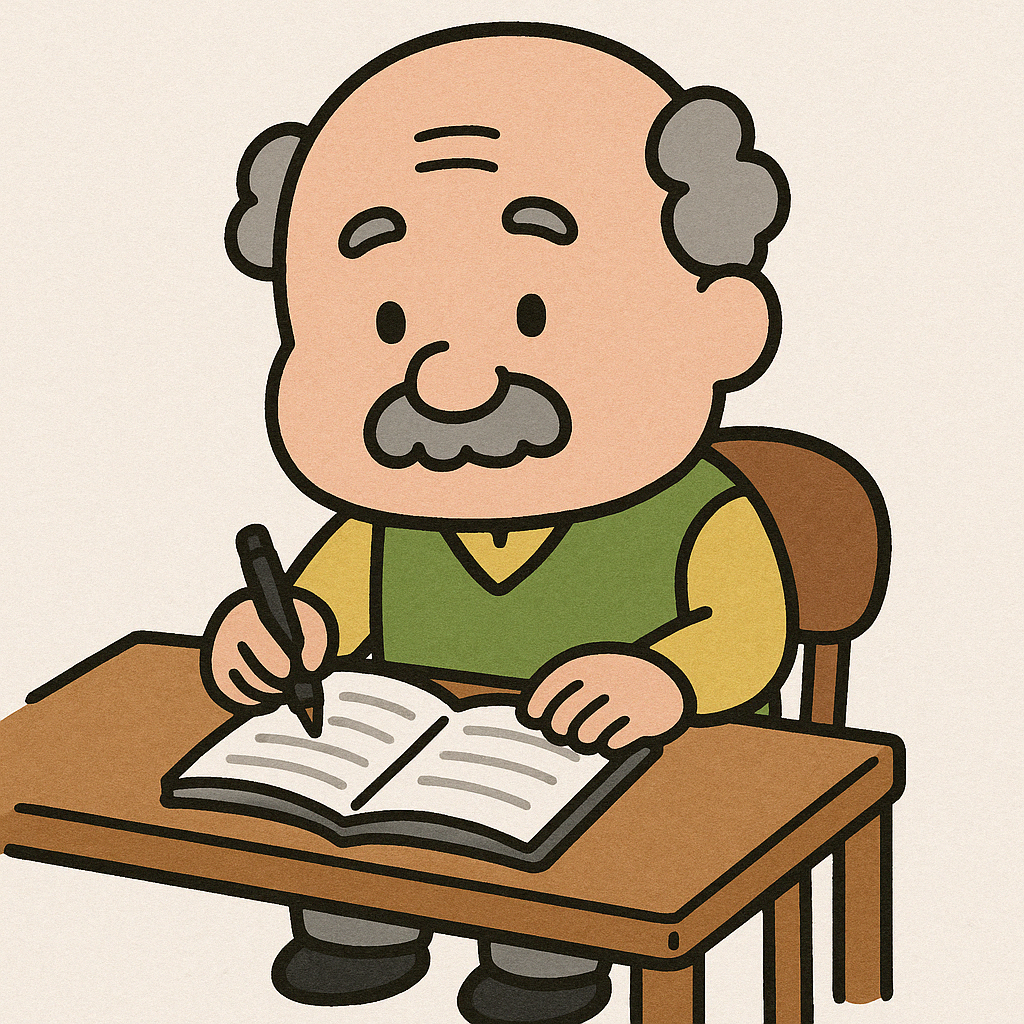
👤 本人が生前にやっておくべきこと【完全ガイド】
1. エンディングノートを書いておく ✍️
- 誰に連絡してほしいか
- 葬儀の希望(宗教・火葬式・誰を呼ぶかなど)
- 持ち物・預貯金の場所
- 延命治療の意向
▶ メモでも構いません。「書き残す」ことが大切です。

2. ケースワーカーに希望を伝えておく 📞
- 「福祉葬でお願いしたい」
- 「家族がいない/頼れない」など状況説明
- 生前から相談しておくことで、行政支援がスムーズになります。
3. 信頼できる人に話しておく 🧑🤝🧑
- 家族・知人・支援員などに「何かあったら連絡して」と伝える
- 亡くなった後にすぐ連絡できる人がいると、対応が早くなります
4. 宗教的な希望があれば記しておく 🕊
- 仏教・キリスト教など、信仰する宗教や葬送儀礼があれば明記
- 無宗教・簡素な火葬式希望でも、事前に記載するとトラブル防止に
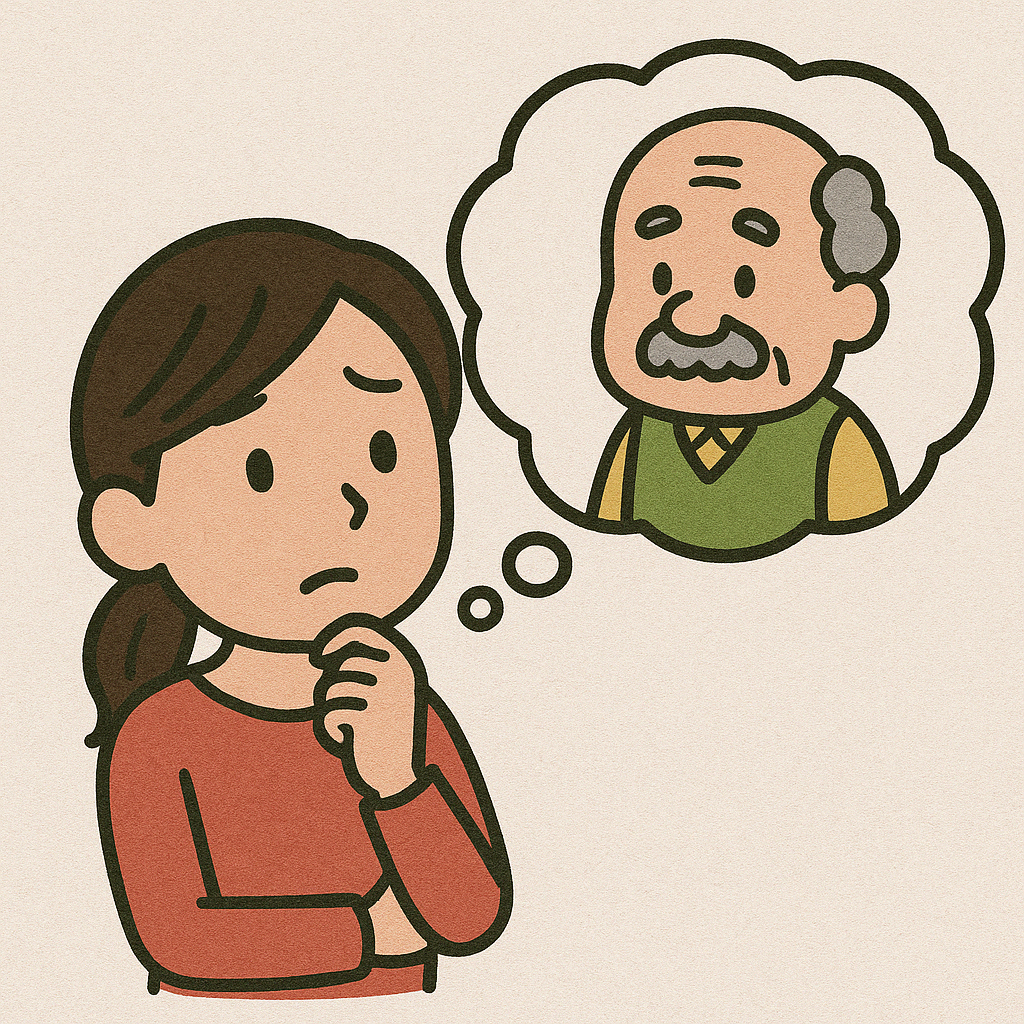
👪 ご家族・関係者がやるべきこと【亡くなった後編】
1. まずはケースワーカー(福祉課)に連絡
生活保護受給者が亡くなった場合、すぐに市区町村の福祉担当へ連絡を。
→ この時点から「葬祭扶助(福祉葬)」の申請プロセスがスタートします。
2. 火葬のみ(直葬)を希望する場合の手順
- 病院・施設からの遺体搬送が必要
- 葬儀社へ「生活保護での火葬希望」と伝える
- 福祉葬対応の実績ある葬儀社に依頼すると、手続きも安心です
3. 「葬祭扶助(福祉葬)」の申請 🧾
- 市区町村の福祉課が審査・承認
- 原則、火葬式にかかる最低限の費用が公費負担
- 遺族に扶養能力があると認定されると対象外になる場合も
4. 宗教儀礼・香典返し等は基本省略
- 僧侶の読経や香典返しは原則自己負担
- 「身内だけで静かに見送りたい」という方には適した形式
💡 ワンポイントアドバイス
- 🔸 生前に「希望を書き残す」だけでも、家族の不安がぐっと減ります。
- 🔸 福祉葬は市区町村によって運用が異なるため、早めの相談がカギです。
- 🔸 無縁仏や身元不明とならないよう、最低限の「つながり」は残しておくと◎
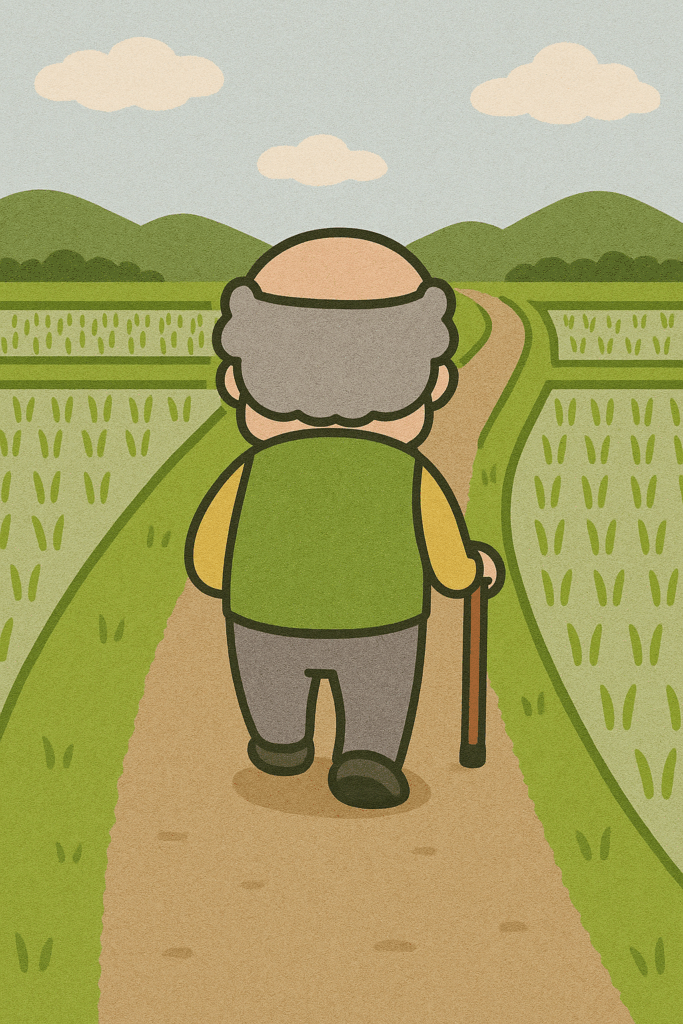
📝 まとめ|“完全版”チェックリスト
| 区分 | やっておくこと | 備考 |
|---|---|---|
| 本人 | エンディングノート | 書式自由、希望を書く |
| 本人 | ケースワーカーに意思表示 | 福祉葬希望など |
| 本人 | 信頼できる人に伝達 | 連絡先などを共有 |
| 家族 | 亡くなったら福祉課に連絡 | 最優先の連絡先 |
| 家族 | 火葬式の相談 | 簡素で dignified に |
| 家族 | 葬祭扶助の申請 | 審査あり、事前相談推奨 |
いかがだったでしょうか?事前の準備が物事をスムーズに進ませます。悲しみの中かと思いますが、やらなくてはいけない事があります。このブログが参考になれば嬉しいです。
関連ブログ