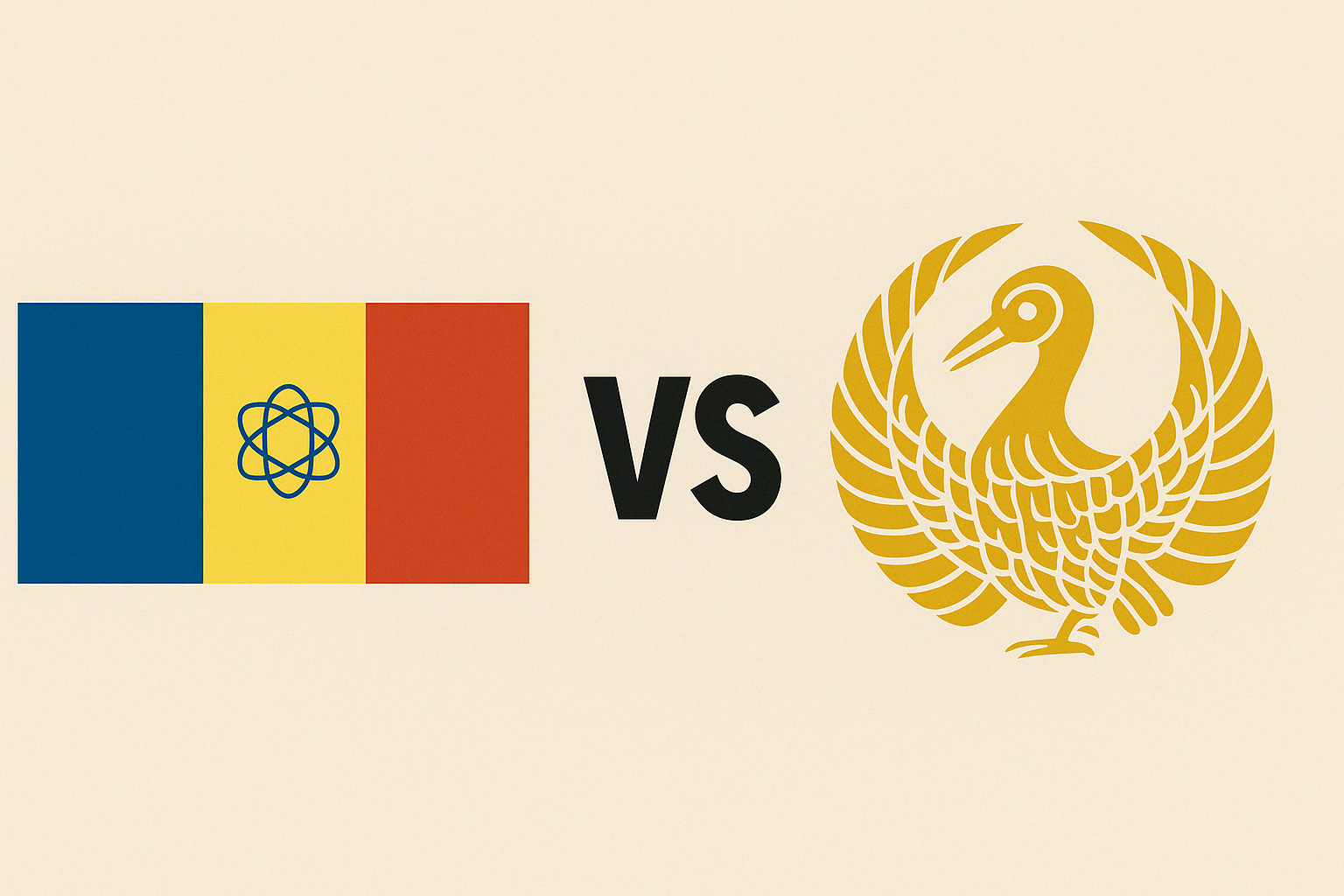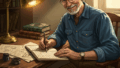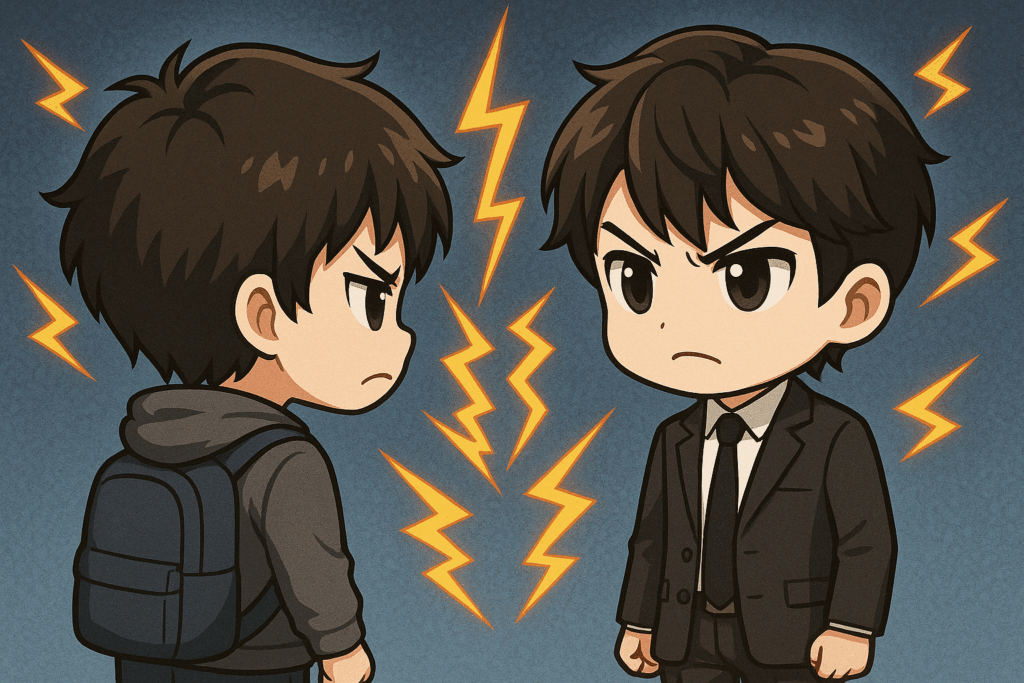
葬儀の打ち合わせでも、「創価学会です」と言われたら、間違っても「日蓮正宗と同じですか?」とは聞けないくらい、両者は“水と油”です。一見、同じ「日蓮系」と思われがちなこの2つの団体ですが、実は深い確執と宗教的対立があります。今回はその背景と、葬儀業界から見た“実情”を掘り下げていきます。
① 創価学会と日蓮正宗の関係とは?
創価学会は1930年、牧口常三郎と戸田城聖によって設立された団体で、当初は「価値創造教育」を掲げる在家中心の教育運動として始まりました。宗教団体というよりも、「人間の幸福とは何か」「どう生きるか」といった哲学的・教育的アプローチに重きを置いていたのです。
しかし第二次世界大戦後、信仰の柱をより明確に打ち出す必要があり、学会は日蓮正宗という宗派に帰依することとなります。この帰依により、創価学会は日蓮正宗の在家信者団体としての立ち位置を明確にし、宗教的活動にも一層力を入れていくようになります。1951年に戸田城聖が会長に就任すると、組織の再編成とともに布教活動が本格化し、日本全国にその存在を広げていきました。
このころから創価学会と日蓮正宗は、いわば「車の両輪」のような関係に。日蓮正宗が“教義の権威”を担い、創価学会が“布教と組織運営”を担うという、僧俗一体の構図が成り立っていたのです。創価学会は日蓮正宗の信仰を在家に広める手足として機能し、日蓮正宗はその精神的支柱であり続けました。
豆知識:信者数と影響力の逆転現象
創価学会は、特に1960年代以降の池田大作体制になってから、破竹の勢いで信者を増やし続けました。街頭での折伏(しゃくぶく=積極的な布教活動)や、文化イベント、青年部の活発な活動によって、信者数は国内で800万人超、全世界で1200万人以上に達したとも言われています。その拡大の背景には、家庭訪問による地道な布教活動や、地元のコミュニティを巻き込んだ集会など、きめ細やかな地域戦略がありました。
一方、日蓮正宗本体の信者数は数十万人規模とされており、布教力・資金力・組織力では、完全に創価学会が主導権を握る構造になっていきました。これは、宗門側にとっては大きなジレンマでした。自分たちが教義の中心であるはずなのに、実質的な“主役”は創価学会――そんな構図が次第に、両者の溝を深めていくことになります。
このような力関係の変化が、のちに起こる“破門劇”の火種となったことは否定できません。教義上の対立というよりは、むしろ「誰が主導するのか」「誰が信者を支配するのか」という組織的主導権争いが根底にあったとも言えるのです。

② 1991年の“破門”──対立の決定的な引き金
1991年、日蓮正宗は創価学会を正式に破門します。この決定は、池田大作氏による教義解釈や、組織の自立路線に対する宗門の反発が背景にありました。宗門側は「教義逸脱」や「僧俗の秩序破壊」を問題視し、創価学会は「時代に合った宗教運動を続けるべき」と主張。
この対立の中には、教義や信仰形式の違い以上に、権力構造の軋轢が色濃く表れていました。池田氏が率いる創価学会の急成長に対し、日蓮正宗側はその影響力の強さを危惧し、コントロールを取り戻そうとしたとも言われています。
これにより、創価学会は日蓮正宗からの独立を余儀なくされ、独自の路線で活動を続けていくこととなります。創価学会はその後、友人葬や学会独自の儀式・祭礼を確立し、在家中心の“生活に根ざした信仰”として定着させていきました。一方、日蓮正宗は「唯一正しい信仰を守る存在」として、創価学会を批判する立場を強めていきました。
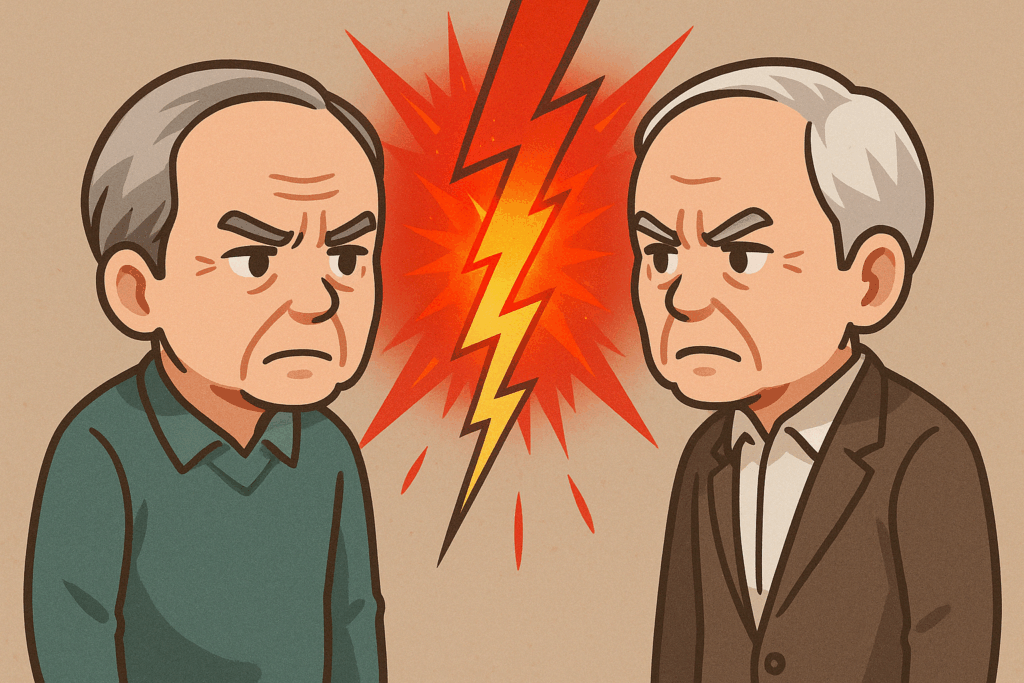
③ 葬儀スタイルにも“決定的な違い”
| 比較項目 | 創価学会(友人葬) | 日蓮正宗(宗門葬) |
|---|---|---|
| ⭕️ 導師 | 学会員(在家) | 僧侶(宗門所属) |
| ⭕️ 読経 | 在家による唱題 | 正式な読経と作法 |
| ⭕️ 会場設営 | 学会員が主導 | 僧侶との連携必須 |
| ⭕️ 経費 | 比較的安価 | 僧侶へのお布施が必要な場合も |
創価学会の「友人葬」は、僧侶を呼ばずに学会員自身が導師となって営む葬儀スタイルであり、簡素ながらも心を込めた葬送儀礼が行われます。一方、日蓮正宗は僧侶による読経や儀式を重んじ、伝統的な宗教作法に則って進行します。
「友人葬でお願いします」と言われた時に、うっかり僧侶の手配をしてしまえば、トラブルになる可能性大。宗派の違いを理解せずに準備を進めると、信者側から強く抗議されるケースもあります。特に、親族間で創価学会と日蓮正宗に分かれている家庭では、形式の違いが大きな対立を生むことも。
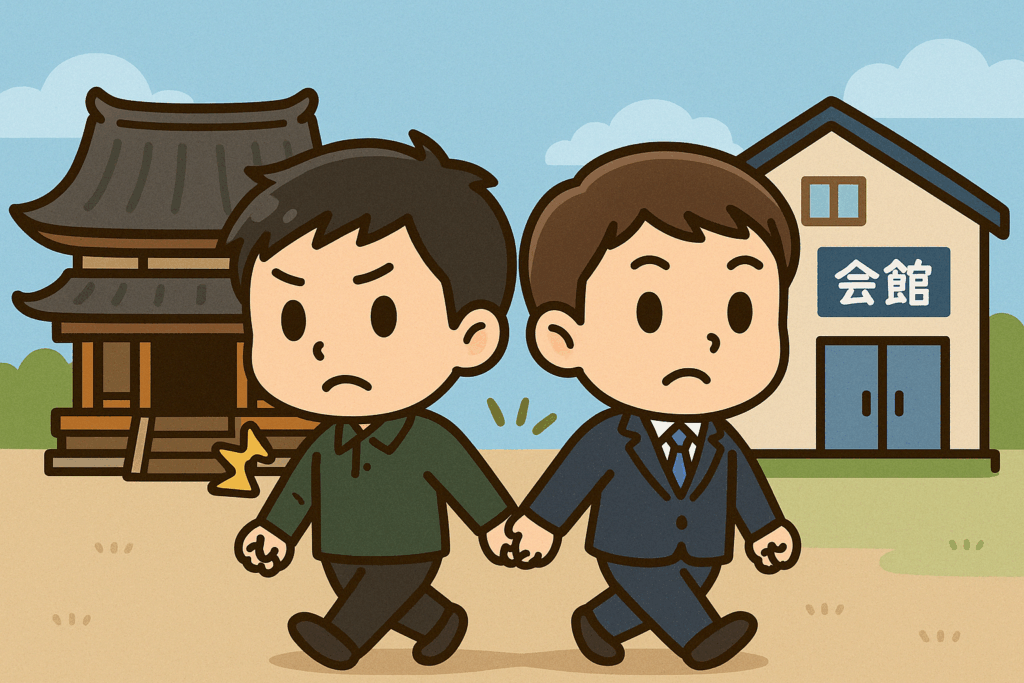
④ 現在のバチバチ具合と“見えない壁”
現在でも、創価学会と日蓮正宗の信者同士は互いに距離を置き、お互いの教義や活動を否定し合うことがあります。特に地方では、両方の信者が親族内に混在しているケースもあり、「どちらの形式で葬儀を行うか」が大きなトラブルに発展することも。
また、寺院や会館での活動制限、資料配布の禁止、相互乗り入れ不可など、組織的な断絶も続いており、「日蓮系だから仲がいい」という認識はまったく通用しない状況です。両者の関係は単なる「意見の違い」ではなく、「信仰の正しさ」を巡る根深い対立なのです。
さらに現場では、僧侶に読経を依頼するか否か、香典の表書きの書き方、参列者への説明内容など、細かな対応一つひとつに緊張感が伴う場合もあります。信仰的背景が異なることで、ちょっとした行き違いが大きな不信につながることもあり、関係者には高度な配慮が求められます。

⑤ 葬儀屋として気をつけるべきこと
- 宗派の確認は丁寧に。学会か宗門か、表現にも注意すること。
- 友人葬=無宗教ではない。創価学会独自の宗教形式である。
- 僧侶手配は慎重に。勝手に依頼すると信頼を損なう。
- 親族間の信仰バランスに配慮を。中立的な立ち回りが大切。
- 事前に教義や葬儀形式の違いを理解しておくと安心。
- 信者本人や家族と信頼関係を築くことがトラブル回避の鍵。
⑥ まとめ:同じ「日蓮系」でもまったくの別物!
📝 創価学会と日蓮正宗は、表面的には似ていても中身はまったく異なります。葬儀の現場においても、宗教的立場の違いを理解していないと、思わぬトラブルの火種になります。
📌 だからこそ、葬儀業界に携わる者として、宗教知識は“現場力”のひとつ。形式や言葉遣い、導師の有無といった細かな違いにも敏感であることが、信頼につながるのです。信仰の違いを尊重しながら、それぞれにふさわしい対応を行うことで、遺族の満足と安心を導くことができます。
おすすめブログ!!
2、🔆顕正会とは?道端での勧誘に注意。教義や被害例から考える“宗教との距離感”
3、☺️エンディングノートと遺書の違いを徹底比較!終活と相続のために知っておくべき書き方と活用法