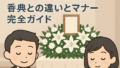はじめに|なぜ「夏」は孤独死が増えるのか?
毎年夏になると、独り暮らしの高齢者が室内で熱中症により亡くなるというニュースを目にします。特に後期高齢者(75歳以上)になると、体温調節機能が低下し、暑さを自覚しにくくなります。加えて、エアコンの使用を控える習慣や、誰とも連絡を取らない日が続くことで、体調の異変が誰にも気づかれないまま亡くなってしまうケースが少なくありません。
では、そうした悲劇を防ぐために、家族は何ができるのでしょうか? お金をかけたくないからといって、何もしないままでいる必要はありません。
本記事では「お金をかけない方法」も含め、後期高齢者の孤独死を防ぐために家族ができることをご紹介します。
家族ができる“見守り”の基本とは?
お金をかけずにできること
- 毎日同じ時間に連絡を取る習慣をつける
- できるだけ同じ時間帯に連絡を入れることで、生活リズムの確認にもなります。朝の「おはようLINE」や、夕方の「元気?電話」など、短時間でも継続が大事です。
- スタンプや短文でも構いません。高齢者にスマホが使えなくても、ガラケーや固定電話でもOKです。
- 家族間で安否確認ルールを作る
- 離れて暮らす家族や親戚が複数いる場合は、「曜日ごとに担当を決める」「連絡の記録をLINEグループに残す」などのルールを作ると、見守りの抜け漏れを防げます。
- 見守りの状況をExcelやGoogleスプレッドシートで共有している家族もいます。
- 近所の人と連携する
- 民生委員、町内会長、隣の住人などと、あらかじめ「連絡先の交換」「郵便受けや電気が何日も動かない時は知らせてほしい」などのお願いをしておくと安心です。
- 最近では「地域見守りボランティア」のような取り組みも多く、声かけ活動をしている地域もあります。
- 地域包括支援センターに相談する
- 全国すべての市区町村に設置されている、高齢者向けの総合窓口です。介護保険だけでなく、生活支援や見守り、地域との連携などを無料でサポートしてくれます。
- 一度相談すれば、継続的な支援が受けられるケースもあります。
地域の公的支援サービスを活用しよう
自治体の「見守り登録」
- 多くの自治体で、「一人暮らし高齢者台帳」や「緊急連絡先登録制度」などがあります。
- 登録しておくことで、異常が起きた際に地域の支援者(民生委員・消防・警察)がすぐに対応できる体制が整います。
- 市町村によっては「訪問見守り」や「週1回の電話確認」を行っているケースも。
緊急通報装置の貸出
- 自治体によっては、ペンダント型の通報ボタンや、固定電話型の装置を無料または低額で貸し出しています。
- 機器にはセンサーが付いており、「長時間動きがない」「トイレに行っていない」などの異常を自動検知するものもあります。
- 通報があると警備会社や消防へ自動連絡され、場合によっては家族にも通知されます。
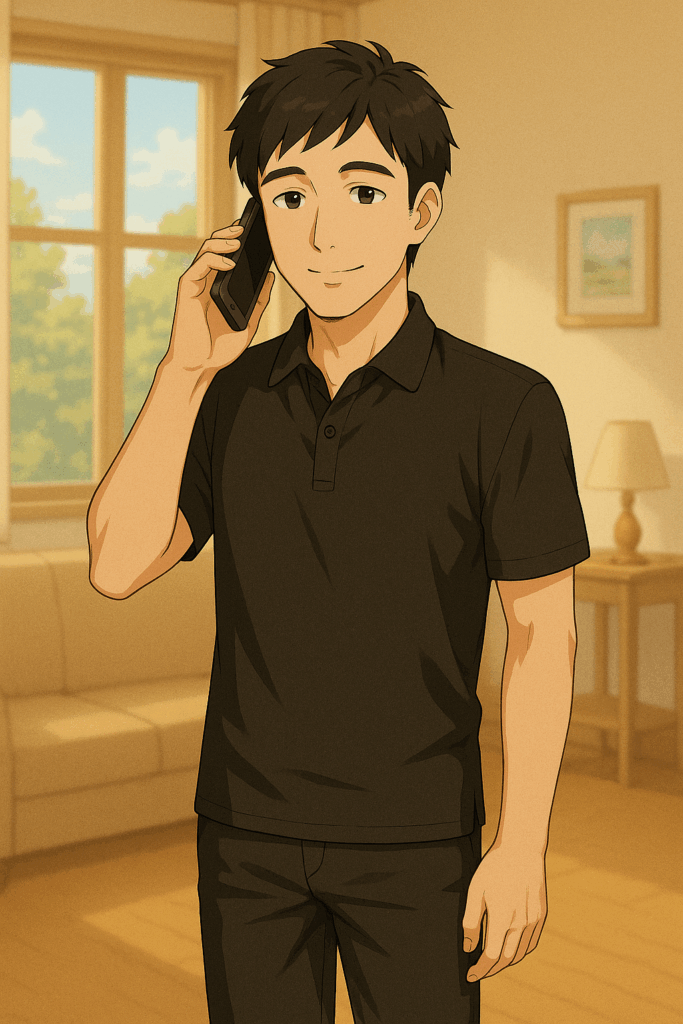
「ちょっとだけお金をかけて安心」を得る方法
郵便局の「みまもり訪問サービス」
- 日本郵便が提供している有料サービスで、郵便局員が月1〜4回、高齢者宅を訪問します。
- 会話内容や体調の様子、生活上の変化などをチェックし、報告書を家族へ送付。
- 直接訪問するので、電話よりも正確な様子がわかる安心感があります。
- 月額980円(税込)〜、地方でも対応しているケースが多いです。
電気・ガス・水道の見守りサービス
- 東京電力や東京ガスなどが展開するサービスで、電力・ガスの使用状況を遠隔で家族が確認できる仕組みです。
- 一定時間以上使用がない、または急激な変化があった場合に通知が届きます。
- 電気料金と一緒に利用料を支払えるため、手続きも簡単です。
- 高齢者のプライバシーに配慮しつつ、そっと見守れるのがメリットです。
配食サービスで“会話”もセットに
- 高齢者向け配食サービスの中には、食事の配達時に「ご本人と対面し、会話をして健康状態を確認する」ことを標準対応にしている業者があります。
- 例:
- ワタミの宅食:専属スタッフが直接手渡し。状況報告あり。
- 生活協同組合(生協):地域密着型で、配達員が家族のように接してくれることも。
- 地域の社会福祉法人やNPOが提供する配食+見守りサービス。
- 食事を通じて体調の変化や食欲の低下にも気づけるので、孤独死の兆候に早く気づくことができます。
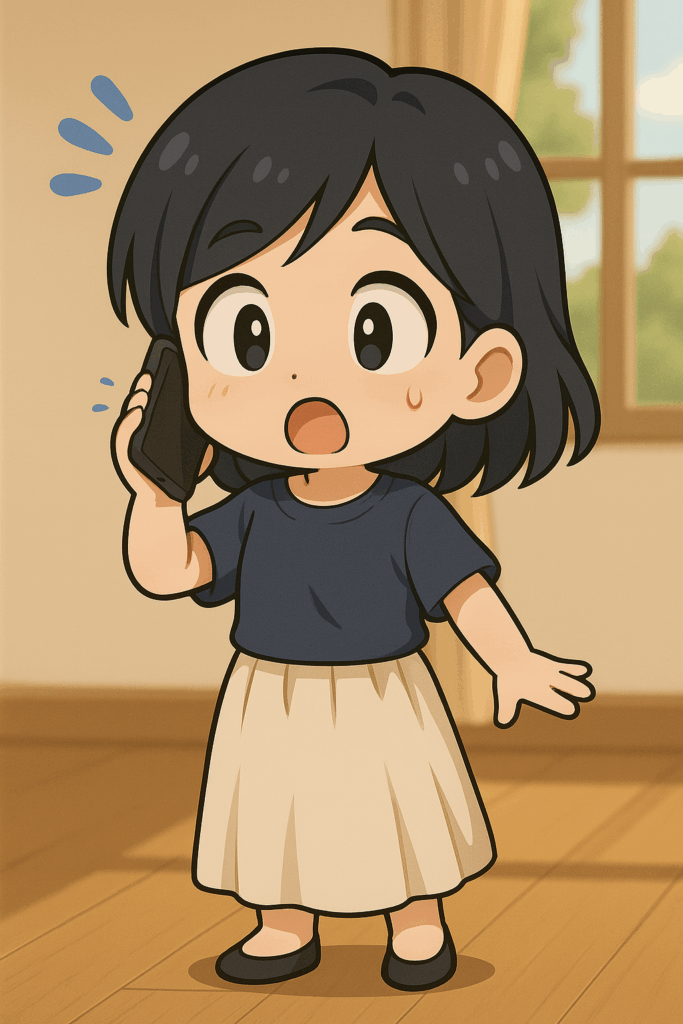
家族のちょっとした行動が孤独死を防ぐ
- エアコンの設置・使用を後押しする:もったいないという気持ちを和らげ、命を守ることを伝える。
- 「冷蔵庫の水ペットボトルを1日◯本飲んだよ!」の報告ルール:水分摂取の可視化。
- 「暑いから心配になって電話しちゃった」:自然な口実で日常的な声かけを。
- 電話やLINEの既読で毎日確認:視覚的な安否確認も効果的。
ペットが亡くなったらどうする?法律・火葬・供養まで完全ガイド【後悔しない見送り方】
まとめ|お金よりも“関心と仕組み”が命を救う
孤独死は「誰にも気づかれず亡くなること」が最大の悲劇です。大切なのは、「異変に気づける仕組み」を日常の中にどう作っておくかです。
見守りの方法は、決してお金がかかることばかりではありません。 「関心を持ち続けること」「小さな連携を積み重ねること」 それが、高齢者の命と安心につながります。
離れて暮らす家族だからこそ、今日からできる一歩を踏み出してみませんか?