第1部】宗教の役割とその変化|無宗教が増える現代社会を読み解くはじめに
宗教を信仰しない人が増えています。
日本では「無宗教」と答える人が7割を超え、世界的にも「どの宗教にも属さない(Nones)」と呼ばれる人々が年々増加しています。特に若い世代ほどその傾向が強いのが特徴です。
本記事は「宗教と現代社会」をテーマにした3部作の第1部です。
第1部では、宗教が果たしてきた役割とその変化について考えます。
続く第2部では「科学とインターネットがもたらした価値観の転換」、第3部では「小さなコミュニティが人を支える未来」について掘り下げていきます。
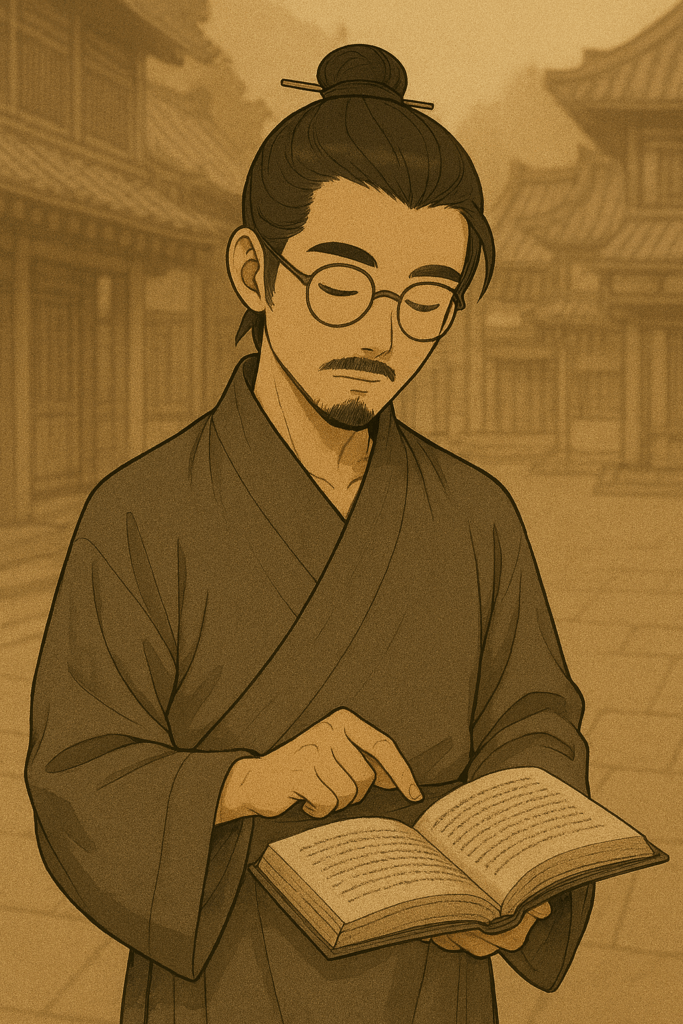
真如苑とは?巨大建築と100万人信者を集める“伸びる宗教”の実態!
宗教は「世界を理解するための言葉」だった
科学が未発達だった時代、人々は自然現象や死を説明する手段を持っていませんでした。
雷や地震は「神の怒り」、病や不幸は「祟り」や「宿命」とされ、宗教は理解できない出来事に意味を与え、不安を和らげる存在でした。
宗教は「共同体をまとめる仕組み」だった
宗教はまた、人々をひとつにまとめる力でもありました。
葬儀や法事、祭りや年中行事を通じて家族や地域社会が結びつき、そこから安心感や一体感が生まれました。
「同じ儀式を行う」ことが「私たちは同じ共同体に属している」という確認作業でもあり、宗教は社会秩序を守る装置でもあったのです。
創価学会・顕正会・統一教会…有名宗教団体のお布施・年間支出はいくら?
現代における宗教の姿
現代では「信仰心はない」と答える人が多い一方で、初詣やお盆、クリスマスなどの行事は根強く残っています。
つまり宗教は「信仰の対象」から「文化や習慣」として生活に受け継がれているのです。
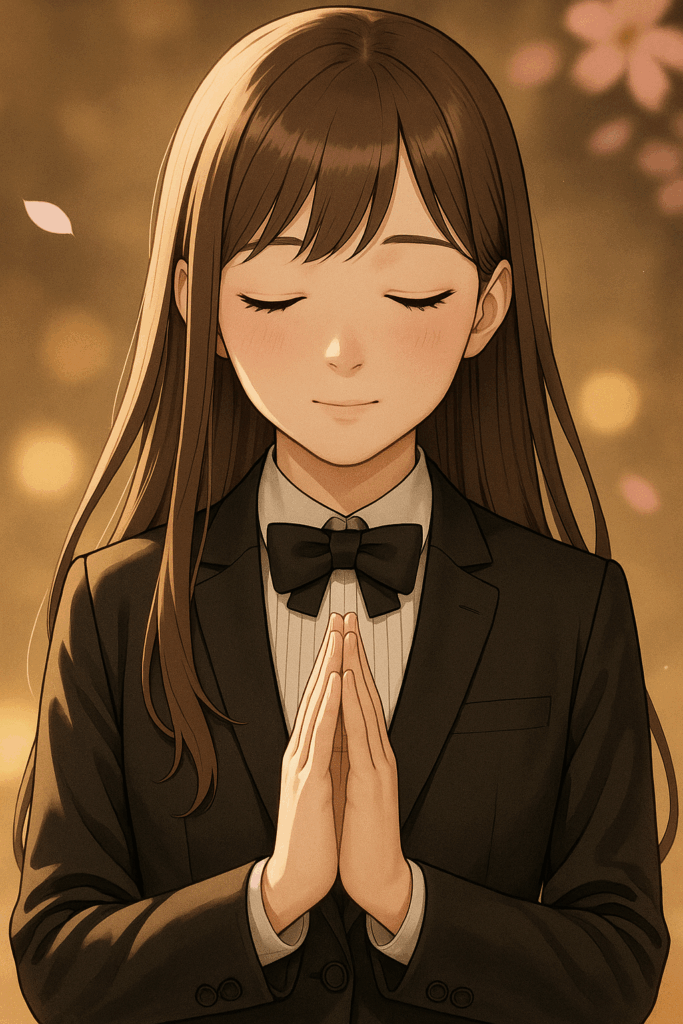
まとめ
宗教は、かつて人々に世界の意味を与え、共同体をつなぎとめる役割を担ってきました。
しかし現代において、その力は弱まり、信仰よりも文化や習慣としての意味が強くなっています。
次回(第2部)では、科学とインターネットが普及したことで、私たちの価値観やアイデンティティがどのように変化してきたのかを見ていきます。



