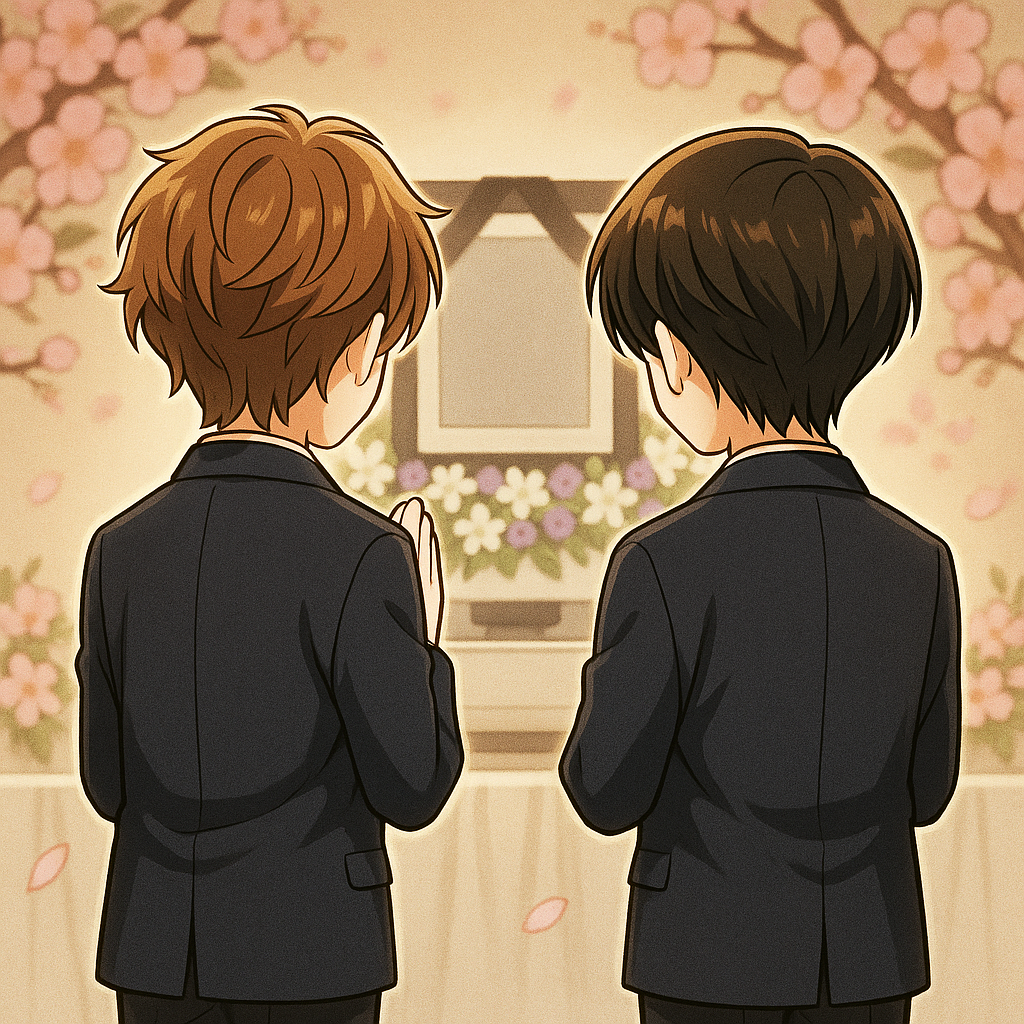お通夜や葬儀は、普段の生活ではあまり経験することのない行事です。そのため、いざ参列することになると「どれくらい時間がかかるの?」「何をすればいいの?」と不安になる人も多いと思います。 お通夜や葬儀は、人生でそんなにあることではありません。準備も実際できません。
この記事では、お通夜や葬儀に参加する際の所要時間や基本的な流れ、知っておくと安心なマナーを、高校生にもわかりやすく解説します。社会人になる前に知っておくと役立つ内容です!

はじめに
お通夜や葬儀に参列するとき、「どのくらい時間がかかるのだろう?」と不安に思う方は多いでしょう。仕事や学校の予定を調整したり、小さなお子さんを連れて参列したりする場合、所要時間の目安を知っておくことは大切です。
本記事では、お通夜・葬儀にかかる一般的な時間の目安を、儀式の流れやマナーとあわせて解説します。
お通夜にかかる時間の目安
お通夜の儀式部分(30分〜1時間程度)
お通夜のメインは読経と焼香です。参列者が多い場合でも、おおむね30分〜1時間程度で終わります。
焼香だけで帰るケースもある
会社関係者や近隣の方などは、焼香だけ済ませて退席することも珍しくありません。長居ができない方は、この形でもマナー違反にはなりません。
通夜振る舞いを含めると2〜3時間になることも
お通夜後に、遺族が参列者をもてなす「通夜振る舞い」があります。出席は任意ですが、ここに参加すると1時間ほど追加され、全体では2〜3時間かかる場合もあります。
葬儀・告別式にかかる時間
式典部分(1〜2時間)
葬儀・告別式では読経・焼香・弔辞などが行われ、一般的に1〜2時間程度です。
火葬や精進落としまで含めた全体の流れ(3〜5時間)
式典終了後は火葬場へ移動し、火葬(1〜2時間)・収骨を行います。さらに精進落としの会食を加えると、トータルで3〜5時間ほどになるケースが多いです。
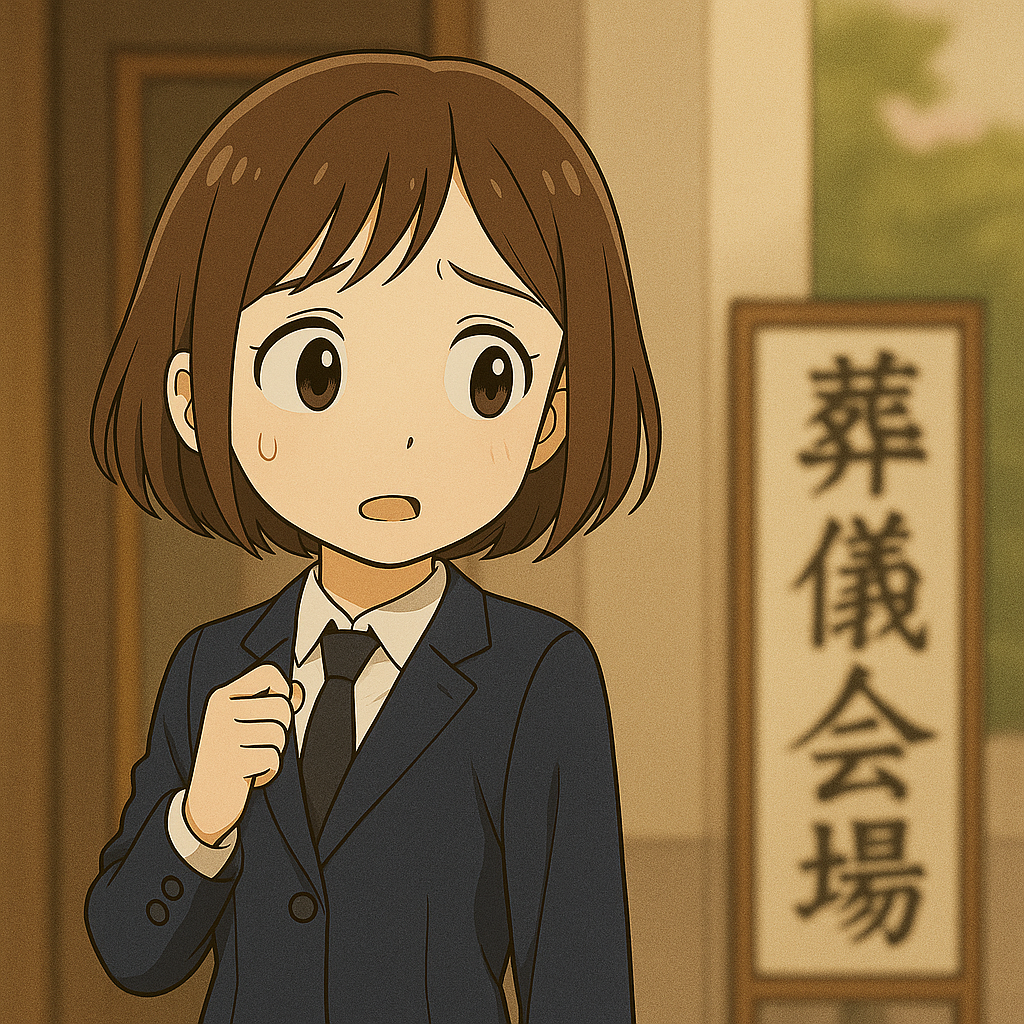
途中退出はしてもいい?マナーと注意点
参列者の途中退出
どうしても都合がつかない場合、焼香まで済ませて静かに退出すれば失礼にはなりません。ただし、式の進行を妨げないよう配慮が必要です。
遺族側の心構え
遺族としては、途中退出する方がいても気にせず感謝の気持ちを伝えることが大切です。
地域・葬儀形式による所要時間の違い
家族葬・一日葬の場合
家族葬は参列者が少ないため、儀式全体がコンパクトになり、所要時間も短め。一日葬では通夜を行わない分、半日程度で終わることが多いです。
無宗教葬・自由葬の場合
音楽や映像を使うケースでは時間が前後しますが、一般的に1〜2時間程度に収められます。
地域差もある
都市部では会葬者が少なく短時間で終わる傾向があり、地方では親戚・地域住民が多く参列するため、全体が長くなることもあります。
時間目安まとめ(一覧表)
| 儀式・行事 | 所要時間の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| お通夜(儀式部分) | 30分〜1時間 | 読経・焼香など |
| 通夜振る舞い | 約1時間 | 出席は任意 |
| 葬儀・告別式 | 1〜2時間 | 式典部分のみ |
| 火葬・収骨 | 1〜2時間 | 待機時間含む |
| 精進落とし | 約1時間 | 省略される場合も |
現代日本の葬儀におけるタブーとマナー|過去から未来へ繋ぐ作法の変遷とポイント
まとめ|お通夜・葬儀の時間は柔軟に変わる
お通夜や葬儀の所要時間は、儀式の形式・参列者数・地域性によって変わります。
- お通夜:30分〜1時間(+通夜振る舞いで2〜3時間)
- 葬儀・告別式:1〜2時間(+火葬・精進落としで最大5時間)
予定を立てる際は、この目安を参考にしつつ、案内状や葬儀社の説明を事前に確認することが安心につながります。