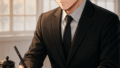「創価学会や幸福の科学なら聞いたことがあるけど、立正佼成会(りっしょうこうせいかい)って何?」
そう思う方も多いかもしれません。実際、テレビや新聞で名前を見る機会はほとんどないでしょう。しかしこの立正佼成会は、かつて日本最大級の新宗教と呼ばれ、現在でも200万人以上の信者を抱える巨大宗教団体です。
本記事では、そんな“静かなる大宗教”である立正佼成会の実態と、知られざる影響力についてご紹介します。

第1章:立正佼成会とは? 静かな大宗教の正体
立正佼成会は1938年に庭野日敬(にわの・にっきょう)氏によって創設されました。日蓮仏教をベースとしながらも、在家の一般信者が主役となって信仰活動を行う点が特徴です。
「一隅を照らす」という言葉を大切にし、それぞれが社会の中で自らを磨き、周囲を明るくすることを目指す姿勢は、創価学会や幸福の科学とは異なる穏やかな信仰スタイルです。
政治的活動や派手な勧誘を行わないため、目立たない存在ではありますが、その内実は極めて組織的で堅固です。
[PR]
創価学会・顕正会・統一教会…有名宗教団体のお布施・年間支出はいくら?
第2章:かつての影響力と社会貢献
1990年代には公称信者数600万人を超え、全国に支部を持つ一大宗教勢力として知られていました。
医療の分野では東京・杉並区に「佼成病院」を開設し、教育や出版、社会奉仕活動にも力を入れてきました。また、宗教者の国際ネットワーク構築にも貢献し、国連NGOにも登録されています。
特に戦後の混乱期から高度経済成長期にかけて、立正佼成会は多くの人々の「心の支え」となりました。金銭的な信仰よりも、行動と生活を重んじるスタイルが庶民に支持され、地方でもその名を知られる存在となったのです。

第3章:なぜ“目立たない”のか?
これほど大規模な宗教にもかかわらず、なぜ立正佼成会はあまり知られていないのでしょうか?
理由の一つは、その“控えめな姿勢”にあります。選挙での組織票、街宣車での布教、テレビCMといった「前に出る活動」はほとんどありません。
また、会員にも「信仰は押しつけない」「静かに実践する」という文化があり、信者であることを公言しない人も多くいます。
結果として、知名度こそ低いものの、各地のコミュニティや家庭の中に「ひっそりと根付いた」信仰とも言えるでしょう。
🪯創価学会 vs 日蓮正宗──破門から始まった“水と油”の関係とは?
第4章:現在の課題と若者の離脱
近年では信者数が減少し、若い世代の離脱も目立ちます。
特に、親の影響で信者になった“二世・三世信者”の中には、教義や組織運営に疑問を持ち、フェードアウトしていく人が少なくありません。
また、年功序列的な体質や、報告・奉仕のノルマなどが若年層にとっては「重たい」と感じられることも。
信仰自体よりも、「宗教団体としての古さ」が障壁となっている側面もあります。
とはいえ、信者の中には、佼成会を“信仰の居場所”として大切にしている人も多く、過度な改革や現代化に対して慎重な声も根強いようです。
[PR]
第5章:参列して感じた、佼成会の葬儀の特徴
筆者が実際に参列した立正佼成会の葬儀では、いくつか特徴的な点がありました。
まず導師(僧侶ではなく、信仰上のリーダー)が読経するスタイルで、法華経を中心にした経文が朗々と唱えられます。
焼香は一回が基本で、合掌は形式にとらわれず自然な形。香典袋の表書きも「御霊前」や「御香典」が一般的です。
葬儀中には短い法話(説教)もあり、故人の信仰や人柄について静かに語られる様子は、どこか柔らかく、温かな空気を感じさせました。
一般的な仏教葬儀と比べて、在家主体の“生活の中の信仰”がにじむ、立正佼成会らしい式でした。
第6章:今後の可能性と再評価の兆し
時代は変わり、「大きな教団に所属しない自由な信仰」が支持される中で、立正佼成会のような組織宗教は苦戦を強いられています。
しかし逆に言えば、「柔らかく、強制のない、穏やかな仏教団体」として、再評価される余地もあります。
スピリチュアルブームやマインドフルネス、仏教思想への関心が高まる中、佼成会の“法華経に基づく暮らし”は、新しい世代にも共感され得る要素を含んでいます。
問題は、それをどう伝えるか。組織的な広報やSNS活用、若者の対話の場づくりなど、“柔らかい宗教”としてのアップデートが鍵となるでしょう。

まとめ
創価でも幸福でもない。だけど、立正佼成会もまた、かつて人々の人生に寄り添ってきた「大宗教」の一つです。
派手ではないけれど、静かに生き方を支える信仰がそこにはありました。
これからの時代、目立つことよりも、共に生きる信仰のあり方が問われていくのかもしれません。