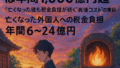日本の葬儀は、静かに、でも確実に大きく変わっています。
公費葬の増加、火葬場のキャパ不足、高齢社会による税金負担、葬儀社の離職率、そして外国人葬儀の増加──。
これらは別々の問題に見えますが、現場にいると 一本の線でつながっている のがよくわかります。
今回は、その「つながり」を含め、葬儀現場のリアルとこれからの日本社会についてまとめます。
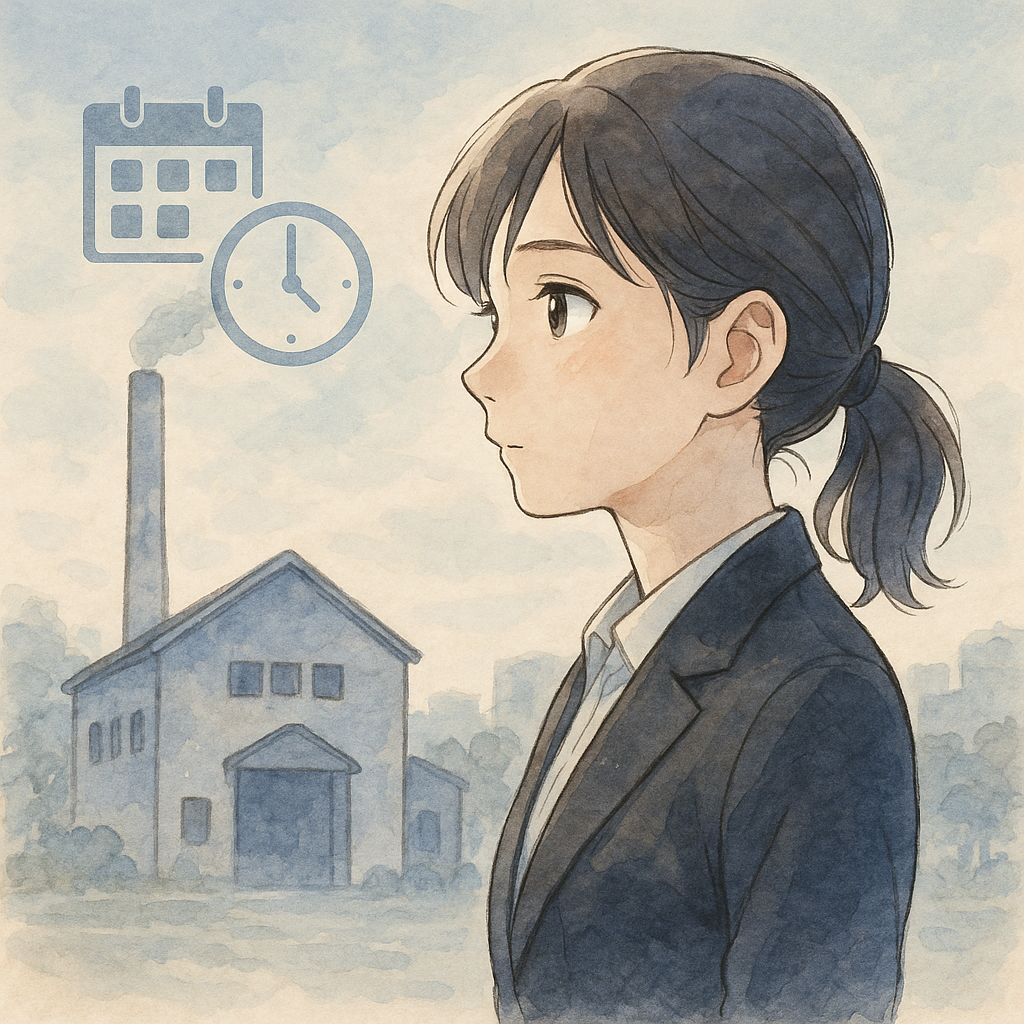
1. 公費葬の急増──“無縁”がこれほど多い時代はない
公費葬(生活保護葬)は、ここ数年で確実に増えています。
背景にあるのは、
- 単身高齢者の増加
- 親族との関係断絶
- 経済的困窮
など、社会の変化そのもの。
自治体の負担も増しており、
「亡くなる人の費用を社会全体が負担する」 ケースがこれまでにない速度で増えています。
現場では、
- 書類手続きに時間がかかる
- 引き取り手のないご遺体が増えている
- 親族が現れても「費用は出せない」というケースが多い
など、行政と葬儀社の双方に負荷がかかっています。
この流れは今後も止まりません。
働く世代が減り続ける中、負担しなければならない税金は確実に増えていきます。
2. 火葬場のキャパ不足──多死社会が生む“火葬待ち”
東京都・神奈川・埼玉・大阪などの都市部では、火葬の予約が取れない状態がすでに日常化しています。
繁忙期は「5〜10日待ち」も珍しくなく、葬儀の日程が組めないこともあります。
なぜこんな問題が起きるのか。
理由ははっきりしていて、
“火葬場を新しく作れない” からです。
住民の反対、土地の問題、行政の遅れ。
これらが重なり、都市部では火葬場が慢性的に不足しています。
現場では、
- 冷凍保管が増えている
- 火葬式(直葬)の依頼が増加
- 遺族の日程調整が大変
という現実が起きています。
2025年〜2040年。
団塊世代が高齢期を迎えるこの時期は、過去最大級の“多死社会”。
火葬場不足はさらに深刻になると見られています。
おすすめブログ 🟤「エタ・非人と葬儀――知られざる差別の歴史と死の送り方」
3. 高齢社会が生む税金負担──“死のコスト”は確実に上がる
日本全体で見ても、
医療・介護・公費葬──これらはすべて税金で支えられています。
死亡者数が増えるということは、
- 最後の医療費
- 介護費
- 公費葬
- 火葬場運営費
などの公的負担が増えるということ。
そしてその負担は、
40代〜60代の現役世代に重くのしかかります。
葬儀は「個人の問題」と思われがちですが、
実は“社会インフラ”であり、みんなで支えているサービスでもあります。
今後、公費葬の増加・火葬場老朽化・人口構造の崩れが重なり、
「死のインフラ」に関わる税金は確実に増えると考えられます。
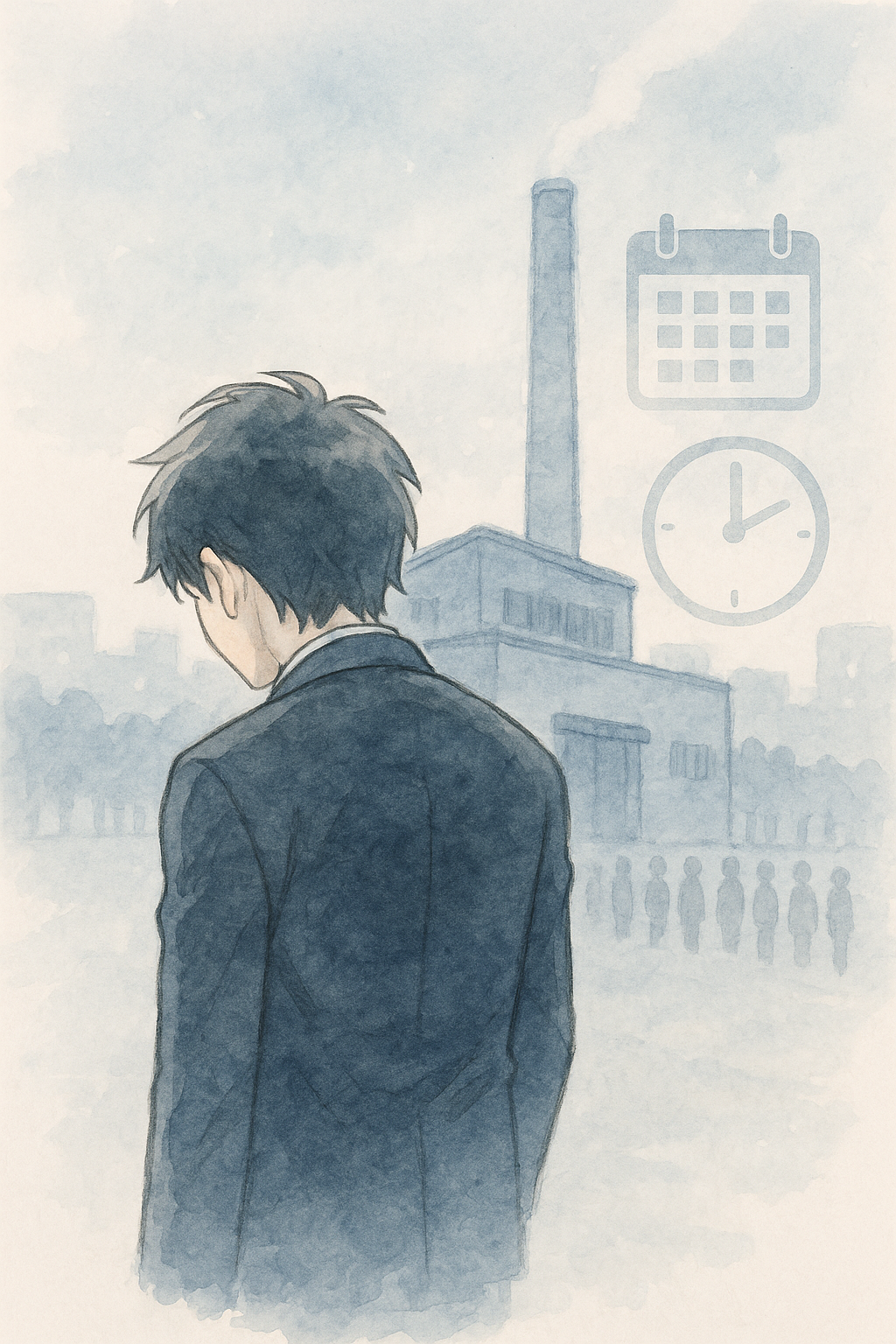
4. 葬儀社の離職率と人材不足──現場は静かに崩れ始めている
小規模葬・火葬式・家族葬が主流になり、葬儀単価は年々下がっています。
売上が減る一方で、深夜搬送・待機・書類業務などの負担は増えるばかり。
このアンバランスさが、
葬儀社の離職率の高さに直結しています。
現場では、
- 深夜帯の搬送で睡眠時間が削られる
- 待機時間が長いのに給料は上がらない
- 経験豊富な人ほど先に辞めていく
という状況が広がっています。
結果として、
葬儀の質が下がるリスク が確実に高まっています。
葬儀は本来、人の死と向き合う繊細な仕事。
人材循環が崩れると、その影響は遺族に返ってきます。
5. 外国人死亡が増える中、現場は“新しい対応”を迫られている
今の葬儀現場で確実に増えているのが、外国人の葬儀対応です。
技能実習生、留学生、外国人労働者──
日本で暮らす外国籍の方が急増しているため、葬儀も増えています。
しかし、外国人の葬儀は手続きが複雑です。
- 親族が海外で連絡がつかない
- 領事館・大使館とのやり取り
- パスポート・在留カード・火葬許可など
- イスラム教など、火葬禁止の宗教への対応
- 言語の壁
このあたりは、経験者でないと絶対に書けない領域です。
今後さらに外国人が増える日本では、
この問題は確実に“社会問題”になります。
おすすめブログ!! 「外国人に使われる税金は年間1,000億円超──そして“亡くなった後”にも税金が使われているという事実」
6. 5つの問題は、すべてつながっている
ここがこの記事で最も大事な視点です。
- 公費葬が増える
→ 税金負担が増え、行政は火葬場新設に予算を回せない
→ 火葬場不足が深刻化
→ 葬儀は簡略化し、葬儀社の売上が減る
→ 葬儀社の離職が進む
→ 外国人対応の質が下がる
→ 無縁・孤独死が増え、公費葬がさらに増える(最初に戻る)
まさに 循環構造 になっています。
個別の問題ではなく、
「日本社会の構造としてつながっている」という視点が必要です。
7. これからの日本の葬儀はどこへ向かうのか
現場にいると、これからの傾向が明確に見えてきます。
- 直葬・火葬式がさらに増える
- 公費葬が一般化し、二極化が進む
- 外国人葬儀が日常化する
- 火葬は“予約制社会”になる
- 遺族ケアよりも“事務処理能力”が重視される
- 葬儀社の分業化が進む(搬送・式典・書類の分離)
葬儀は“静かに変化していく分野”ですが、
今、間違いなく大きな転換点にいます。

まとめ:日本の葬儀は「社会インフラ」として見直されるべき
葬儀と言うと「家庭の問題」と考えられがちですが、
本当は社会全体で支える“公共サービス”でもあります。
- 高齢化
- 公費葬
- 税金負担
- 火葬場不足
- 外国人増加
- 葬儀社の離職
これらが絡み合い、日本の葬儀は見えないところで大きく変わっています。
あなたの体験とともに、
この現実をもっと多くの人に知ってもらえることには大きな意味があります。