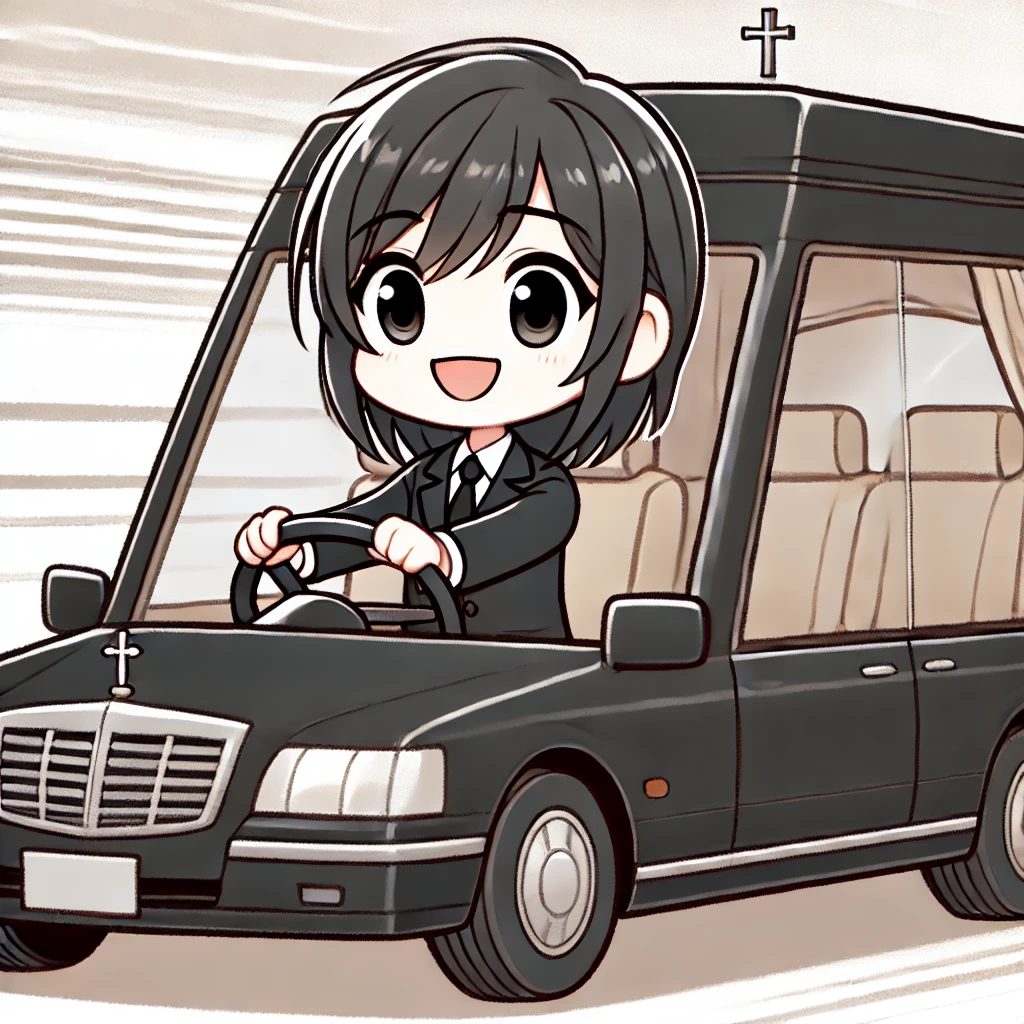近年、特に都市部では「運転しない人」が増えている傾向があります。免許は持っているものの実際には運転しない、または運転が苦手という人が増えており、その影響で運転できる人の価値が高まっています。
その中でも、意外と知られていないのが葬儀業界における運転スキルの需要の高さです。葬儀業界では、故人の搬送や遺族の送迎をはじめ、多くの場面で車の運転が必要になります。本記事では、「なぜ葬儀業界で運転できる人が求められるのか?」という視点から、業界の現状と仕事の詳細、そして運転スキルを活かした働き方について詳しく解説していきます。
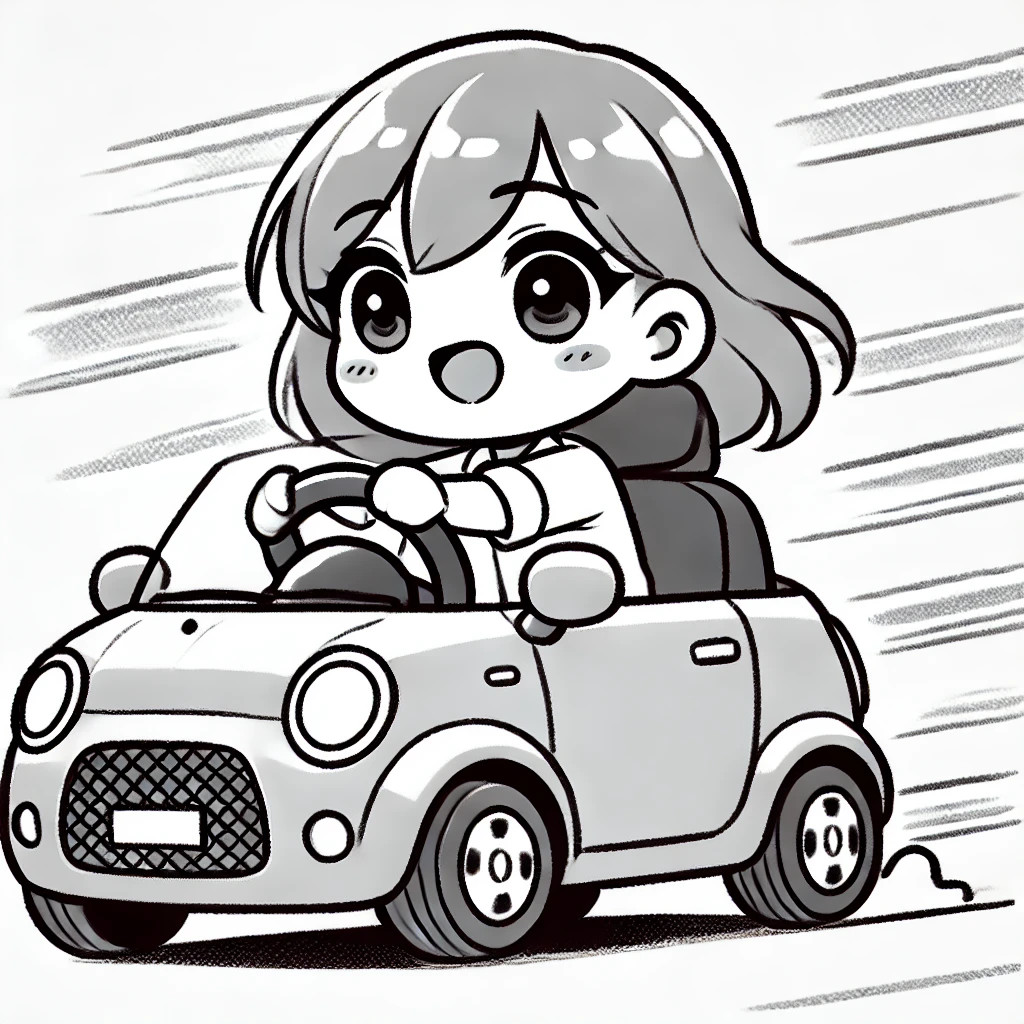
1. 免許はあるが運転しない人が増えている理由
近年、「運転しない人」が増えている背景には、いくつかの要因が挙げられます。
- 都市部では公共交通機関が充実しているため、日常生活で車を使う機会が少ない。
- 運転に対する不安やストレス(交通量の多さ、駐車の難しさ、事故リスクなど)。
- カーシェアやタクシーアプリの普及により、必要なときだけ車を利用できるようになった。
- 車の維持費が高い(駐車場代、保険、税金、ガソリン代など)。
- ペーパードライバーが増加しており、運転技術に自信がない人が多くなっている。
- 職場やライフスタイルの変化によって、そもそも車を必要としない生活スタイルが広まっている。
- 都市部では駐車スペースが限られているため、車を所有しても使いづらい。
さらに、交通事故への懸念も運転離れを加速させています。特に高齢者や若年層の中には、「自信がないから運転しない」と考える人も増えており、免許は取得したものの、ほとんどハンドルを握ったことがないという人も少なくありません。
このような背景から、特に都市部では「運転しない」または「できない」という人が増えています。その一方で、運転できる人材が必要とされる業界では、人手不足が深刻になりつつあります。物流業界やタクシー業界も同様ですが、葬儀業界もその一つであり、運転できる人の確保が急務となっています。

2. なぜ葬儀業界で「運転できる人」が求められるのか?
2-1. 葬儀業界は移動が多い
葬儀業界は、「移動」が多い業界です。業務の中で車を使う場面が多く、運転できる人が欠かせません。
- 故人を病院や自宅から安置場所へ搬送:病院や介護施設、自宅など、故人の安置先までの搬送は、葬儀社の重要な役割の一つです。
- 葬儀会場から火葬場へ霊柩車で移動:火葬場の場所によっては長距離の移動が必要になることもあります。
- 遺族や僧侶、参列者の送迎業務:高齢の参列者も多く、特に地方では送迎車が必要になる場面が多いです。
- 斎場や火葬場へ必要な備品の運搬:祭壇やお供え物などの物資を運ぶためにも車が必要です。
- 都市部では狭い道をスムーズに運転するスキルが求められる:駐車スペースの確保や、一方通行の多いエリアでの運転技術が必要です。
- 地方では長距離運転が発生する:火葬場が遠方にしかないケースも多く、運転時間が長くなることがあります。
このように、葬儀業界では車を使った業務が非常に多く、運転できる人がいないと業務が成立しないのです。
2-2. 葬儀業界の主な車両
葬儀業界で使用される車両は、主に以下の4種類があります。
1. 霊柩車(れいきゅうしゃ)
故人を葬儀会場や火葬場へ搬送する専用車両。一般的なワゴンタイプの霊柩車なら普通免許で運転できますが、大型車両を扱う場合は中型・大型免許が必要になることも。
- セダン型:高級感があり、一般的な葬儀で使用される。
- バン型:シンプルで利便性が高く、家族葬など小規模な葬儀で使われることが多い。
- リムジン型:格式の高い葬儀で使用されることがあり、見た目の美しさが重視される。
2. 搬送車
病院や自宅から故人を安置場所へ搬送する際に使用する車両。主にバンやワゴン車が多く、夜間の搬送業務が発生することもあります。
- 夜間・早朝の搬送が多い:急な依頼にも対応するため、柔軟な働き方が求められます。
- 運転技術が求められる:遺族が同乗することもあり、落ち着いた運転が必要です。
3. 送迎車(マイクロバス・ワゴン車)
遺族や僧侶、参列者を葬儀会場・火葬場へ送迎する車両。大規模な葬儀ではマイクロバスが使われることもあり、その場合は中型免許以上が必要になることがあります。
- 家族葬ではワゴン車が主流:少人数の移動に適しています。
- 大規模葬儀ではマイクロバスが必要:多数の参列者を安全に移動させるための手段です。
4. 葬儀社の業務用車両
葬儀の準備や備品の搬送に使われる車両もあります。小型トラックや軽ワゴンなどを利用し、花や供物を運ぶケースもあります。
2-3. タクシーやバス運転手との違い
タクシー運転手やバス運転手は、二種免許(普通二種・大型二種)が必要ですが、葬儀業界では基本的に普通免許があればOKなことが多いのが特徴です。
- タクシー業界:流し営業があるため、都内の道を細かく覚える必要がある。
- バス業界:固定ルートの運行が多く、大型免許が必須。
- 葬儀業界:固定ルートではないものの、事前に計画されたルートを走るため、都内の全道路を覚える必要はない。
また、タクシー業界のように「営業トーク」が求められるわけではなく、落ち着いた態度や配慮のある運転が求められるため、接客が苦手な人でも安心して働きやすい環境です。
さらに、葬儀業界の運転は長距離運転が発生することもあり、タクシーやバスとは違った運転スキルが求められる場面もあります。特に地方では、山間部の狭い道や高速道路の運転を求められることがあるため、適応力のあるドライバーが重宝されます。
2-4. 葬儀業界の運転手に求められるスキル
葬儀業界で運転業務を行うには、以下のスキルが求められます。
- 安全運転技術:故人や遺族を乗せるため、急ブレーキや乱暴な運転は厳禁。
- 地理の把握力:火葬場や葬儀場の所在地を把握し、スムーズに移動できること。
- 時間管理能力:葬儀のスケジュールに合わせ、時間通りに移動できること。
- 緊急時の対応力:渋滞や道路封鎖など、予期せぬ事態にも冷静に対応できること。
このように、葬儀業界での運転は単なる「移動手段」ではなく、故人と遺族に寄り添う大切な役割を果たします。そのため、運転技術だけでなく、心配りや配慮ができる人が求められます。
葬儀業界での運転業務は、タクシーやバス業界とは異なり、より静かで慎重な対応が求められる仕事です。運転が好きで、人の役に立ちたいと考える方にとって、非常にやりがいのある職業となるでしょう。

3. 葬儀業界で運転業務に就くメリット
3-1. 安定した業界で働ける
葬儀業界は、需要が安定している業界の一つです。高齢化社会が進む中、今後も葬儀のニーズがなくなることはないため、長期的に働ける環境が整っています。
3-2. 特別な資格がなくても始めやすい
タクシー業界とは異なり、普通免許だけで始められるのが葬儀業界の強み。中型・大型免許が必要な場合でも、会社負担で取得できる制度がある葬儀社もあります。
3-3. 夜間手当や特殊業務手当で収入アップ
葬儀業界では、夜間の搬送業務が発生することもあります。そのため、
- 夜間手当
- 特殊業務手当
- シフト手当
といった手当がつくことが多く、収入アップが期待できます。

4. まとめ:運転スキルを活かして新しいキャリアを!
「運転できる」というスキルは、多くの業界で必要とされていますが、特に葬儀業界ではその需要が高まっています。
✅ 普通免許があれば働ける(特別な資格は不要)
✅ 需要が安定している(景気の影響を受けにくい)
✅ 夜間手当などで収入アップも可能
✅ 接客が苦手でも安心して働ける環境
もしあなたが「運転するのは嫌いじゃないけど、今の仕事では活かせていない」と感じているなら、ぜひ葬儀業界の求人をチェックしてみてください。
運転スキルを活かして、安定したキャリアを築きたい方にとって、葬儀業界は大きな可能性を秘めたフィールドです。ぜひ、新たな一歩を踏み出してみませんか?
オススメ記事
1、【宗教別】葬儀費用の違いを徹底解説!仏式・神式・キリスト教・新宗教【相場まとめ】