近年、厚生労働省が公表する「都道府県別死亡率ランキング」で、東北地方の県が上位に並ぶことが注目を集めています。2022年のデータでも、秋田県・青森県・岩手県・山形県・福島県といった東北各県が上位にランクインし、さらには新潟県や島根県、高知県、鳥取県、茨城県などの地域が続く結果となりました。この傾向を見たとき、「なぜ東北の死亡率が高いのか?」「生活習慣や社会構造に何か特徴があるのか?」と疑問を持たれる方も多いことでしょう。
本記事では、東北地方を中心とした死亡率の高さの要因について、具体例を交えながら解説していきます。今後の地域社会や健康対策、そして個人のライフスタイルを考えるうえで、ぜひ参考にしてみてください。

1. 東北地方の死亡率が高い背景とは?
厚生労働省が公表する都道府県別死亡率ランキングでは、人口1000人あたりの死亡数を都道府県別に比較しています。そこで上位に名を連ねる県の多くが東北地方や日本海側の地域であることが多く、2022年のデータでもその傾向は変わりませんでした。東北地方は「高齢化の進行」や「気候条件」「生活習慣」など、さまざまな要因が重なっていると考えられます。まずは、その全体像を押さえておきましょう。
2. 高齢化率の高さと若年層の流出
2-1. 高齢者人口の割合が全国平均より高い
東北地方の県は、全国と比較しても高齢化率(65歳以上が人口に占める割合)が特に高いことで知られています。たとえば、秋田県は毎年のように高齢化率の全国1位を記録し、40%前後に達する年もあるほどです。高齢化率が高いということは、当然ながら死亡率の上昇要因となり得ます。高齢者ほど病気や体力低下による死亡リスクが高まるためです。
2-2. 若年層の首都圏流出
もう一つ見逃せないのが、若者の流出です。大学進学や就職を機に、首都圏や大都市圏に移り住む若者が多いのは全国的な傾向ですが、特に東北地方ではその流出幅が大きいとされています。働き口の少なさや都市部と比べた所得格差などから、若年層が地域を離れてしまうケースが目立ちます。若年人口が減少すれば、その地域に残るのは高齢者の割合が相対的に増えた状態となり、結果として死亡率が高くなるのです。

3. 気候条件と死亡率の関係
3-1. 寒冷地特有のリスク:「ヒートショック」
東北地方の冬は長く、積雪や厳しい寒さが特徴的です。こうした寒冷地特有の気候が、死亡率とどのように関係しているのでしょうか。代表的な例として挙げられるのが「ヒートショック」です。ヒートショックとは、冬場に暖房の効いた部屋と、寒い浴室やトイレなどを行き来する際の急激な温度変化によって、血圧が大きく変動し、心筋梗塞や脳卒中を引き起こすリスクが高まる現象を指します。東北地方のように寒さが厳しい地域では、ヒートショックによる死亡リスクが上昇しやすいのです。
3-2. 豪雪による事故や運動不足
東北地方では、雪の多い地域で屋根の雪下ろし中に転落・落雪事故が起きることも珍しくありません。こうした豪雪ならではの事故死が死亡率を押し上げる一因となることがあります。また、冬場の屋外活動が制限されるため、慢性的な運動不足から生活習慣病が進行しやすいという指摘もあります。気候的要因による健康リスクは、特に高齢者にとって深刻な問題となりがちです。
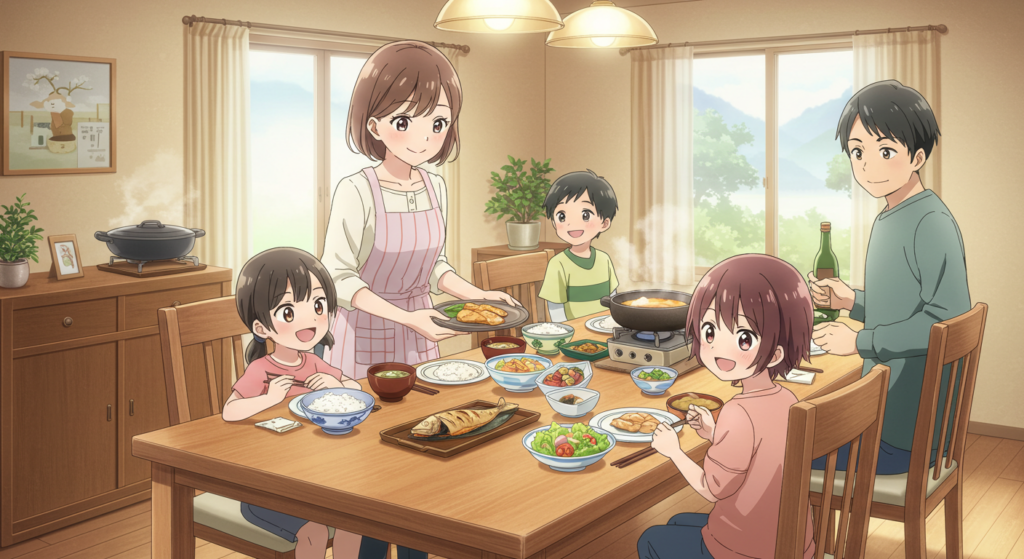
4. 生活習慣と食文化:塩分摂取量や喫煙率の影響
4-1. 東北地方の塩分摂取量が多い理由
日本海側や寒冷地では、古くから冬に備えた保存食文化が発達してきました。塩漬けの漬物や味噌を多用した郷土料理、塩辛い魚介類の加工品など、塩分量が多い食事が日常的に登場します。東北地方の一部地域では、全国平均と比較しても塩分摂取量が高い傾向があり、高血圧が多い原因の一つとされています。高血圧は脳卒中や心疾患、腎不全など、死亡リスクの高い病気を引き起こす大きな要因の一つであり、これが死亡率の高さにつながっている可能性は否定できません。
4-2. 喫煙率の高さ
厚生労働省の調査などから、青森県や秋田県は喫煙率が比較的高いことも知られています。喫煙はがんや心臓病、肺疾患など多岐にわたる疾患リスクを高め、死亡率の上昇に直結しやすい要因です。生活習慣の見直しが叫ばれて久しいものの、地域の慣習や嗜好などから脱却するのは容易ではありません。

5. 医療へのアクセスと地域格差
5-1. 病院数・診療所数の不足
都市部に比べ、東北地方を含む地方では病院数や診療所数が不足している地域も少なくありません。とりわけ、山間部や過疎地域では、高齢者が定期的に受診できる医療機関が近くにない場合もあります。医療サービスへのアクセスが悪いことは、病気の早期発見や早期治療の遅れにつながり、重症化や死亡リスクの上昇を招く一因となります。
5-2. 救急医療体制の整備不足
加えて、救急搬送に時間がかかったり、救急科を備える病院が少なかったりといった問題も存在します。特に脳卒中や心筋梗塞など、急性期の対応が必要な病気の場合、適切な治療を開始できるかどうかは生死を分ける重要なポイントです。こうした医療インフラの不足が、都市部と地方の死亡率格差を生む原因の一つと言われています。

6. 地域社会の課題と対策の現状
6-1. 高齢者の健康管理に注力する自治体
東北地方をはじめとして、地方自治体では地域包括ケアシステムの構築や、在宅医療・訪問看護サービスの充実化を図るなど、高齢者の健康管理に力を入れています。具体的には、地域の保健師やケアマネージャーが定期的に家庭を訪問し、生活習慣や服薬状況を確認したり、バランスの取れた食事指導やリハビリテーションを促したりといった取り組みが進められています。
6-2. 予防医療や検診の重要性
死亡率を下げるうえで欠かせないのが、予防医療や定期検診の受診率向上です。脳卒中や心臓病が発症する前に、血圧管理やコレステロール管理を徹底し、危険因子を早期に把握できれば、重大な疾患を防ぐことが期待できます。自治体によっては、住民検診や無料でのがん検診などを積極的に行っており、こうした取り組みを活用することが健康寿命の延伸につながります。
6-3. 生活習慣の改善を促す取り組み
高塩分食や喫煙など、地域の慣習として根付いている生活習慣を変えるのは簡単ではありません。しかし、近年は減塩食品の普及や「少しでも運動量を増やそう」といった啓発活動が進んでいるほか、自治体によっては「禁煙外来」への補助金制度やウォーキングイベントなどを開催し、住民の意識改革を後押ししています。

7. まとめ:東北地方の死亡率の高さをどう考えるか
2022年の都道府県別死亡率ランキングで、東北地方の県が上位に並んだ要因をまとめると、下記のようなポイントが挙げられます。
- 高齢化率の高さ
- 若年層が流出し、高齢者の割合が相対的に増加
- 寒冷な気候による健康リスク
- ヒートショックや豪雪による事故、運動不足
- 生活習慣や食文化
- 塩分摂取量の多さや喫煙率の高さが生活習慣病の原因に
- 医療体制へのアクセス問題
- 病院・診療所の不足や救急医療体制の不備
これらの要因は互いに関連しており、どれか一つを改善しただけでは死亡率の劇的な低下を期待することは難しいかもしれません。しかし、高齢者に優しいインフラづくりや、地域に根付く食文化を少しずつ見直す動き、医療アクセスを改善するための改革など、個人と自治体の両面からアプローチすることで、今後は状況が変わっていく可能性があります。
東北地方に限らず、日本社会全体が超高齢化に直面している現在、死亡率の高低を他人事のように捉えるのではなく、より健康寿命を延ばすための取り組みに注目していくことが重要です。高齢者だからこそ必要とされるケアや、生活習慣病予防のためのサポートは、どの地域にも共通する課題といえるでしょう。地域それぞれの特色を活かしながら、少しずつでも健康リスクを下げる方法を模索していくことが、将来的な日本の姿にとって大切な一歩となるはずです。

この記事のポイント
- 東北地方の死亡率が高い理由は、主に高齢化率の高さ・寒冷な気候・塩分摂取量の多い食文化・医療アクセス不足など。
- 若年層の流出によって高齢者割合がさらに増え、死亡率が上昇する構造がある。
- ヒートショックや豪雪事故といった寒冷地特有の健康リスクも見逃せない。
- 予防医療や生活習慣の改善、医療インフラの整備など、自治体や個人が協力して取り組むべき課題が多い。
東北の死亡率ランキング上位は、単なる「地域のイメージ」だけで終わる話ではなく、日本全体が抱える課題の縮図とも言えます。高齢者人口が増加していくなかで、どうやって健康寿命を延ばし、医療費を抑制しながら地域社会を活性化するか――。この難問を解くカギは、私たち一人ひとりの生活習慣や自治体の取り組みにかかっています。秋田や青森といった県のデータに注目することで、国内各地域が抱える問題点や今後の課題が見えてくるのではないでしょうか。ぜひ地域の健康対策や高齢者支援の現状を知り、自身の暮らしのなかでもできることから始めてみてください。
1、海洋散骨の総費用を徹底解説!家族同行や葬儀の有無で変わる具体的な金額とは?



