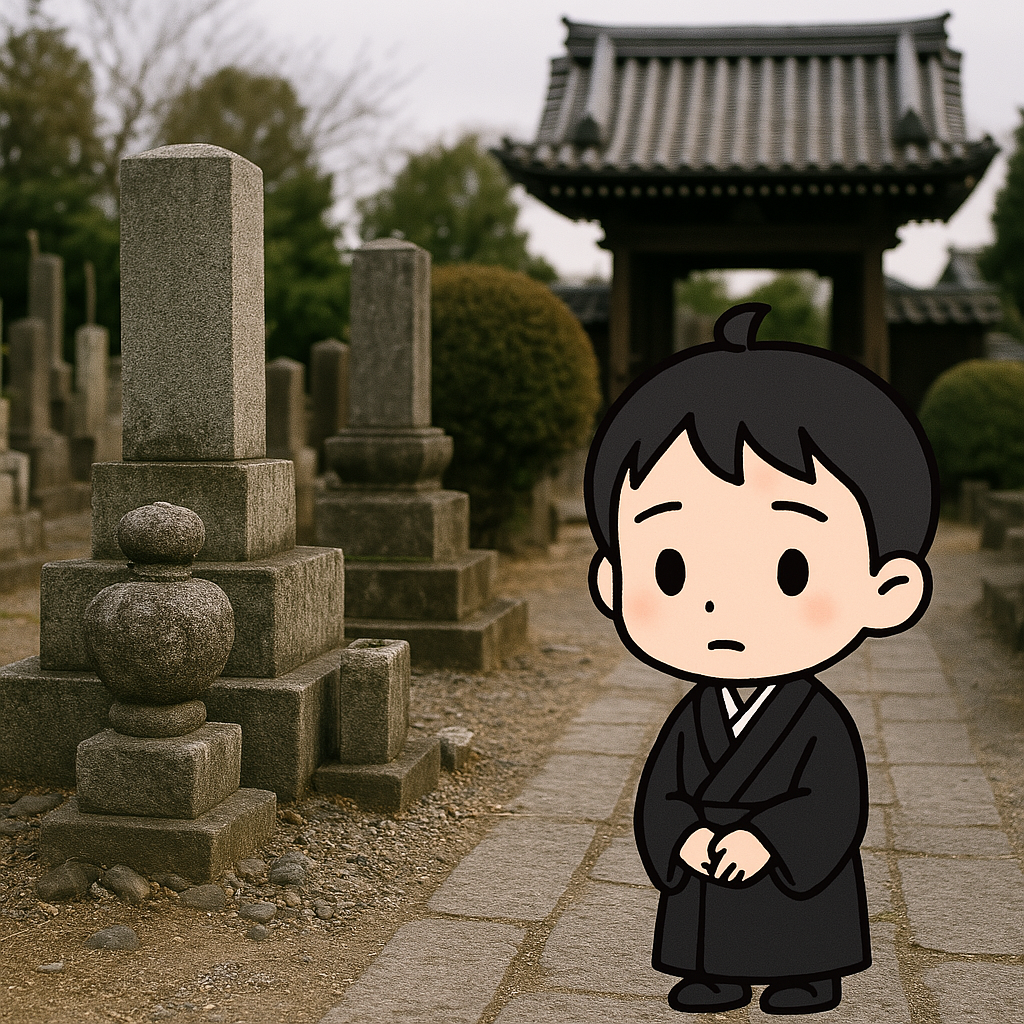
【はじめに】
日本の歴史において、「エタ」「非人」と呼ばれた被差別民の存在は、死や葬儀の文化と深く結びついてきました。現代に生きる私たちにとっては、過去のことのように思えるかもしれませんが、実はその名残や影響は、まだ社会の一部に色濃く残っていると言われています。特に「穢れ(けがれ)」とされた死や血にまつわる仕事を担ってきた彼らが、どのように葬儀に関わり、そしてどのように自らの死を見送られてきたのかは、あまり語られてきませんでした。本記事では、エタ・非人と呼ばれた人々の葬儀文化について、歴史的背景から現代への影響まで、なるべくわかりやすくまとめてみたいと思います。

【死と「穢れ」の思想】
日本には古来より、神道を中心に「死は穢れ」という考え方が存在しました。死者を葬る行為や血を見る行為は、神聖なものから遠ざけられる“忌むべき行為”とされていたのです。時代が下るにつれて仏教が普及し、葬儀の形態は変化しましたが、死を「穢れ」と捉える感覚自体は根強く残りました。そのため、死に直接関わる仕事や血に触れる仕事を担う人々は、一段低く見られ、差別される構造が生まれていきました。
[PR]
【エタ・非人とは何か】
江戸時代以前、日本には「士農工商」という身分制があったと説明されることがありますが、それは理想像であり、実際にはもっと複雑でした。その中でも「エタ(穢多)」「非人(ひにん)」と呼ばれた人々は、最下層の身分とみなされ、社会的に隔離されることが多かったのです。エタは主に皮革業や動物の屠殺、葬送に関わる役目を担い、非人は刑罰の執行補助や清掃、門付け芸能のような仕事を担っていました。彼らは特定の場所に集団で居住することが多く、そこを後の「被差別部落」と呼ぶようになります。

【エタ・非人と葬儀の関わり】
死や血に関わる職務が「穢れ」とされる中で、エタ・非人の人々は火葬・埋葬の場面でも重要な役割を果たしていました。例えば、刀剣の試し斬りに使われた死体を処理したり、死刑執行後の遺体を火葬・埋葬するなど、当時の社会が必要としながらも敬遠した仕事を引き受けていたのです。こうした行為は一般の人々から忌避されがちであったため、その担い手として押し付けられる形でエタや非人の身分が固定化されていったとも言えます。さらに、一部では「火葬や埋葬に携わる以上、彼らがいなくては葬儀が成り立たない」という矛盾も生まれ、差別しながらも依存するという構図ができあがりました。
【エタ・非人自身の葬儀】
では、エタ・非人と呼ばれた人々が自らの死を迎えたときは、どのように葬られていたのでしょうか。まず、一般の寺院や墓地に受け入れを拒否されることが多く、彼ら自身の集落内で葬儀を完結させるしかない地域もありました。江戸時代には仏教が庶民にも広がっていきましたが、被差別民は檀家として正式に受け入れられないケースも珍しくありません。そのため、独自の宗教行事や作法が形成される一方、周辺の寺社とも何とか関わりを持とうとする動きも見られました。
地域によっては「被差別部落」に専用の墓地が設けられ、そこに葬られることになりますが、その墓地はしばしば人里離れた場所に置かれ、集落の人々が静かに送り出す姿があったとされています。とはいえ、一部の土地では町や村の共同墓地の一角を使用していた例もあり、地域や時代によって状況はさまざまでした。
【明治以降の変化と残った差別】
明治政府が1871年に「解放令」を発布し、法的にはエタ・非人などの差別的身分は廃止されました。しかし、実際には新たな差別の形が生まれ、葬儀や墓地についても「部落の墓地」は受け入れがたいという社会的な偏見が色濃く残っていました。近代になると火葬場が整備されていきましたが、その周辺に被差別部落があることを理由に「この地域は穢れている」「あの墓地は部落だ」といった噂が絶えず、結婚や就職においても不利益を被る人々が後を絶ちませんでした。
また、寺院側でも、正式な檀家として迎えたくないという意識が続き、被差別部落出身の遺族が通常の葬儀プランを組みにくい事例も散見されました。昭和の時代になって同和対策事業が進められた結果、環境改善や法整備が進んだとはいえ、人々の根強い意識がすぐに変わるわけではなかったのです。

[PR]
【現代における影響と課題】
現代の日本では、表向きは身分差別がない社会になっています。しかし、部落差別を含むあらゆるマイノリティに対する差別意識が、SNSやインターネット上の風評などで再燃することもあります。葬儀についても、葬祭業に携わる方々から「被差別部落出身の人だと聞いて躊躇する客がいる」といった声が、まだ完全には消えていないと言われています。
かつてエタ・非人の担い手が担ってきた役割は、現代の葬儀社や自治体が果たすものとなりましたが、それまでに積み重なった差別の歴史やイメージは、簡単に拭い去れるものではありません。無自覚なまま「この火葬場がある地域は…」と噂したり、「あの墓地は古くからの部落だ」と言及することが、当事者を深く傷つけることになりかねないのです。
【命の終わりに差をつけない社会へ】
葬儀とは、本来ならば「命の尊厳」を最後まで見届け、旅立ちを祈る尊い行為です。にもかかわらず、過去の歴史の中で「穢れ」や「差別」と結びつき、それを引きずったまま現代に至っているのは、私たちが学び、改めるべき大きな課題といえます。
エタ・非人という呼び方や、そうした身分制自体は法的に廃止されたはずですが、先祖代々の土地や仕事の関係で、「あの家は部落だった」という偏見のまなざしを受ける人も存在します。死は誰にでも平等に訪れるものであり、「穢れ」として忌避されることでもなければ、そこに優劣の差があってはなりません。むしろ、私たちがこうして過去を知り、痛ましい歴史を学ぶことで、同じ過ちを繰り返さないようにすることが何より大切ではないでしょうか。

【おわりに】
ここまで見てきたように、エタ・非人と呼ばれた人々は、江戸時代などの身分制社会で厳しい差別を受けながらも、葬儀や死の処理といった生活に欠かせない役割を担ってきました。そして、自らの死に関しても、周囲から遠ざけられた場所で弔われたり、寺や墓地の利用を拒否されたりと、現代の価値観からは考えられないほどの不当な扱いを受けてきたのです。
それでも、私たちは今、法的には身分の区別がない社会に生きています。しかし、それは単に「解放令が出ました、はい終わり」という話ではなく、人々の意識や言葉づかい、習慣の一つひとつを見直していく努力が必要です。特に葬儀や墓地は、その人とその家族の最後の大切な時間を象徴するもの。そこに差別が入り込む余地を作ってはならないはずです。
エタ・非人の葬儀の歴史を振り返ることで、「死」や「穢れ」にまつわる偏見が、いかに多くの苦しみを生んできたかが見えてきます。その苦しみをくり返さないためにも、私たちは過去を学び、命の平等を尊重する社会を目指さなければなりません。そうしてはじめて、どんな背景を持つ人であっても、穏やかに人生の幕を下ろせる社会が実現するのではないでしょうか。
なお、この問題をより深く学ぶ際には、被差別部落の歴史や同和問題に関する専門書や資料に目を通すことが推奨されます。過去に実際どのような葬儀が行われ、地域によってどんな違いがあったのかを知ることで、さらに具体的な理解が深まるはずです。葬儀は誰にとってもいつか訪れる大切な行為であるからこそ、差別のない未来に向けて、この歴史を学び続ける意義は大きいと言えるでしょう。
興味をそそるブログ!!
1、幸福の科学を巡る現状と今後の展望 ~信者への献金や葬儀参加時の注意点も徹底解説~
2、モルモン教と日本社会の摩擦:勧誘・経済負担・葬儀文化のギャップ」
3、💡日本の政治に影響を与える宗教とは?創価学会・神道・旧統一教会…宗教と政治の関係を解説‼️



