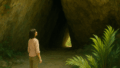はじめに:「外資になったら骨が粉々?」という噂
最近、ネットやSNSで「火葬の骨が粉々だった」「喉仏が残らなかった」といった口コミを目にしたことはありませんか?
その多くに共通して登場するのが、**東京博善(とうきょうはくぜん)**という名前です。
さらに深掘りしてみると、「外資系ファンドに買収されたから効率優先になった」という声まで──。
実際のところはどうなのでしょうか?
今回は、口コミをもとに東京博善の評判や背景事情を整理してみます。
東京博善とは?都内を牛耳る火葬場の民間会社
都内の6か所の火葬場を運営
東京博善は、以下の6つの火葬場を運営しています。
- 町屋斎場(荒川区)
- 桐ヶ谷斎場(品川区)
- 落合斎場(新宿区)
- 代々幡斎場(渋谷区)
- 堀ノ内斎場(杉並区)
- 四ツ木斎場(葛飾区)
これらはすべて民営火葬場で、東京都心部の火葬をほぼ一手に担っていると言っても過言ではありません。
外資系ファンドが関与?
2010年代後半より、外資系投資ファンド(例:カーライル・グループ)などが出資者として関与しているとの報道があります。
このことが、最近の“変化”に敏感な利用者の不安材料となっているようです。
よく見られる口コミとその実情
「骨が粉々で悲しかった」
「火力が強くなったのか、遺骨がほとんど灰のようだった」
「喉仏が残らなかったのがショック」
「まるで“処理”されたみたいで心が痛い」
こうした口コミは確かに複数確認できます。
火葬の火力や時間は年々効率化のために高められている傾向があり、それに伴い「遺骨の原型が残りにくい」と感じる遺族もいるようです。
ただしこれは、外資系の影響というより、火葬技術や設備の近代化の影響とも考えられます。特に高齢者や病気で骨が脆くなっているケースでは、火力の加減が難しいといった技術的背景もあります。
「流れ作業みたいで悲しい」
「火葬がとにかく早く終わる」
「立ち会いの時間が短く、感情の整理が追いつかない」
「施設は綺麗だけど、心のケアが薄い印象」
これは火葬場の混雑と回転率の問題に起因しているケースもあります。
東京博善が運営する斎場は非常に人気があり、日程も取りづらいため、どうしても時間がタイトになりがちです。
なぜこうした印象になるのか?考えられる3つの背景

1. 外資系による「収益化」の圧力
一部の利用者は、「効率重視=儲け優先」と感じるようです。
外資が関与しているという事実が、よりいっそうその印象を強めている面は否定できません。
2. 火葬技術の近代化と副作用
- 高火力化による時短
- 自動制御による省人化
これらは技術革新の成果でもありますが、「丁寧さ」が失われたように感じる人もいます。
3. 都市部ならではの制約
都内の火葬場はとにかく需要が多く、火葬→骨上げ→退出の時間がきっちり決まっています。
感情の余韻に浸る時間が取りにくいのは、施設運営側の都合だけでなく、地域的な事情も大きく影響しています。
では、どうすれば納得のいく火葬ができる?

🔸事前に希望を伝える(葬儀社経由)
「骨をなるべく残したい」「時間を丁寧に取りたい」といった希望は、葬儀社を通じて火葬場側に伝えることで、ある程度配慮されることがあります。
🔸他の火葬場も検討する
都内在住でも、たとえば八王子斎場や瑞穂斎場などの公営施設を選ぶことで、時間的なゆとりや丁寧な対応が得られることもあります。
🔸葬儀社の「経験値」を活用する
評判のよい葬儀社は、火葬場との関係性も築かれており、遺族の思いをきちんと汲んで調整してくれることが多いです。
まとめ:「東京博善=外資=悪」とは言い切れない
確かに、東京博善に関しては「外資化」「効率化」といったワードが先行し、ややネガティブな印象を持つ人も少なくありません。
しかし、それが全てのケースで“雑な扱い”につながっているわけではなく、現場は今も丁寧な対応に努めているのも事実です。
重要なのは、遺族がどういう送り方を望むかを明確にし、それをしっかりと伝えること。
そして、信頼できる葬儀社とともに、火葬場の選択肢も含めて最適な形を考えることです。
終わりに
効率化が進む社会の中で、最後の別れの時間だけは「丁寧に」過ごしたい——
そんな思いが、こうした口コミの背景にあるのかもしれません。